電磁場の非同次波動方程式
ヘヴィサイド(O.Heaviside)1885年とヘルツ(H.Hertz)1890年が集大成したMaxwell方程式系から、電場及び磁場が満たす非同次波動方程式を導きます。そして、電磁ポテンシャルA、φの非同次波動方程式について説明します。
単位系として非有利化Gauss単位系を用います。電磁気学の単位系については別稿「電磁気学の単位系が難しい理由」5.(4)をご覧下さい。
また、相対論的な4元ベクトルや、計量テンソルの表現としては別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」3.で説明した右側の定義を用います。
1.電磁場のMaxwell方程式系
(1)非有理化単位系
非有理化単位系で表した法則
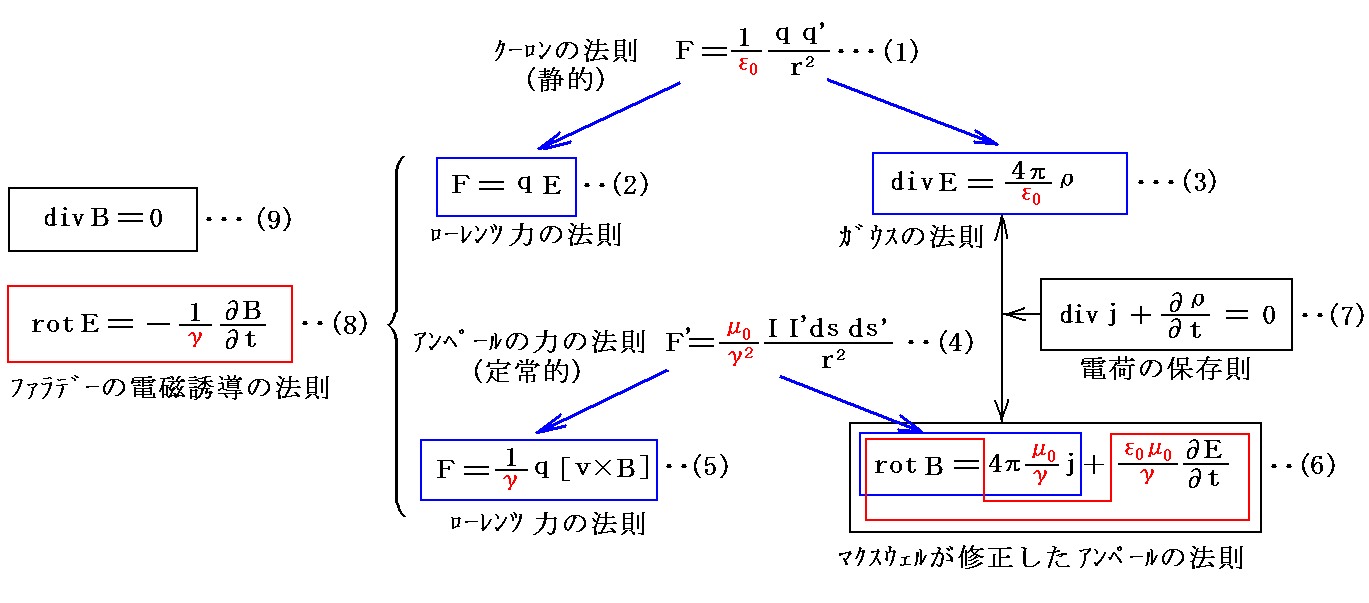
q、j、E、B、ε0、μ0、γは、(2)(3)(5)(6)(7)(8)等の式で互いに関係づけられているから、当然何らかの制約があるはずです。式をやりくりしてみたら別稿「電磁気学の単位系が難しい理由」1.(3)で述べたように
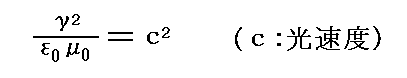
と言う関係を満たさなければならなかった。そして実験で測定してしてみると別稿「電磁気学の単位系が難しい理由」4.(1)で述べたように定数cは光速度だったと言うわけです。
このとき、3個の比例定数ε0、μ0、γに対して条件式は1個だけだから2個は任意に取れる。そのためその2個を一番簡単な置き方にしよう。そして、どの2個を選ぶかで3通りの単位系が考えられる。
(1)静電単位系:ε0=1、γ=1、μ0≒1/c2
(2)電磁単位系:μ0=1、γ=1、ε0≒1/c2
(3)ガウス単位系:ε0=1、μ0=1、γ≒c
もともと、静電気の研究から始まったので(1)の単位系がつくられた。しかし、電流の磁気作用が発見されてからは最も重要な応用は動電気的なものとなったので、(2)の単位系が重要になった。しかし、理論的な考察には次元の対称性から(3)も捨てがたい。
このように三種類の単位系が並立する事になったのは、電磁気学を展開するには4個の物理量[電荷q][電流I][電場E][磁場B]の導入がどうしても必要だったからです。そのとき、これらの導入には最低3個の比例定数(4個でなく3個で良いのは別稿「電磁気学の単位系が難しい理由」1.(3)2.で注意したように、そこのk1に1以外を与えても何の意味もないからです)が必要なのに、条件式は1個だけだからです。つまりこれらの単位系が並立する事の中に電磁気学の本質がある。
(2)有理化単位系
今日、広範に使われている
(4)MKSA有理化単位系:γ=1、μ0=4π×10-7[N/A2orH/m]、ε0≒107/(4πc2)[F/m]
については、別稿「電磁気学の単位系が難しい理由」5.(4)2.を参照されたし。
補足しますと、オランダの H.A.Lorentz や英国の Oliver Heaviside は 有理化されたガウス単位系 を用いています。
2.電場E、磁場Hの波動方程式
以下ではε0=1、μ0=1、γ≒c の非有理化Gauss単位系の方程式系で論じます。そのとき、この単位系ではB=Hですので、Bの代わりにHを用います。
(1)電磁場の方程式系
1.ヘヴィサイド・ヘルツのMaxwell方程式系
1.(1)で示したMaxwell方程式系を説明する。
まず、最初の2つは
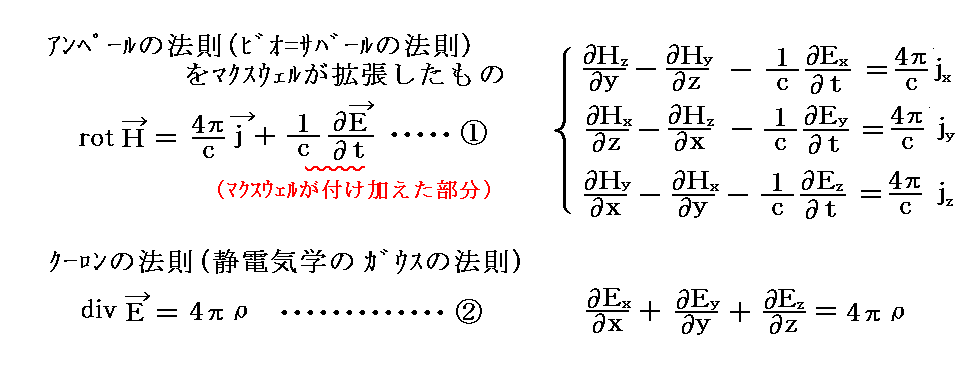
です。この2つは電荷や電流という物質が担う量と電磁場との関係を示している。これを今後①式、②式とする。
次の2つは
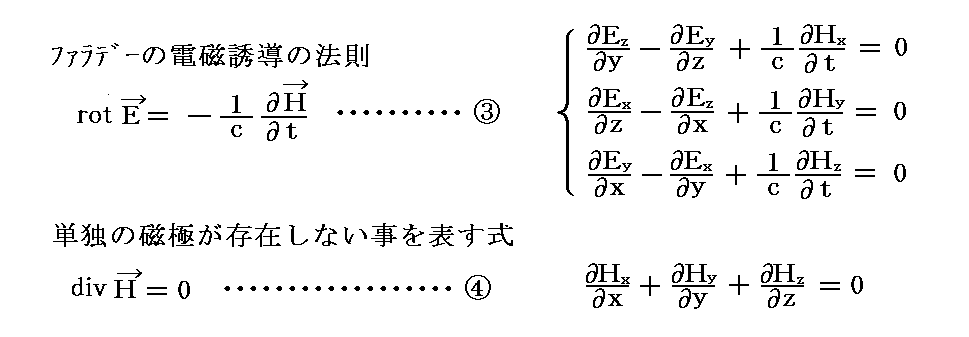
です。この2つは電場と磁場という二種類の場の間に存在する関係、あるいは電場、磁場そのものが持つ性質を表している。これを今後③式、④式とする。特に④式は磁場は連続している(つまり磁力線は連続している)ことを表している。これは②式が電気力線は必ず電荷から出発し、電荷に終わることを示しているのに対して、④式は磁力線についてはその様な事は無く、磁力線は常に連続しており、磁力線の終端である磁荷(つまり電気力線が出入りする電荷の様なもの)が存在しないことを示している。
以上の4式がヘヴィサイドとヘルツが整理統合したいわゆるMaxwell方程式といわれるものです。以後の議論はこの①~④式から出発する
2.電荷保存則(連続の式)
1.(1)で説明した電磁場の方程式系の中にはいわゆるMaxwell方程式①~④とは別に“電荷保存則”を表す(7)式
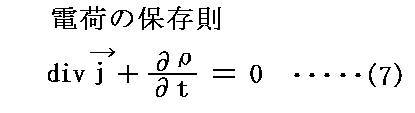
がありました。この(7)式は別稿「マクスウェルによるアンペールの法則の拡張」(2)で説明したように
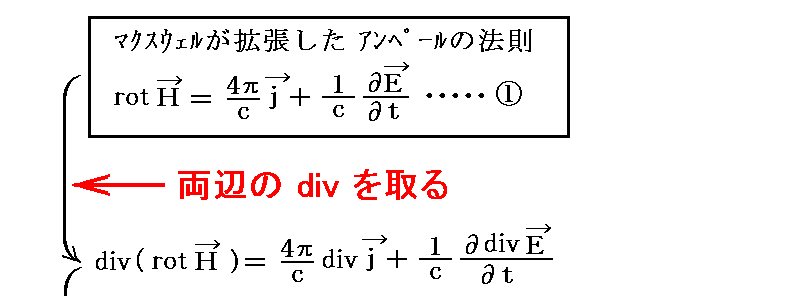
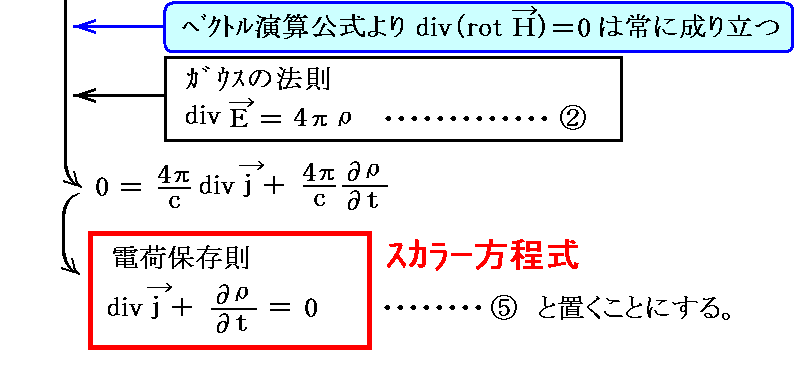
となります。このことは別稿「アインシュタインの特殊相対性理論(1905年)」3.(4)[補足説明4]でも説明しています。
そのため、電荷保存則(連続の式)(7)はMaxwell方程式①、②式と極めて密接な関係にあります。つまり、“電荷保存則(連続の式)”(7)式 は [Maxwell方程式①、②式] と等価です。
今後の使用に便利な様に、この“電荷保存則”(7)式を改めて⑤式と置くことにします。
[補足説明1]
このとき、先ほどの①、②式は、別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」5.(2)[補足説明3]で示した様に、[相対論的4元ベクトル方程式]と見なせます。この両辺の4元divを取ったとき、2階反変交代(反対称)テンソルの4元divは恒等的に0となるベクトル演算公式により、右辺も0となって“電荷保存則”は直ちに導けます。
実際の計算は別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」5.(2)[補足説明4]で示した様に
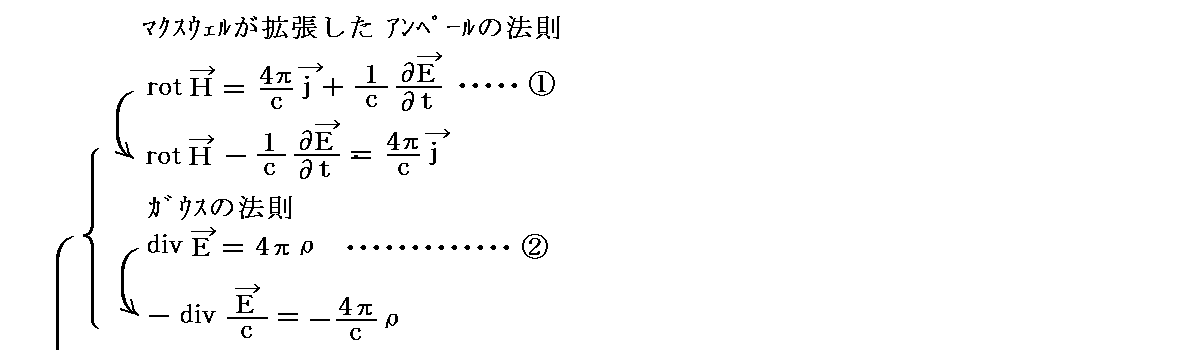
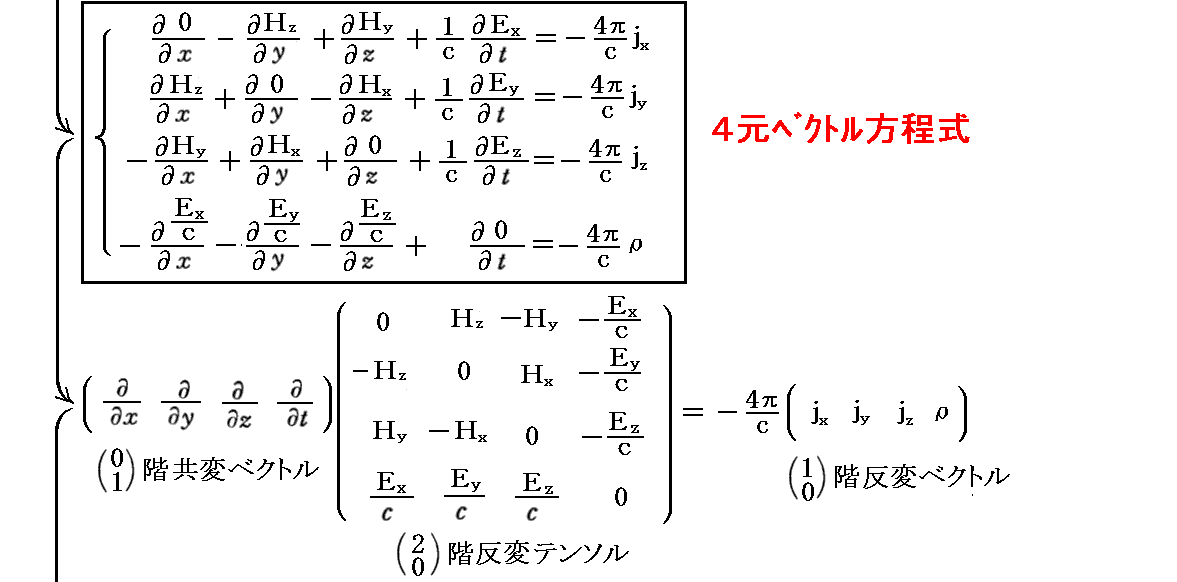
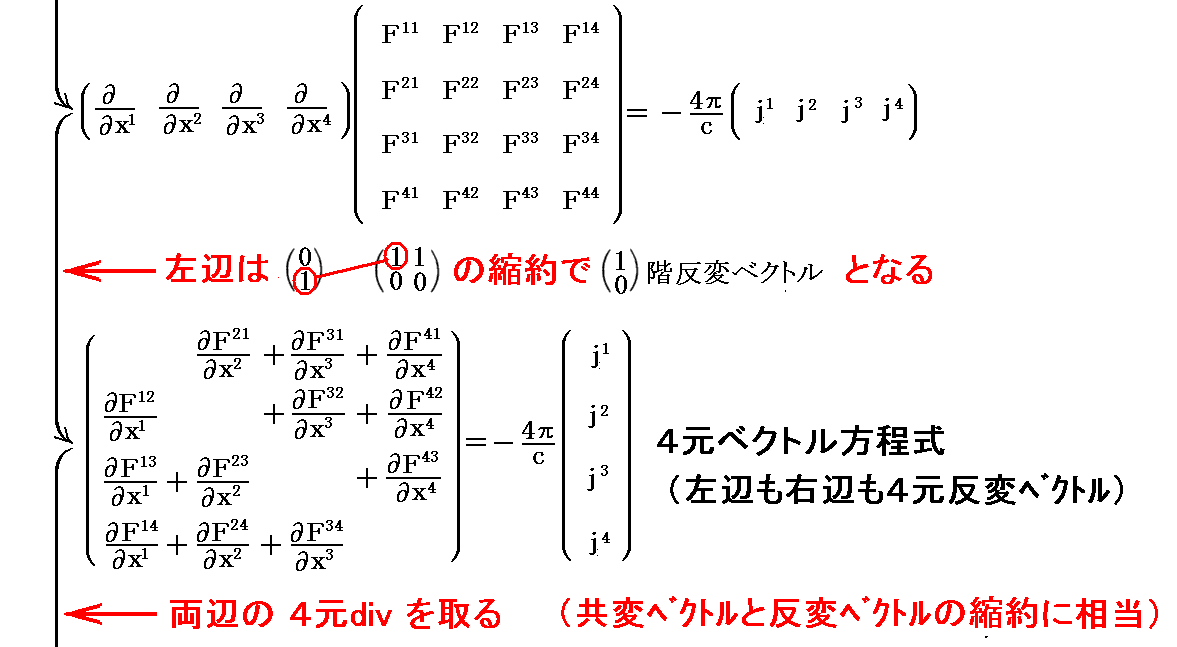
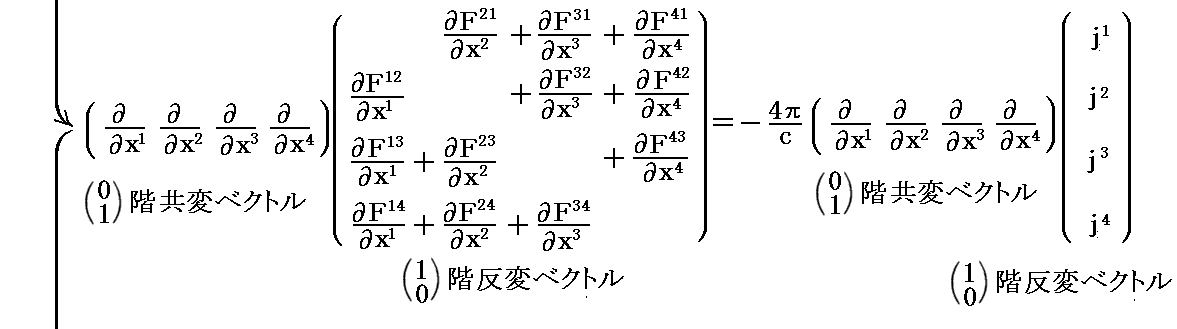
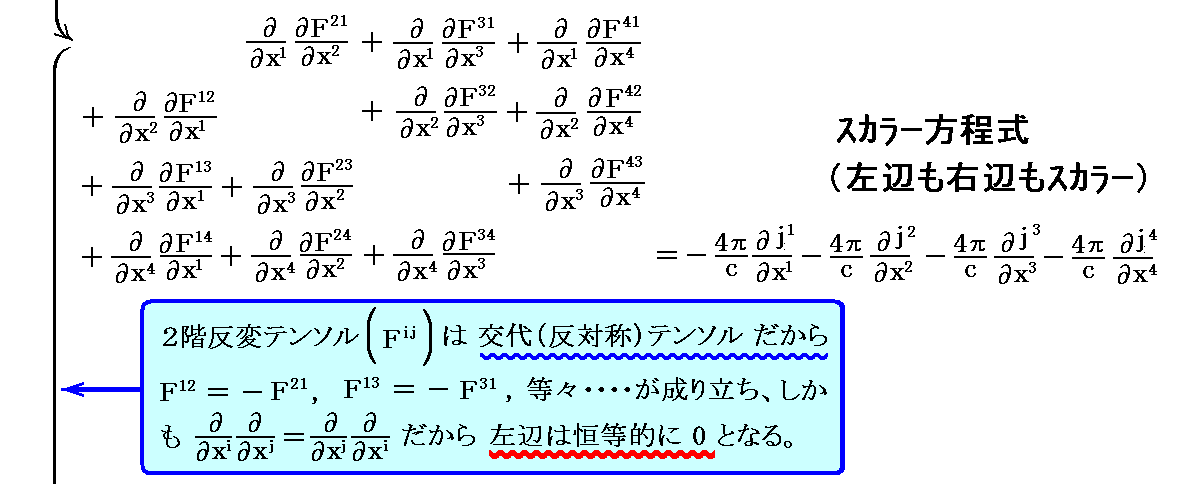
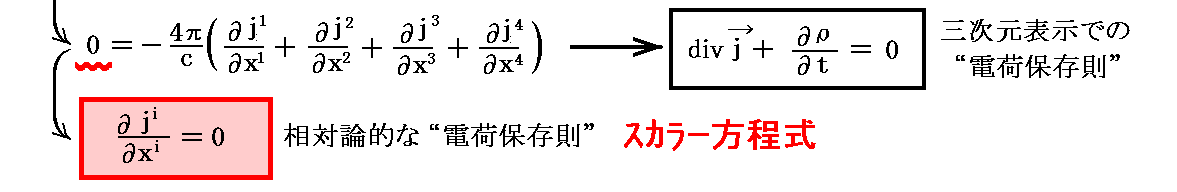
となる。
要するに、本文中で示した、“電荷保存則(連続の式)”⑤式 は [Maxwell方程式①、②式] と等価である事の証明を、相対論的な4元divで一気に行えばこうなるということです。
さらに補足しますと、上記の式変形について3.(3)3.[補足説明2]もご覧下さい。
3.ローレンツの力の法則
1.(1)で説明した電磁場の方程式系の中には “いわゆるMaxwell方程式系” とは別に“ローレンツの力の法則”(2)、(5)式がありました。
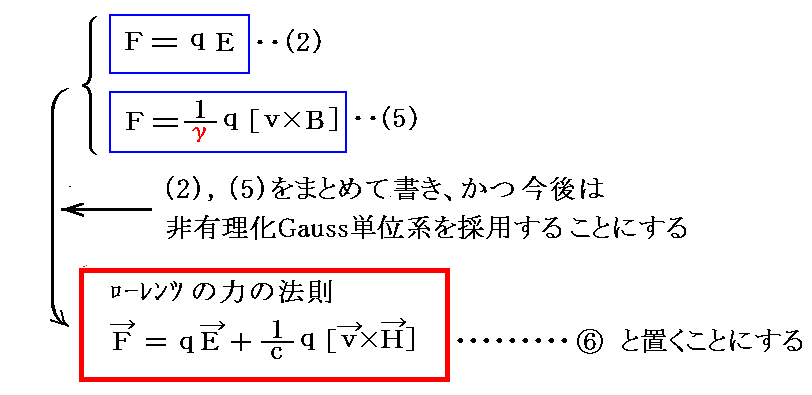
この2つをまとめて、今後⑥式と置くことにする。
“いわゆるMaxwell方程式”①~④式 は電場、磁場間の関係と電場、磁場と物質(電荷密度、電流密度)の間の関係を与えるものですが、この中には物質(電荷密度、電流密度)に働く力と電場、磁場との関係式が抜けています。ここで取り上げる“ローレンツの力の法則”は、その抜けている関係式を与えるものです。
我々は電磁場の存在を直接観測することはできません。我々は荷電粒子の受ける力(加速度)を通してしか電磁場を認知できないのです。従って電磁場を観測可能な物理現象に関係付けるこの“ローレンツの力の法則”は必須の法則です。
[補足説明1]
そのとき、前項の[補足説明1]で説明した様に “電荷保存則” と “Maxwell方程式①、②式” は密接に関係しましたが、“ローレンツの力の法則”
も “Maxwell方程式①、②式” と密接に関係します。
実際、別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」4.(2)で説明した様にローレンツの力の法則の力を4元力表示に拡張すると、4元力の3次元表示は別項「4元速度、4元加速度と4元力」5.(3)で説明したように
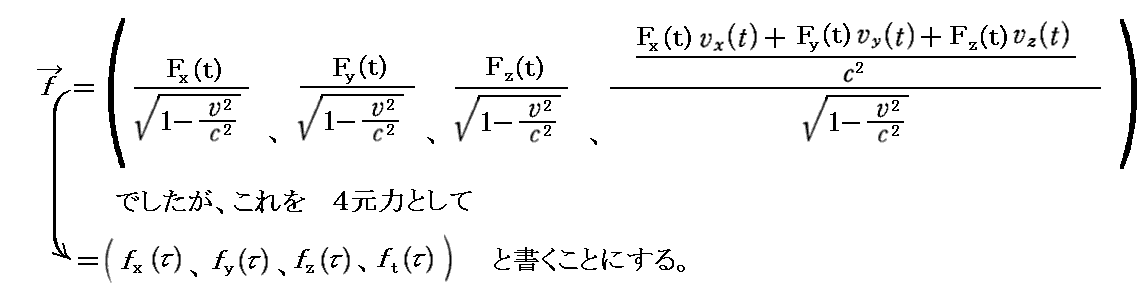
ここで、S’系はS系のx軸に沿って速度Vでx軸の正方向へ移動しているとしてます。またその移動速度を電荷の移動速度vと混同しないように大文字の“V”で現しています。上記成分表示式の分母の平方根記号内のvは座標系の移動速度ではなくて“電荷の移動速度”です。それは座標時を固有時に置き換える関係で出てきた速度なのですから。もちろん電荷の移動速度vは座標系の移動速度Vとは何の関係もありません。
この第4成分 f t の表現を “ローレンツの力の法則” により電磁場(EとH)と4元速度u による表現に置き換えると
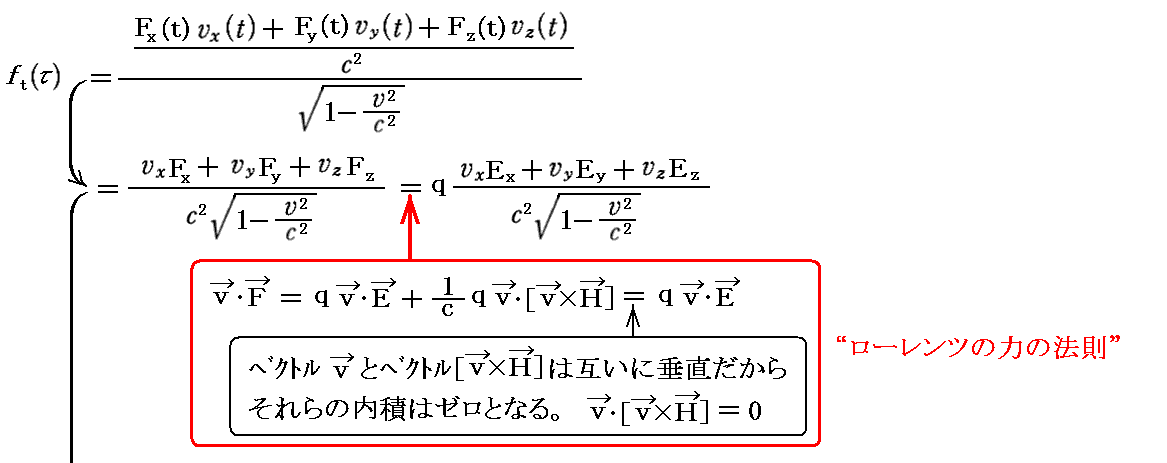
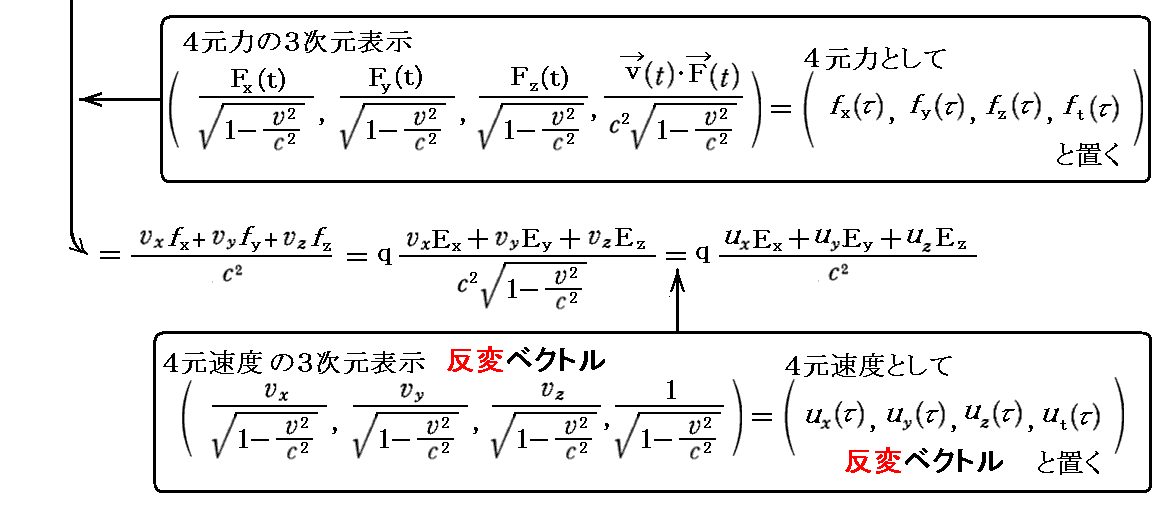
と成ります。このとき用いた4元速度の 3次元表示 と 4元表示 の関係は別稿「4元速度、4元加速度と4元力」2.(3)を復習されたし。このように、電磁場中で電荷に対して成される仕事が電場によるものしか現れないのは、磁場による力が電荷の移動方向に対してつねに垂直にしか働かないからです。
同様にして4元力のすべての成分を書き記すと
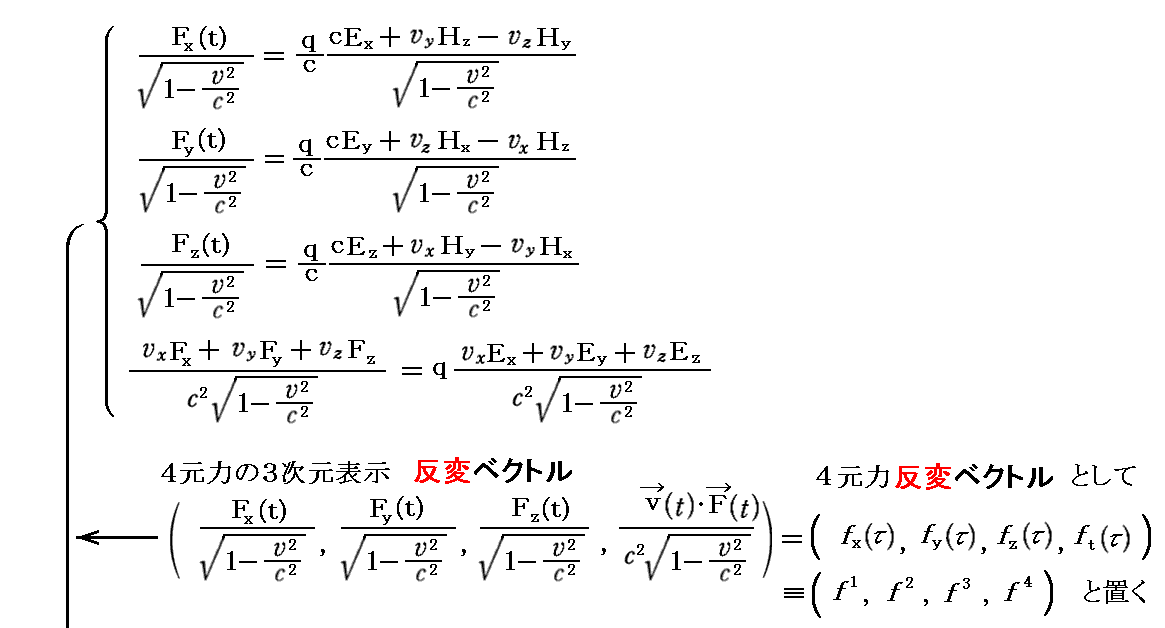
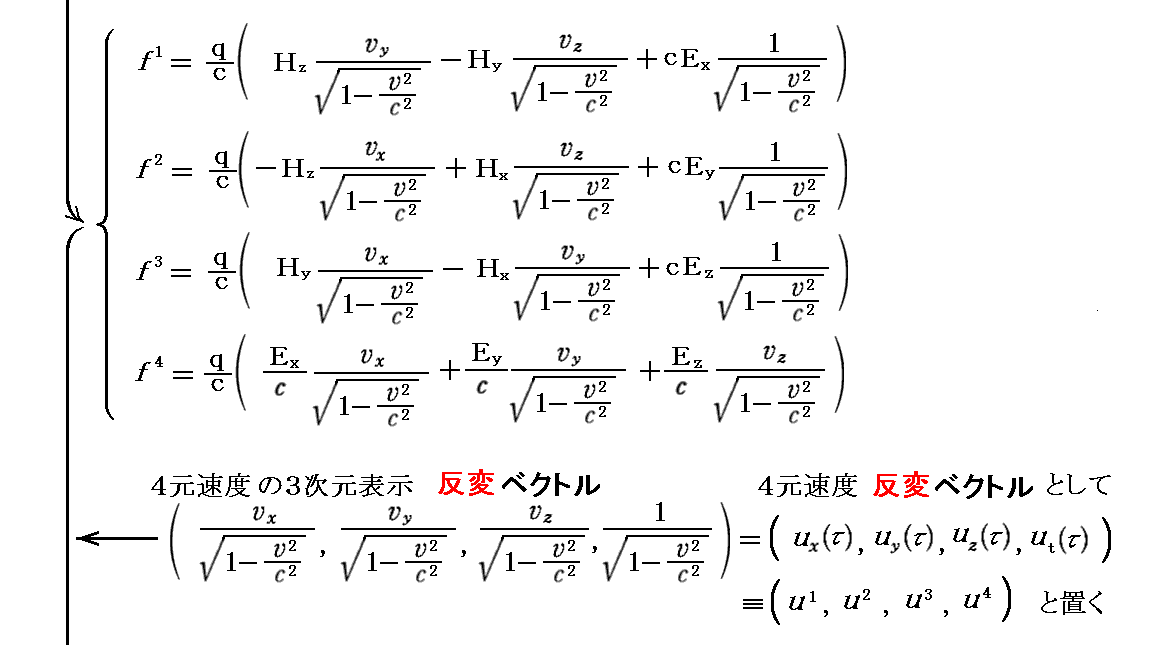
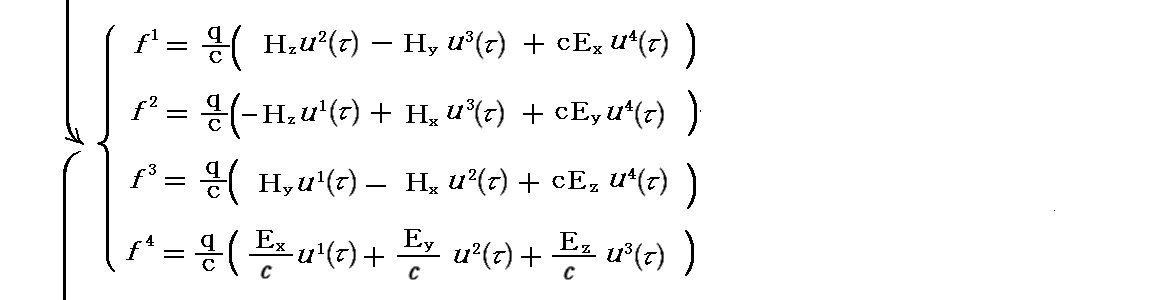
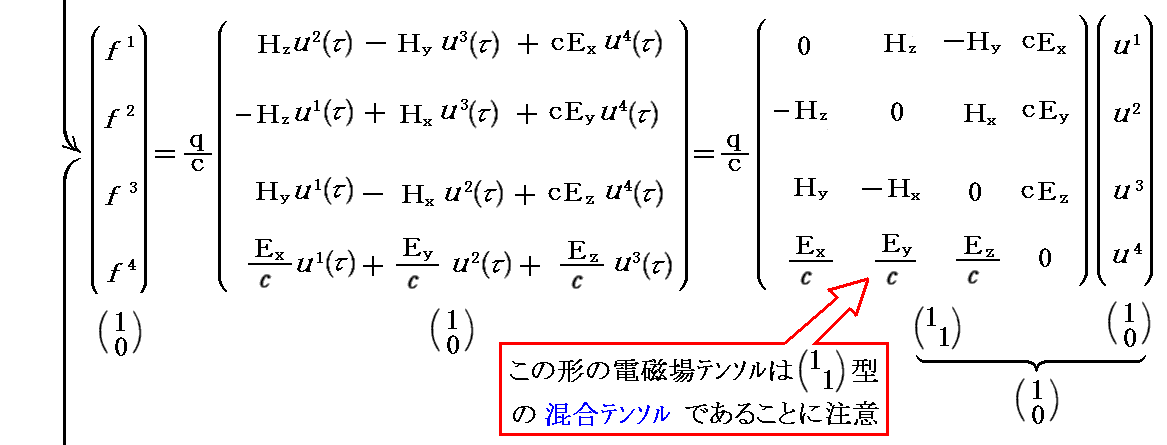
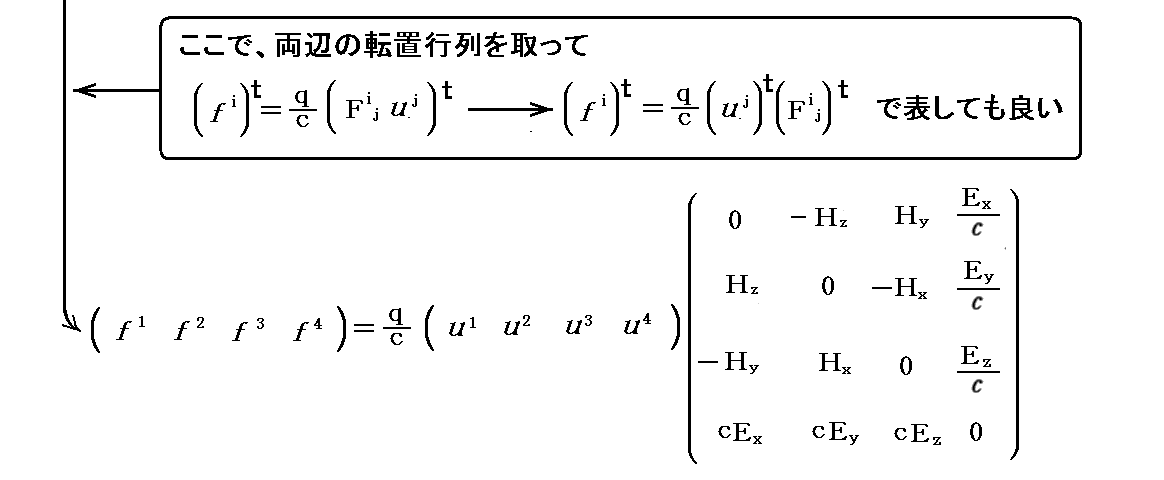
いずれにしても相対論的な“ローレンツの力の法則”は
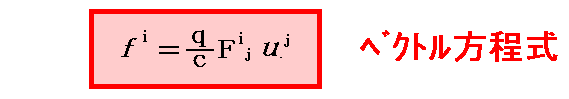
となります。上記の式は “4元速度” と “4元力” を用いた相対論的な表現にしてある。上記の“4元電磁場テンソル”Fijが2階混合テンソル
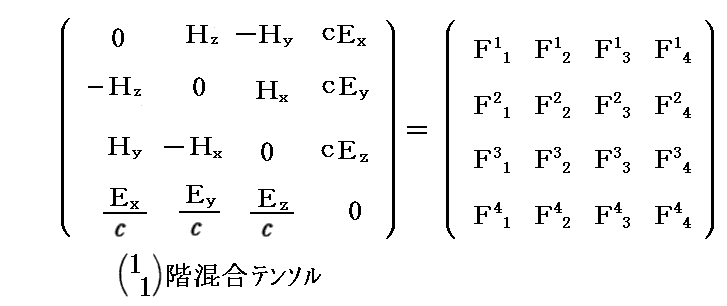
であることは別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」5.(2)[補足説明2]でご確認ください。
【 2階反変テンソル表現 】
補足しますと、先ほど4元速度として反変ベクトル表示を用いましたが、以下の様に共変ベクトル表示を用いることもできます。そのようにすると、電磁場テンソルは必然的に2階反変テンソルの形になります。
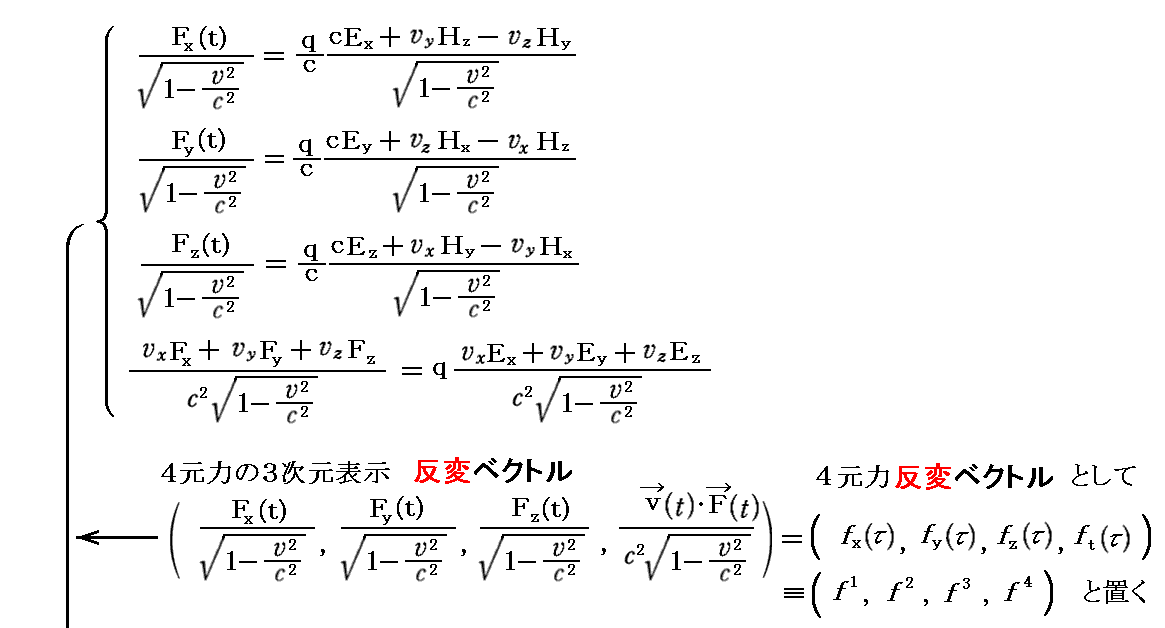
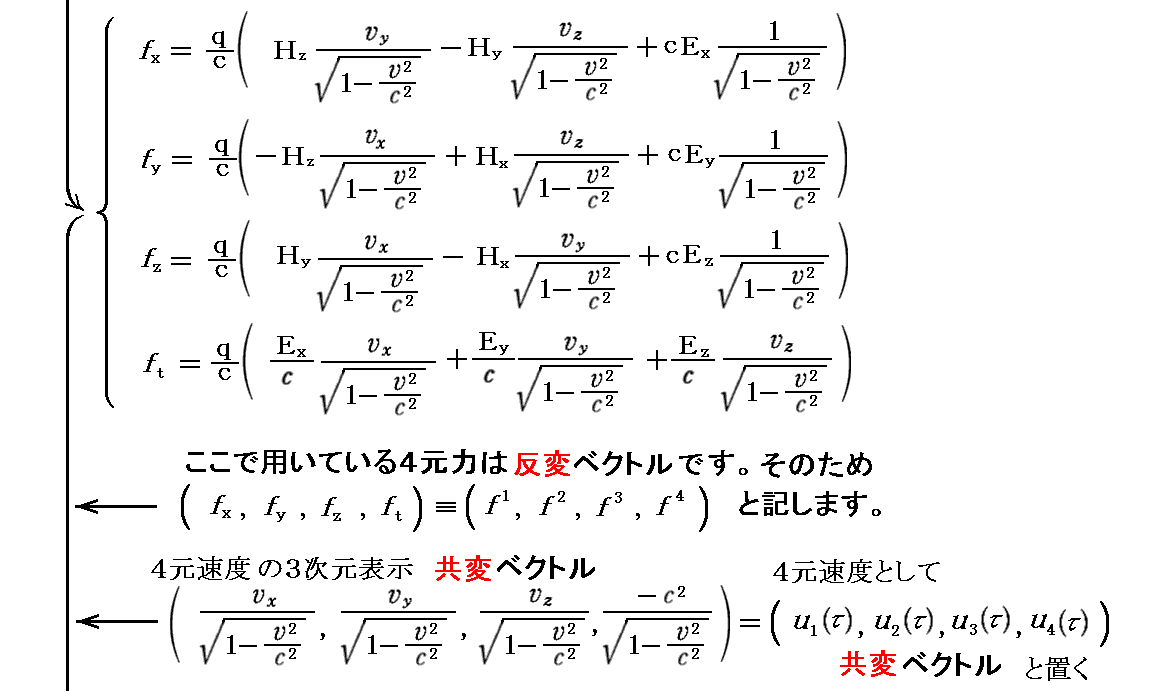
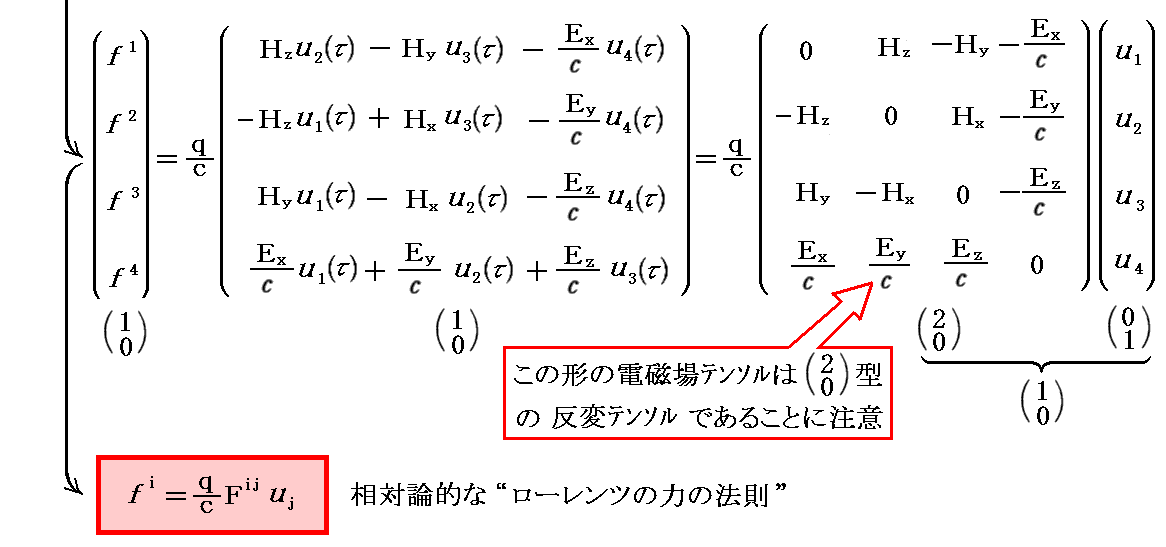
実際、上記の“4元電磁場テンソル”Fijが2階反変テンソル
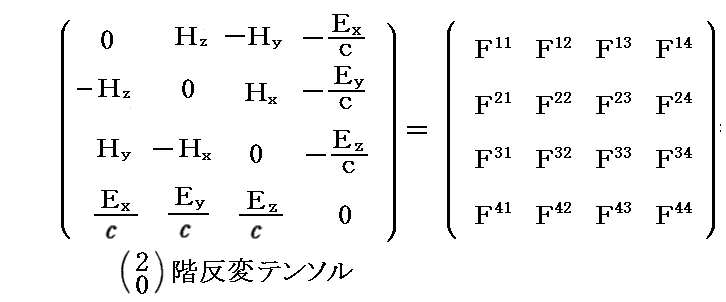
であることは別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」5.(2)[補足説明2]でご確認ください。
【 2階共変テンソル表現 】
さらに補足しますと、最初のローレンツの力の法則の両辺を共変ベクトル表示にすると
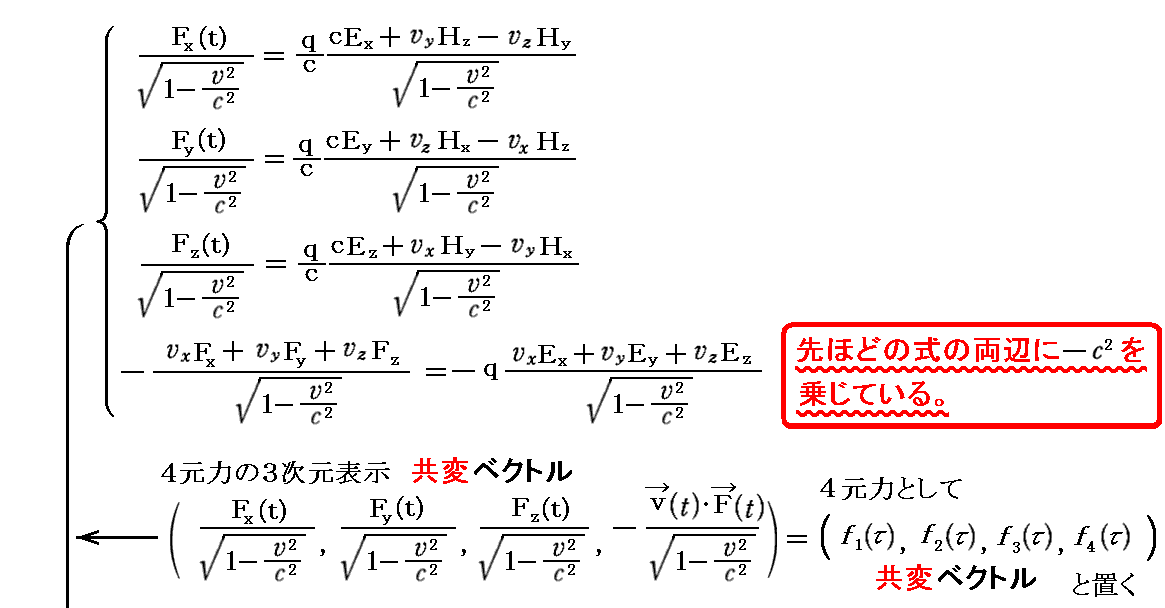
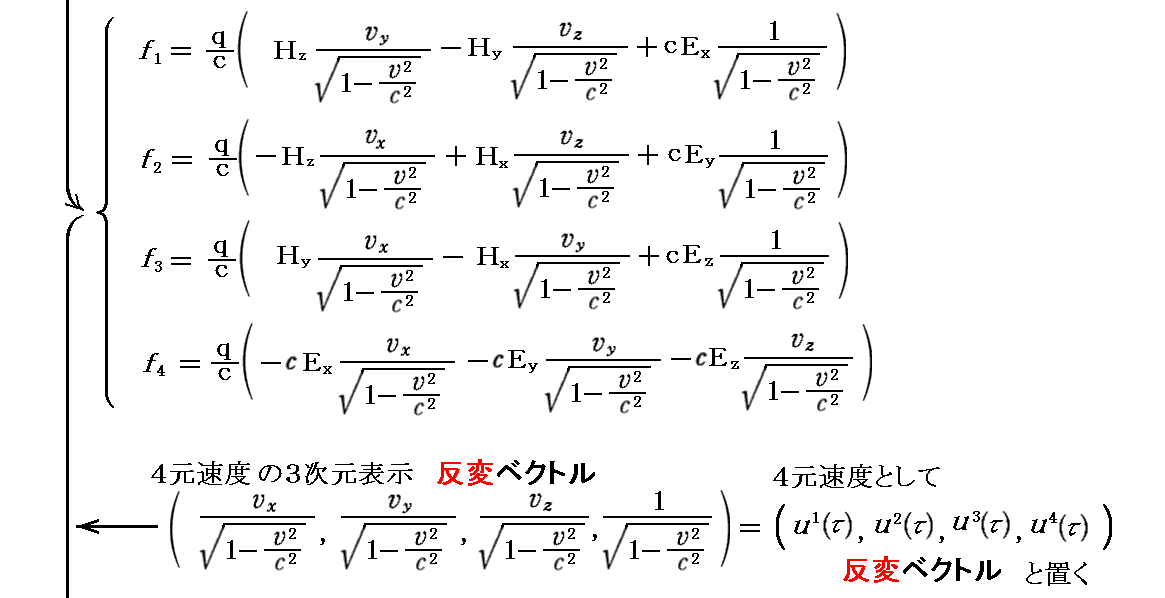
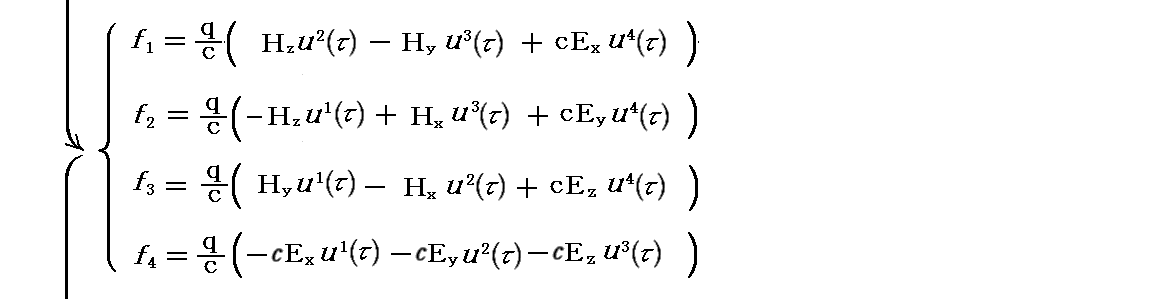
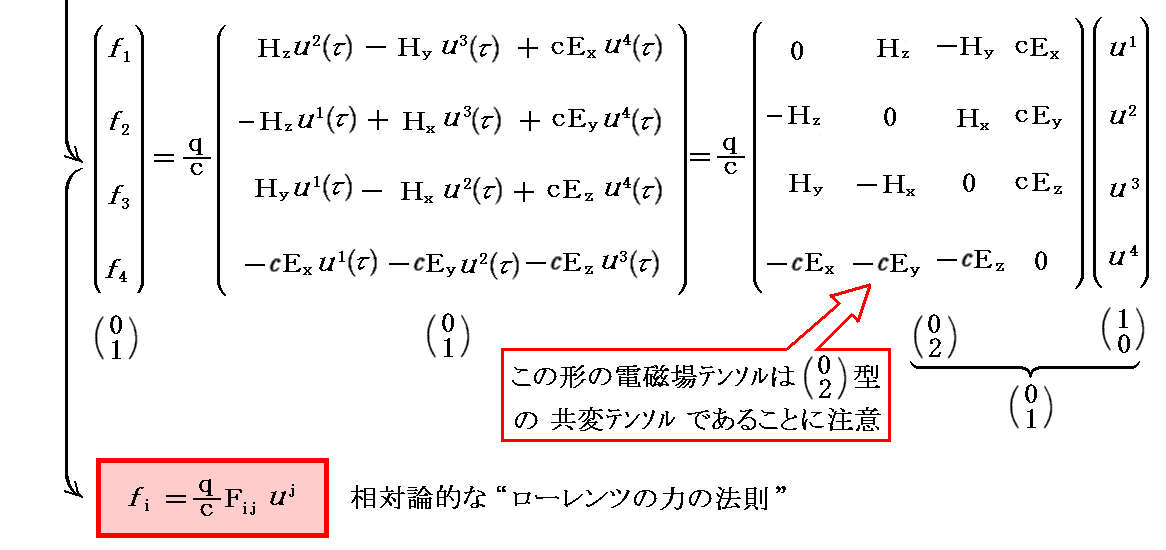
となります。つまり、右辺の4元速度ベクトルを反変表示のままにすると、電磁場テンソルは必然的に2階共変テンソルの形になります。実際、上記の電磁場テンソルが2階共変テンソル
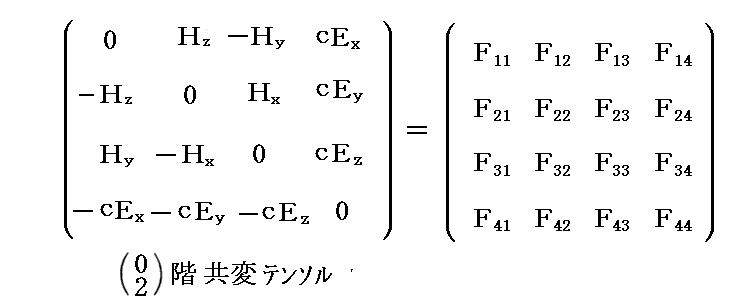
であることは別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」5.(2)[補足説明2]でご確認ください。
上記式変形の途中で、4元速度ベクトルの3次元表示として共変ベクトル表示を用いると、以後の変形は以下の様になります。
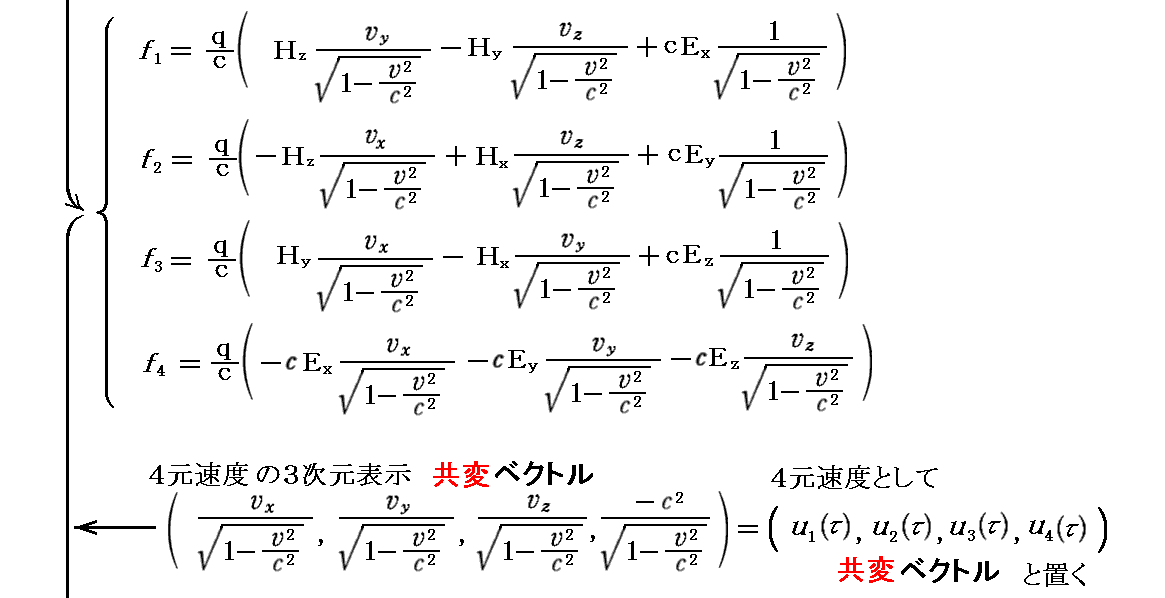
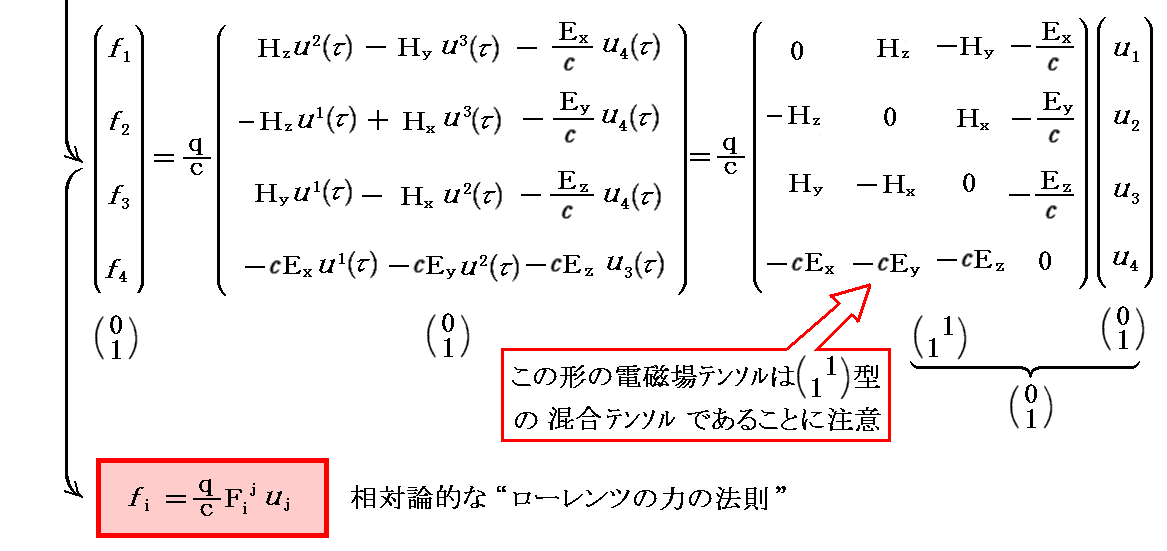
つまり、右辺の速度ベクトルを共変表示にすると、電磁場テンソルは必然的に(11)型2階混合テンソルの形になります。実際、上記の電磁場テンソルが(11)型2階混合テンソル
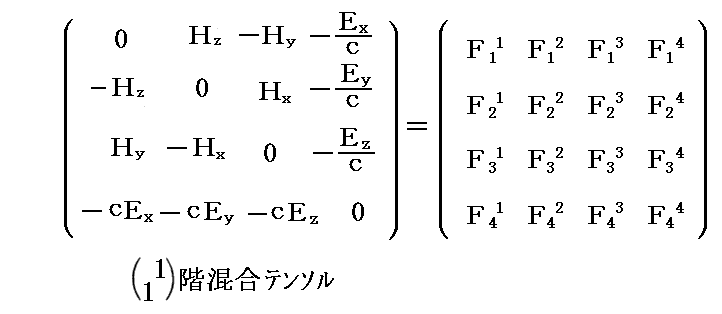
であることは別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」5.(2)[補足説明2]でご確認ください。
補足しますと、ここでは“4元速度”と“電磁場テンソル”で表現しましたが、4元速度の代わりに“4元電流密度”で表す事もできます。
結局、4元力と4元速度を共変ベクトル表現、反変ベクトル表現のいずれを用いるかに応じて電磁場テンソルを2階混合テンソル、2階反変テンソル、2階共変テンソルのいずれかに調整できます。これらの形については別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」5.(2)[補足説明2]でご確認ください。
ここに出てきた“反変・共変”の概念と、その間を取り持つ“計量テンソル”([補足説明2]参照)の概念が理解できていない方は別稿「基底ベクトル・双対基底ベクトルと反変成分・共変成分(計量テンソル・クリストッフェル記号・共変微分とは何か)」 をご覧下さい。
ここで、出てきた電磁場2階テンソルはいずれも、2.(1)2.[補足説明1]で説明する(2,0)型2階反変テンソルと、物理的には同じものです。そしてこのテンソルは、そこで説明した様にMaxwell方程式①、②式の左辺
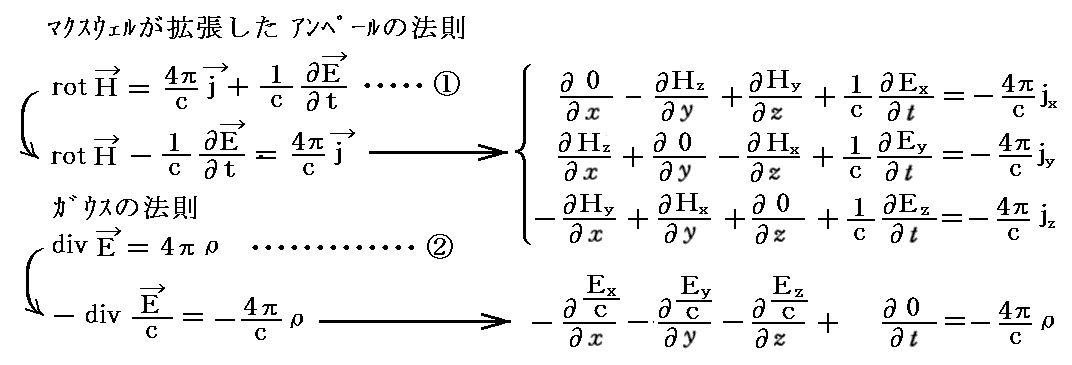
から出てくるものです。
故に “ローレンツの力の法則”⑥式 は [Maxwell方程式①、②] と、密接に関係することによって、最初に述べた“電磁場を現実の物理(力学)現象に関係付ける”ことを実現しています。
以上は電磁場テンソルを用いた表現でしたが、第3章との関連を見越して、電磁ポテンシャルを利用した表現に変換しておきます。その事を、できるだけ多くの表示形式について説明します。
以下の議論から解る様に、“電磁場テンソル”は“4元電磁ポテンシャルベクトル”の“4元回転演算”で得られる2階テンソルです。(“4元回転演算”については3.(1)3.[補足説明2]をご覧下さい。)
そのとき、その特質から明らかな様に、反変テンソルや共変テンソルを構成する場合には演算としての意味を持つのですが、混合テンソルを構成する演算としては意味を持たないのでしょう。
[補足説明2]
本稿ではGauss単位系(非有理化-磁場H)を採用し、相対論的な4元ベクトルや、計量テンソルの表現として別稿3.で説明した右側の定義を用いていることを忘れないで下さい。
まず1906年3月のM.Planck論文から始めます。その論文でPlanckは相対論的に正しい運動方程式
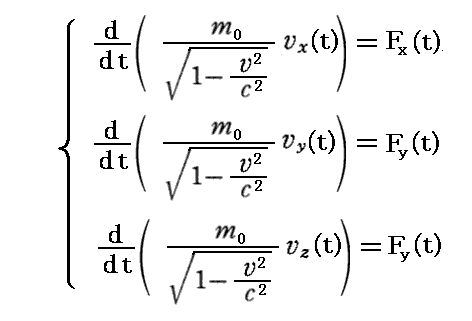
を導きます。これは3次元表示での相対論的方程式ですが、完璧に正しい式です。しかし、相対性理論ではすべての量、すべての方程式は4元化されるべきです。
運動方程式もそうあるべきで、その4元化は以下の手順でなされる事を別稿「4元速度(4元運動量、4元電流密度)、4元加速度と4元力」5.(4)で説明しました。
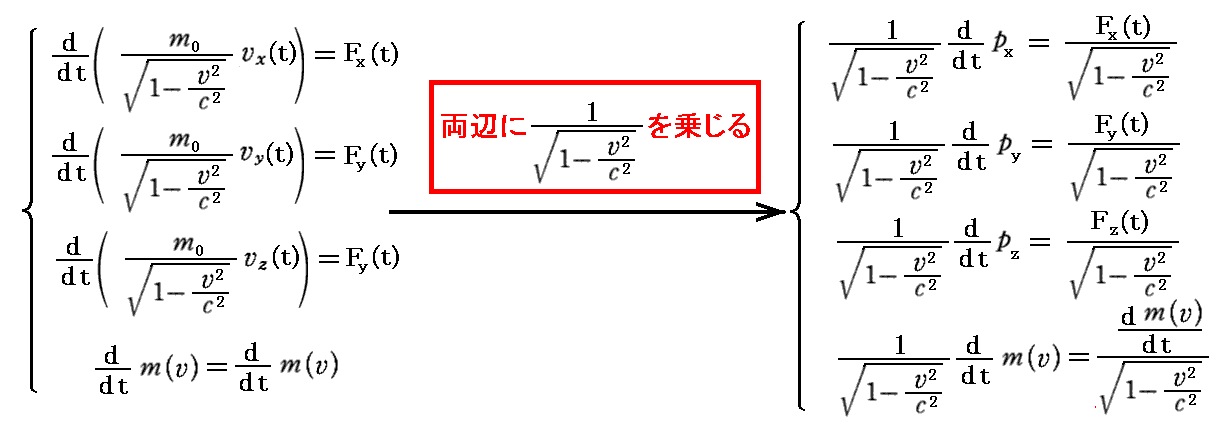
このとき、第4成分も付け加えて4元化するためには、両辺に
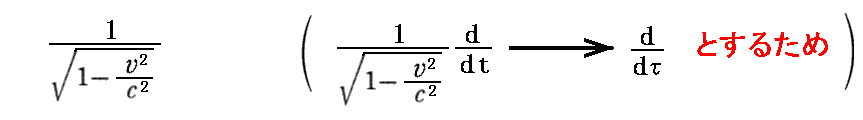
を乗じなければいけません。なぜそうしなければならないのかは前記別稿5.(4)を復習されてください。このとき上記の→右側の表現は、下記の4元ベクトル方程式表現と等価です。
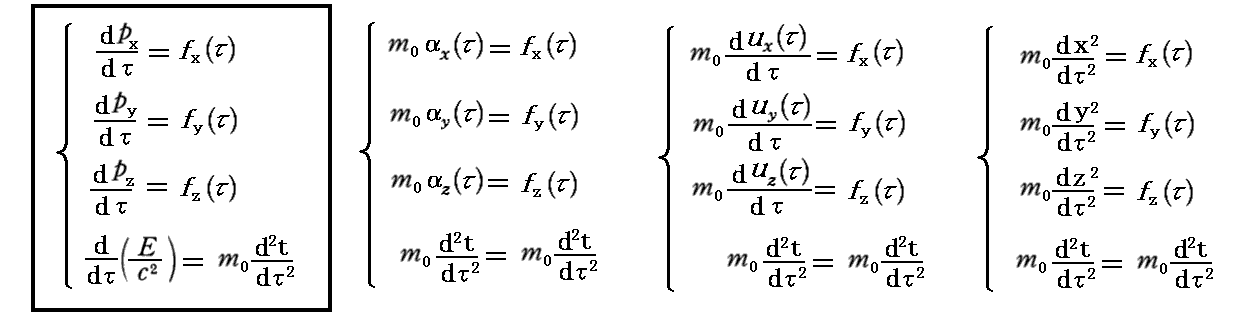
このときm0は固有質量、τは固有時です。またp、α、uはそれぞれ4元運動量、4元加速度、4元速度を表します。
ここでは別稿「電磁場中の荷電粒子の運動」との比較を考慮して上記一覧の左端の表現を用います。Gauss単位系(非有理化-磁場H)に書き換え、力の具体的形として“ローレンツの力の法則”を利用すると“4元運動方程式”は以下の様になります。ただし、そのとき
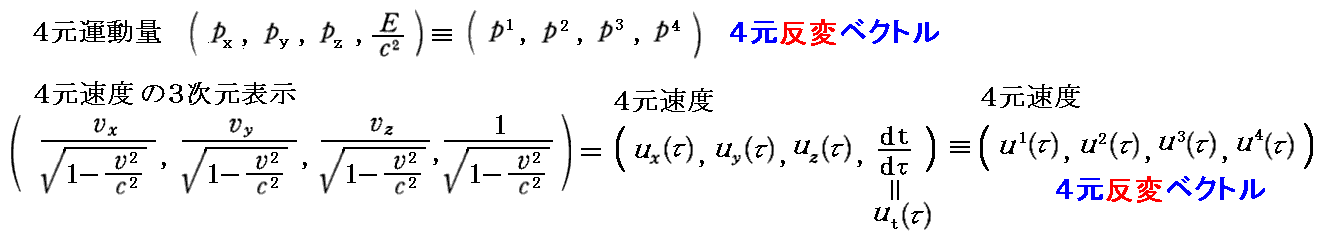
と置き換えています。
つまり、最初は速度ベクトルとして反変ベクトル表示を用います。そうすると電磁場テンソルは必然的に(1,1)型混合テンソルとなります。そのため以後の展開は下記の様になります。
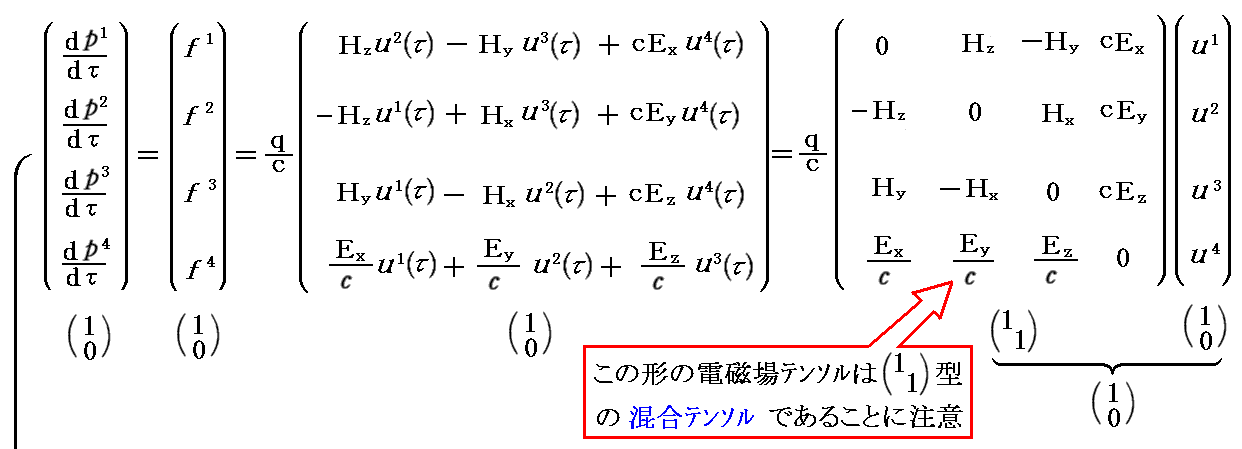
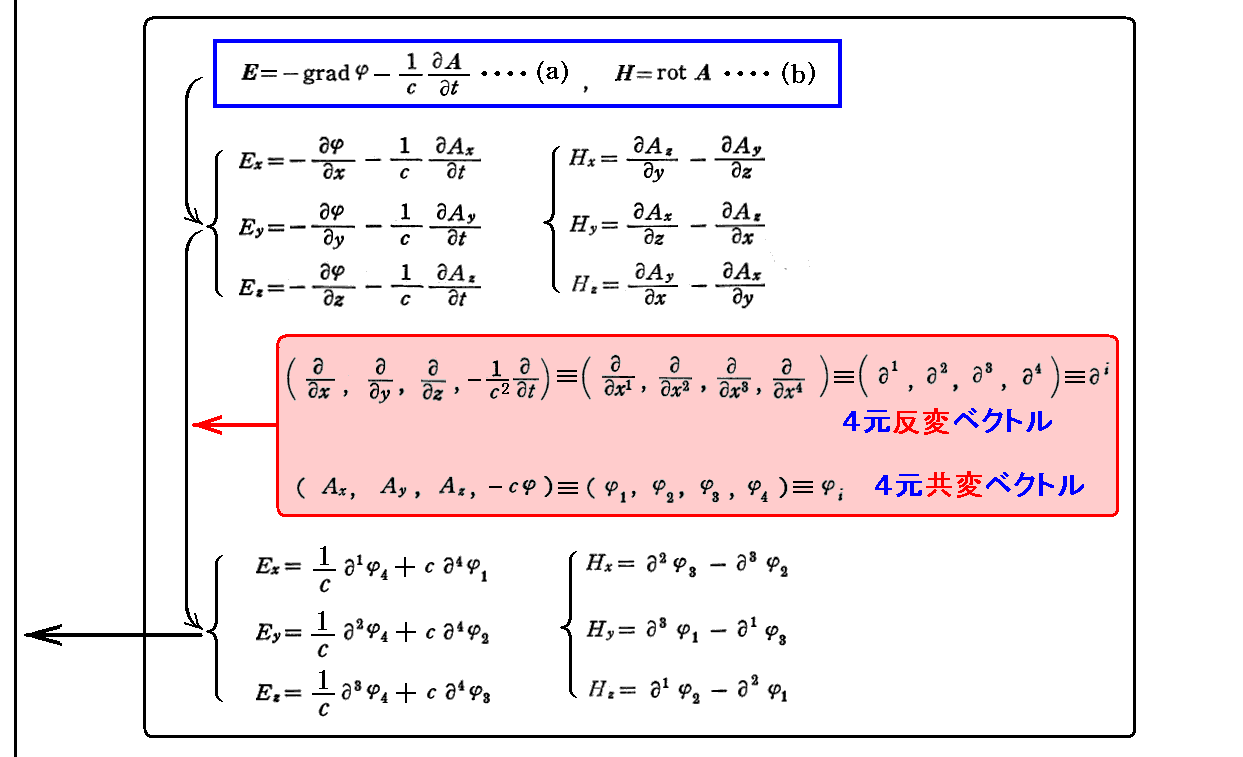
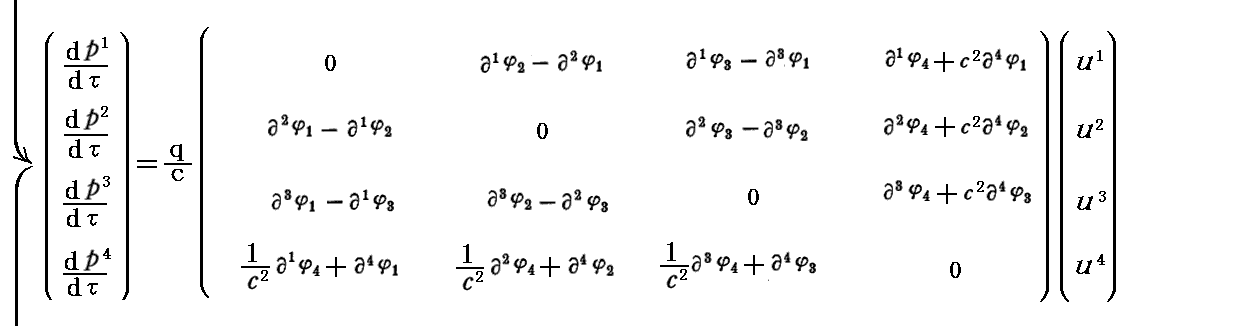
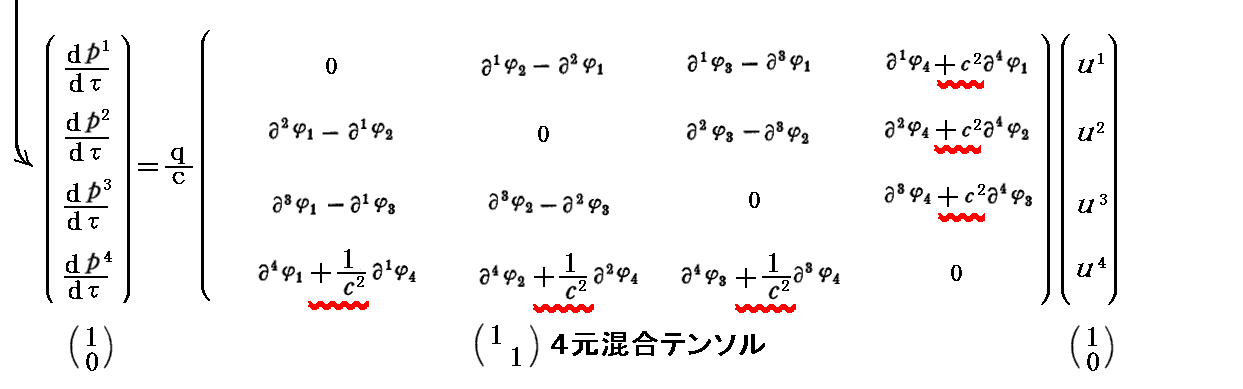
上記で電磁場テンソルを3.(1)で導入する電磁ポテンシャルで置き換えていますが、このとき(1,1)型混合テンソルの行列表現の第4列目の表示と、第4行目の表示が、赤波線で示している様に他の(行・列)要素と揃った形にならないことに注意してください。そのため、混合テンソル形式の表示では、反対称テンソルには成りません。つまり、4元回転演算という操作が(1,1)型混合テンソルを作り出すときには、意味を持たない。
補足しますと、“ミンコフスキー時空”の“計量テンソル”を用いて変形すると様々な表示形式の方程式に変更できます。
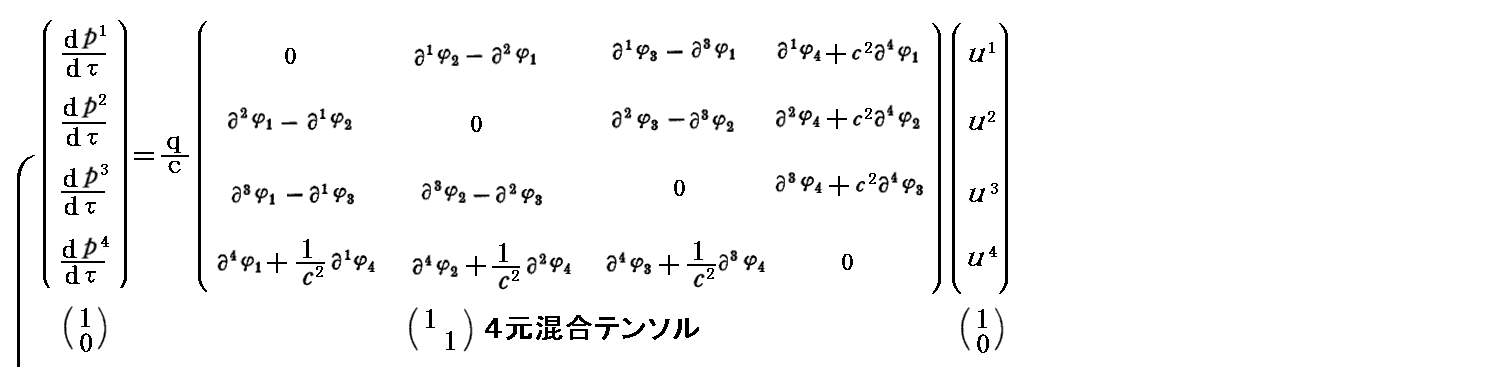
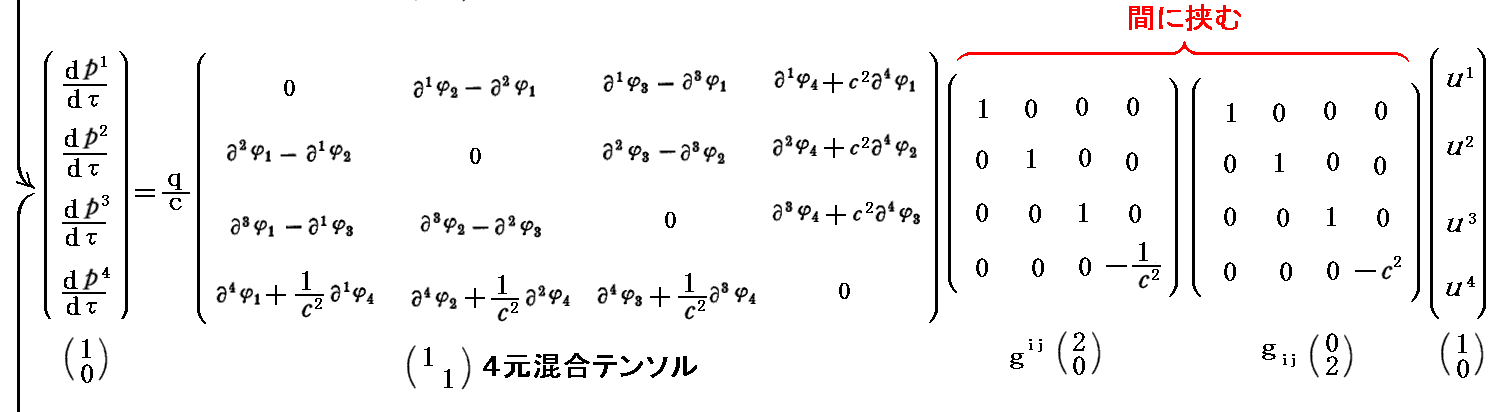
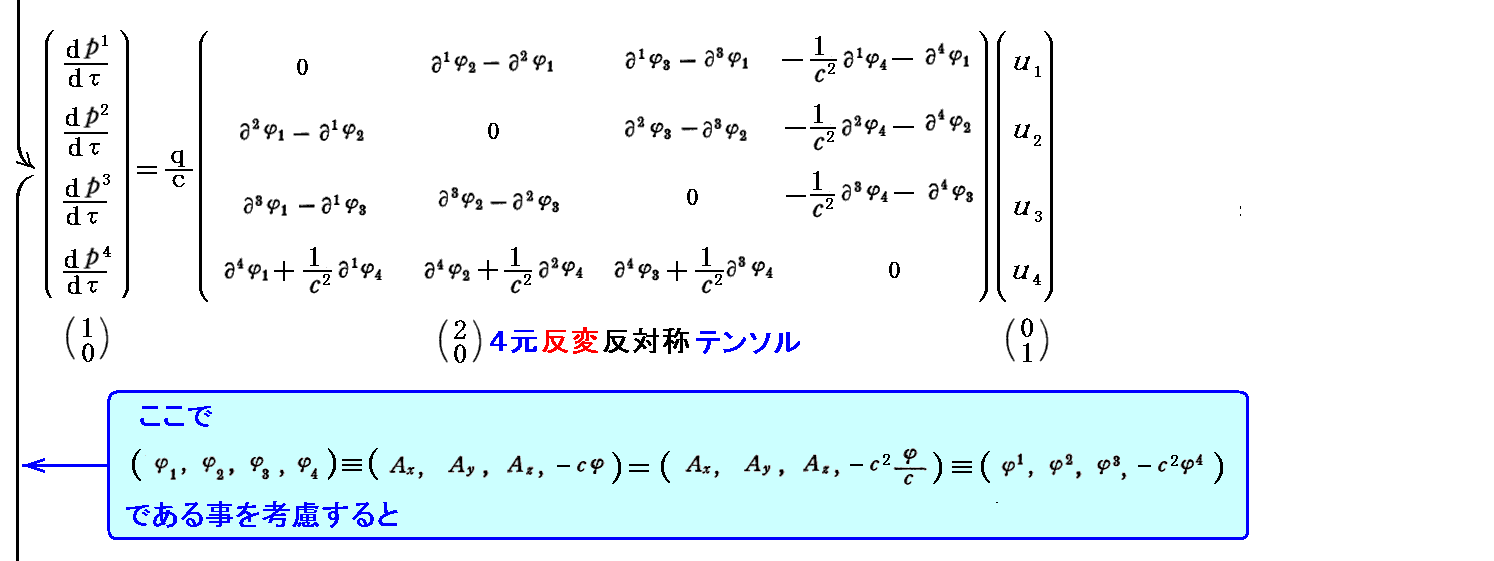
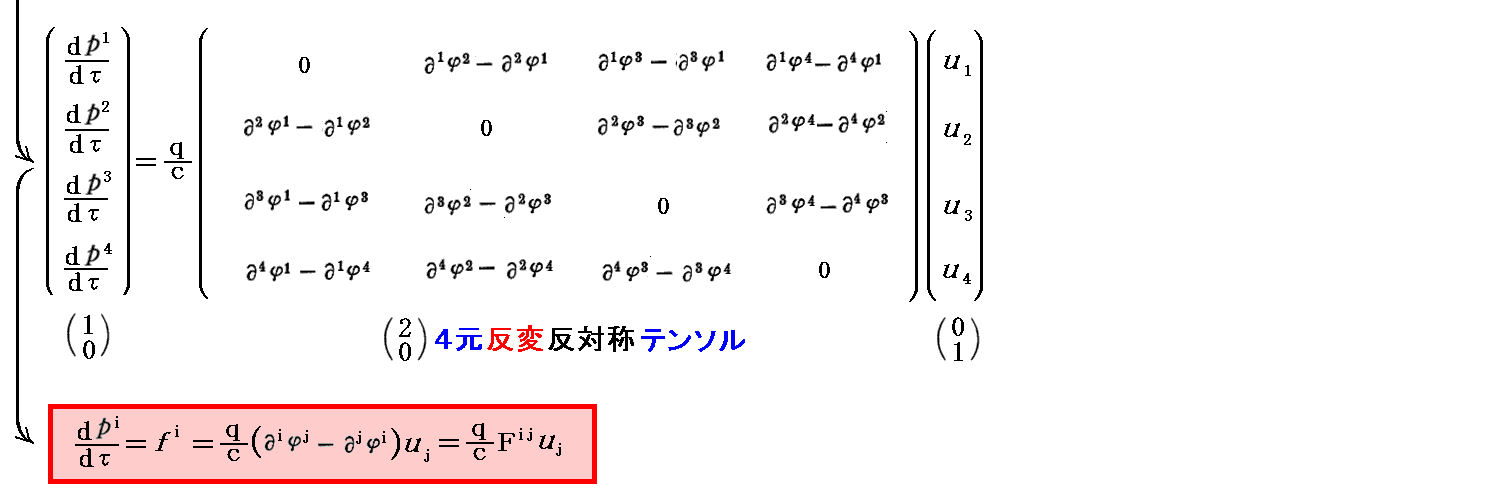
ここで注意して欲しい事ですが、上で求めた4元反変テンソルや次で求める4元共変テンソルの第4列、第4行は他の行・列要素の表現と同じ形になっており、反対称テンソルである事が実現されています。そのため、4元回転演算という操作が意味を持ちます。
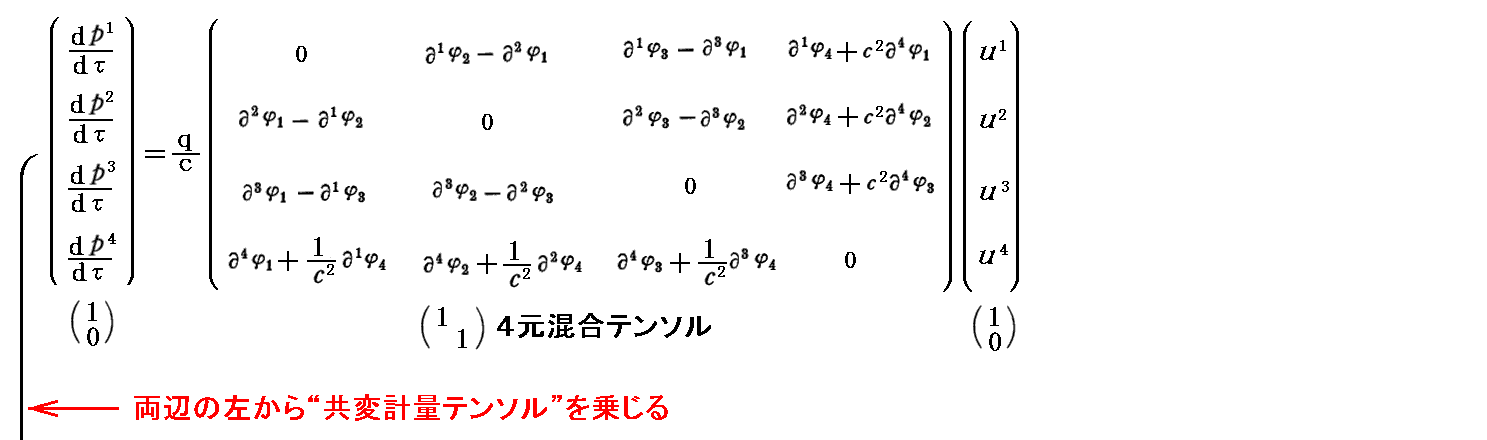
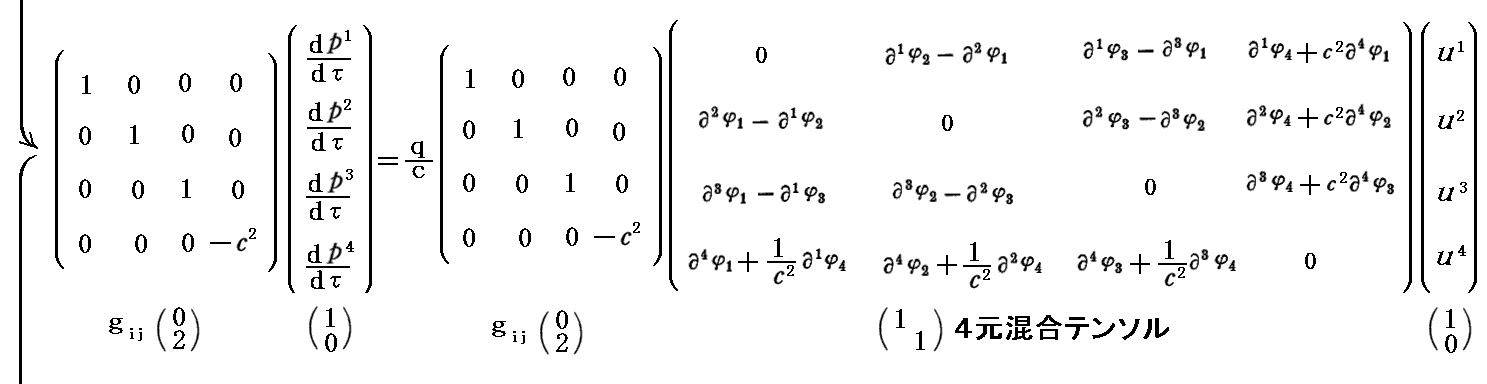
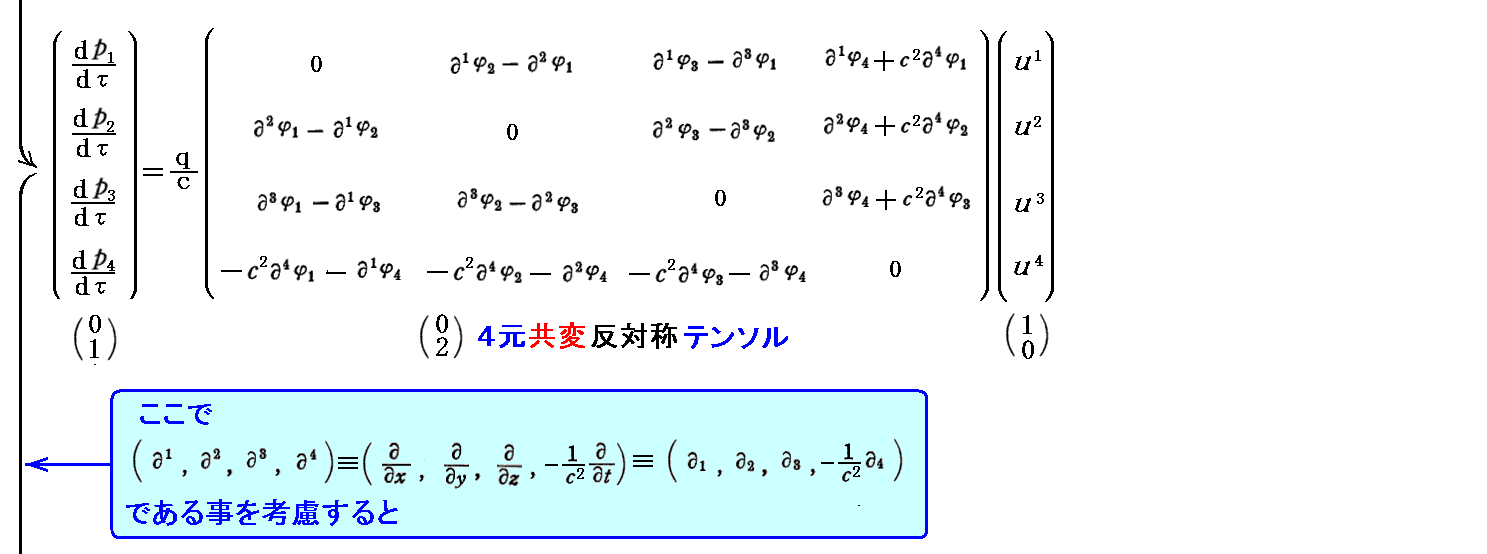
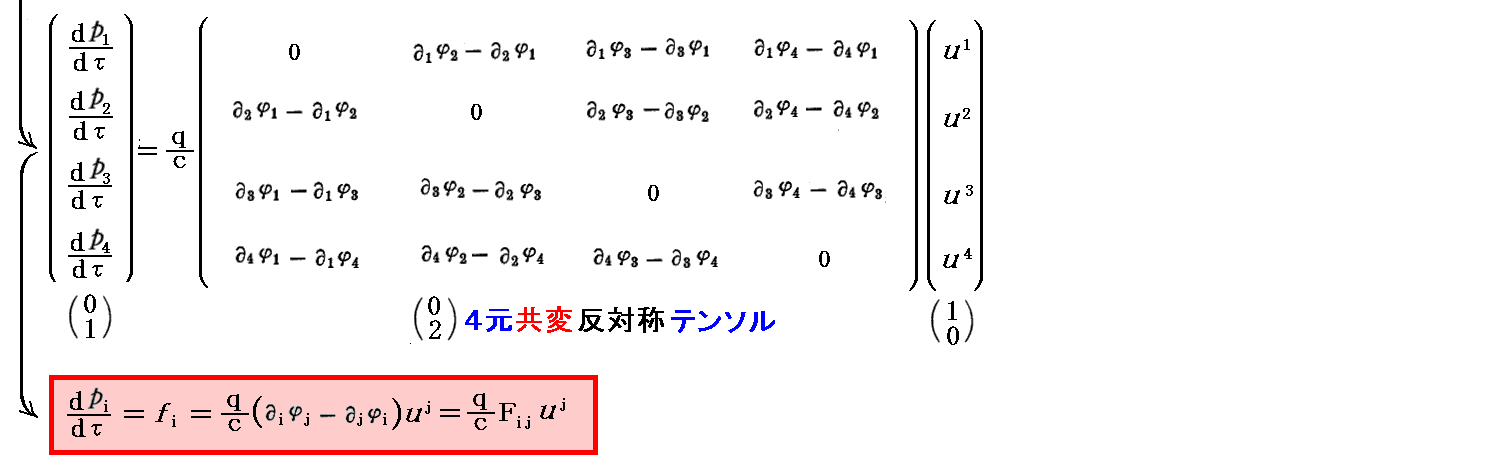
上記の4元共変反対称テンソルは、次に述べる様に4元反変反対称テンソルの左右から共変計量テンソルを作用させても導く事ができます。
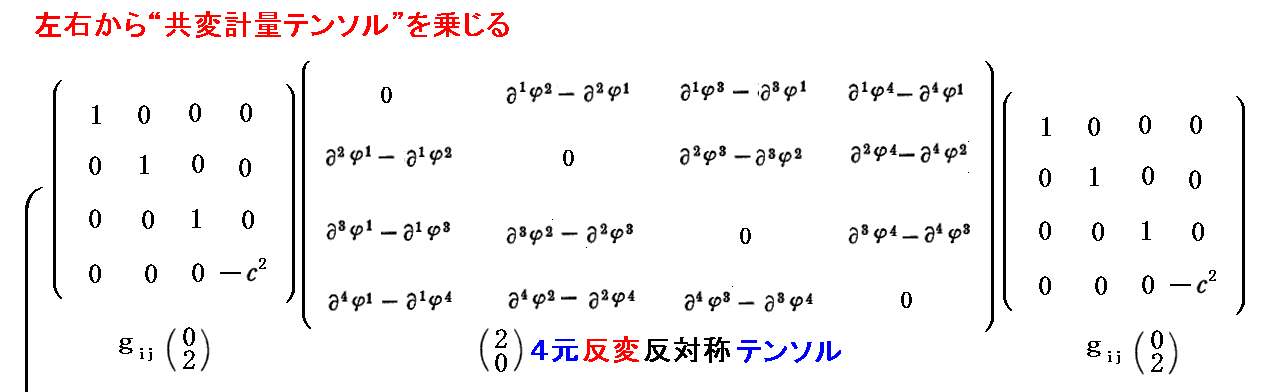
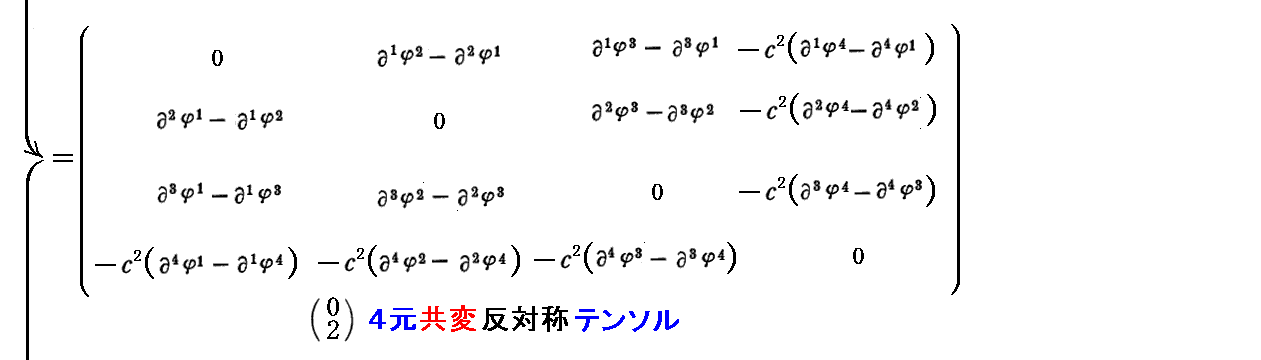
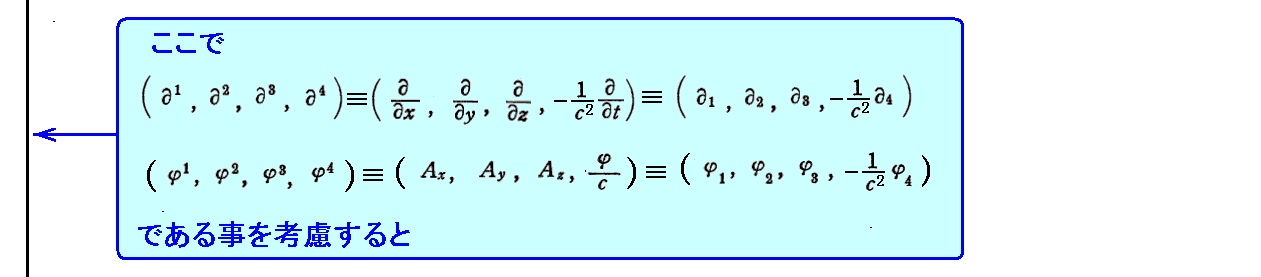
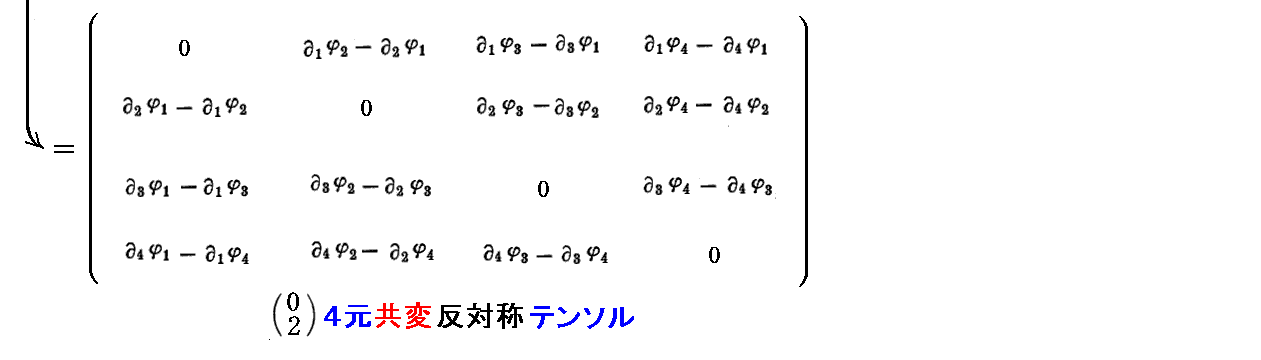
このとき、(2,0)型や(0,2)型の電磁場テンソルの行列表現の第4列目の表示と、第4行目の表示に於いて、先ほど注意した不揃いがなくなることに注意されたし。そしていずれも反対称テンソルになります。
【 2階反変テンソル表現 】
上記以外に、左辺は反変ベクトル表示のままで、右辺の速度ベクトルを共変ベクトル表示にすると、先に説明したように電磁波テンソルは(2,0)型2階反変テンソル表現になります。
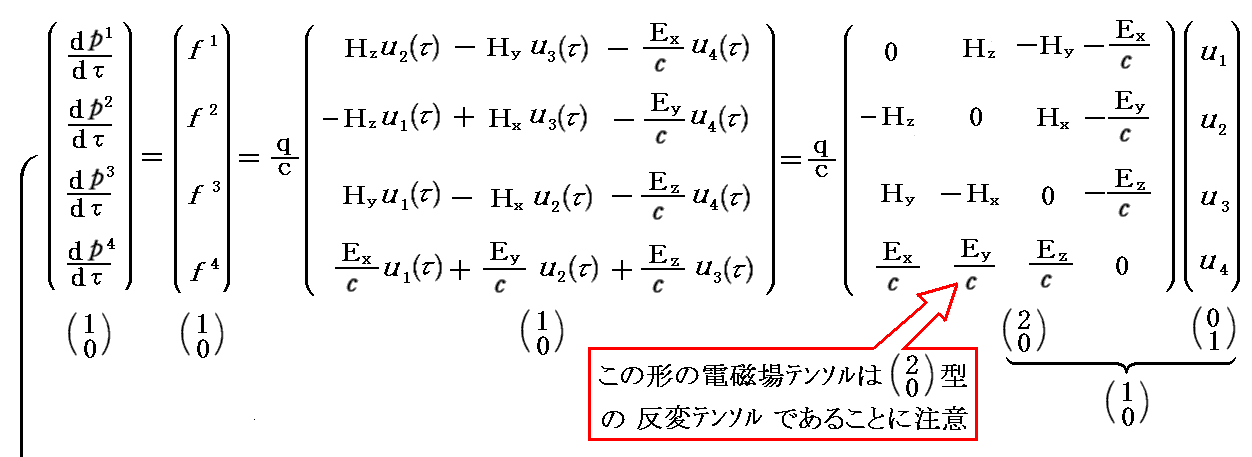
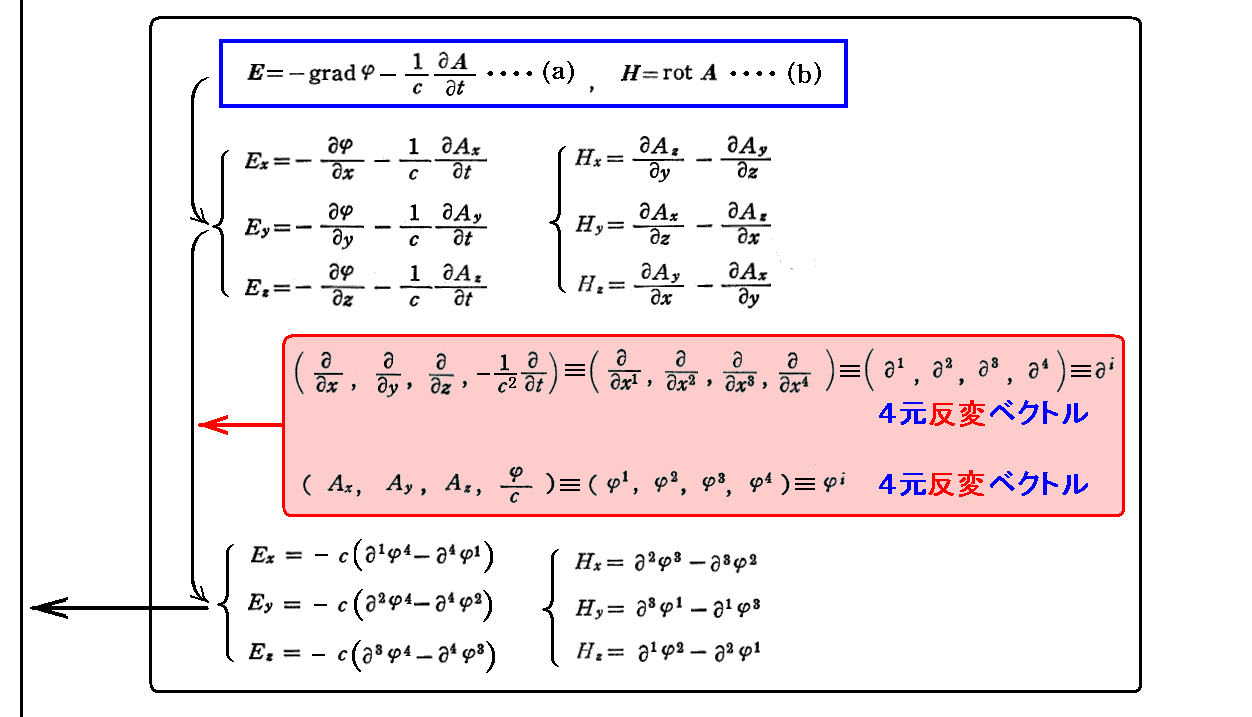
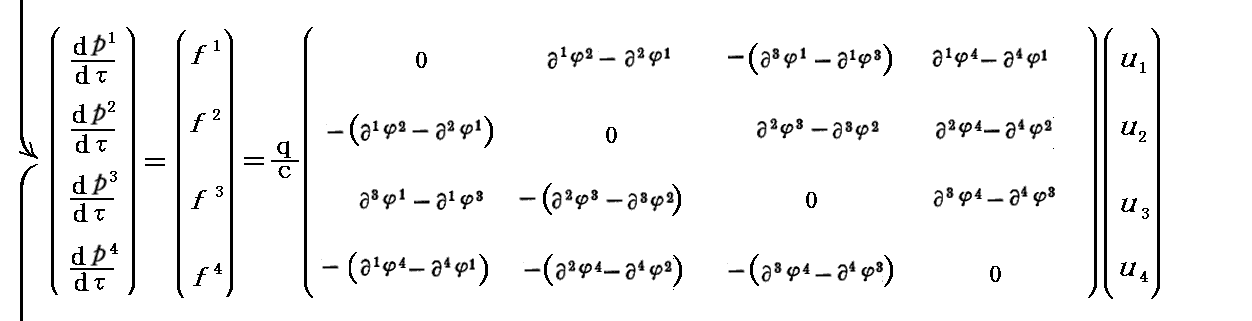
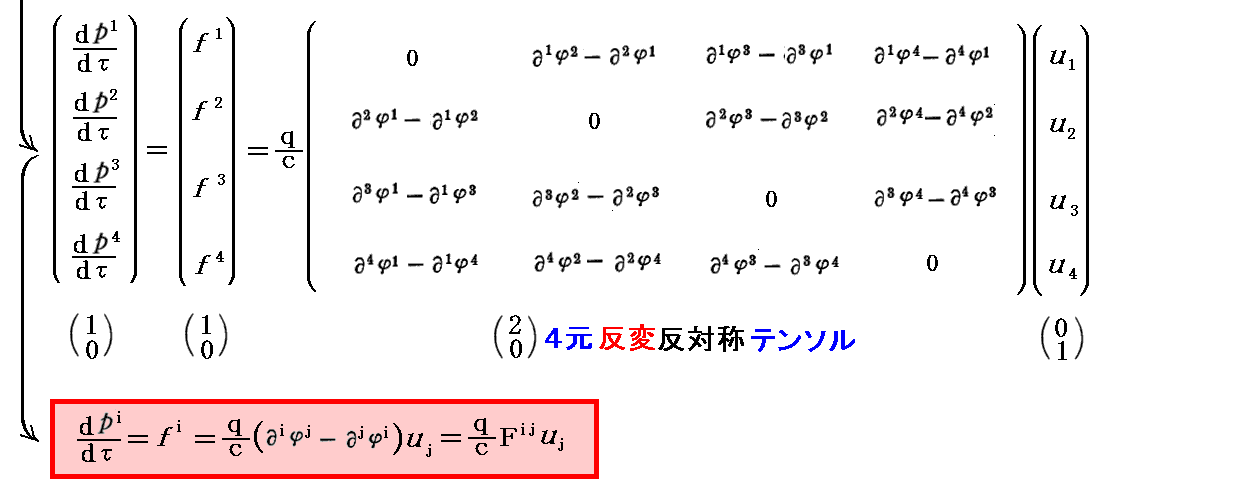
【 2階共変テンソル表現 】
最初の式の第4成分の両辺に-c2を乗じて、両辺を共変ベクトル表示にする。つまり
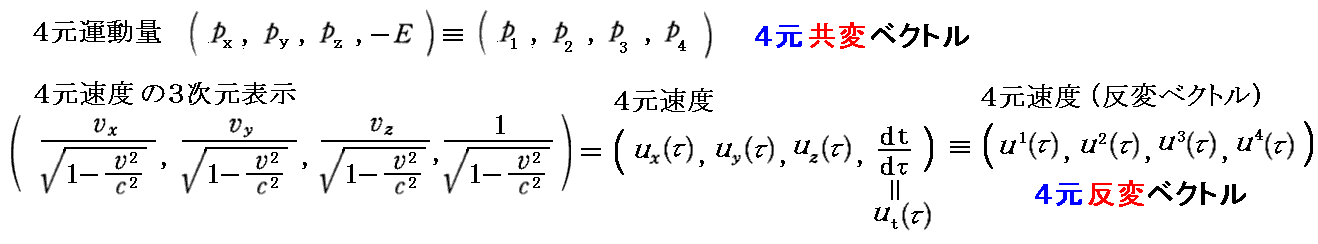
とする。こうすると先に説明したように右辺は(0,2)階共変テンソル型の電磁場テンソルと反変ベトクル表示の4元速度の積(縮約)になります。この場合を以下で説明します。
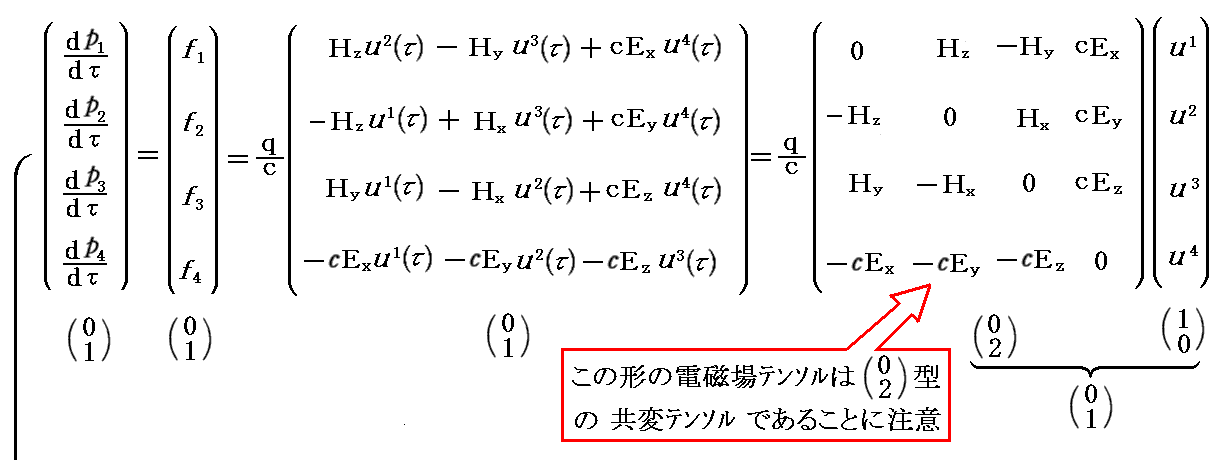
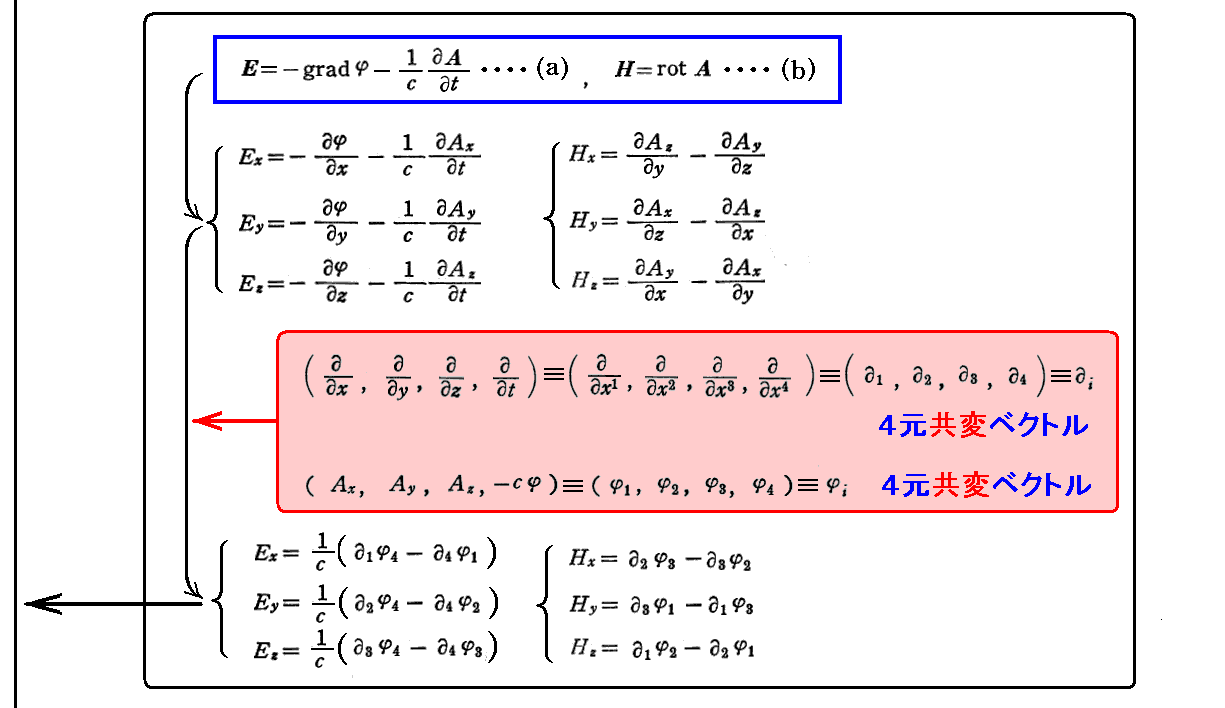
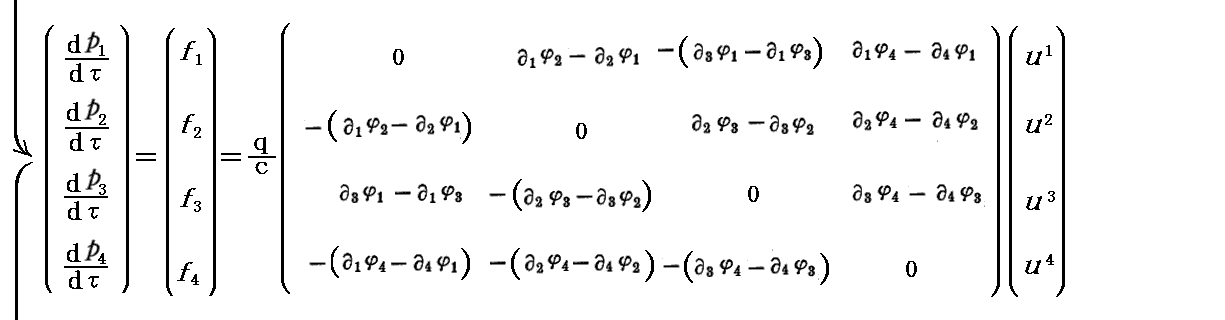
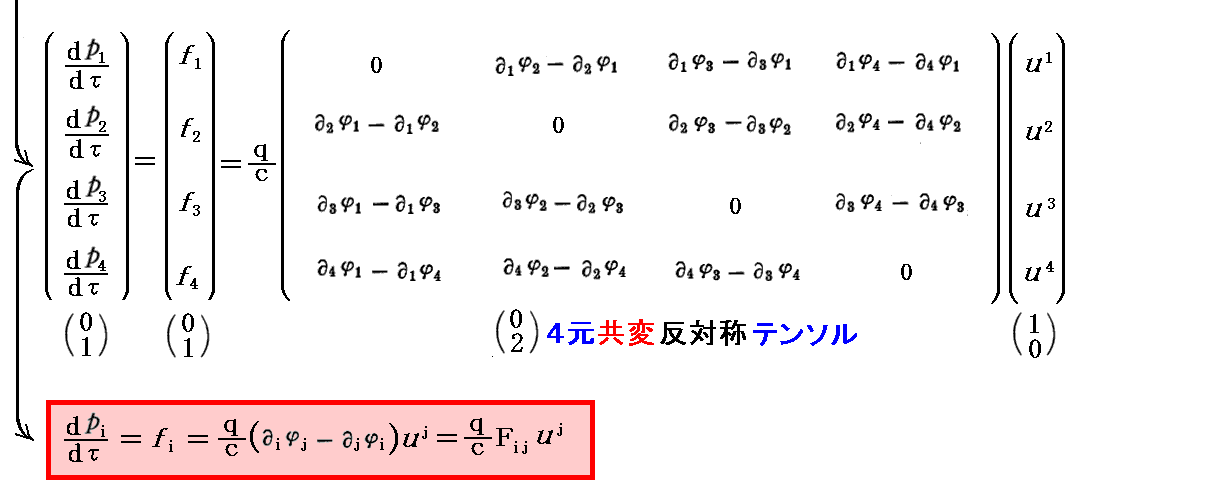
上記の表現から出発して、ミンコフスキー時空の共変計量テンソルを作用させて変形すると様々な表示形式の方程式に変更できます。繰り返しになりますが、以前の議論と整合性が成り立っている事を確認しておきます。
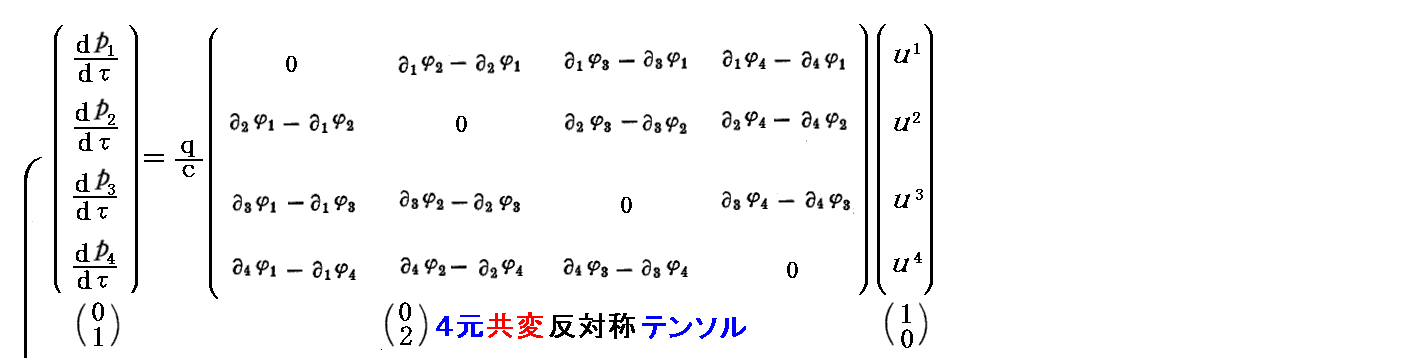
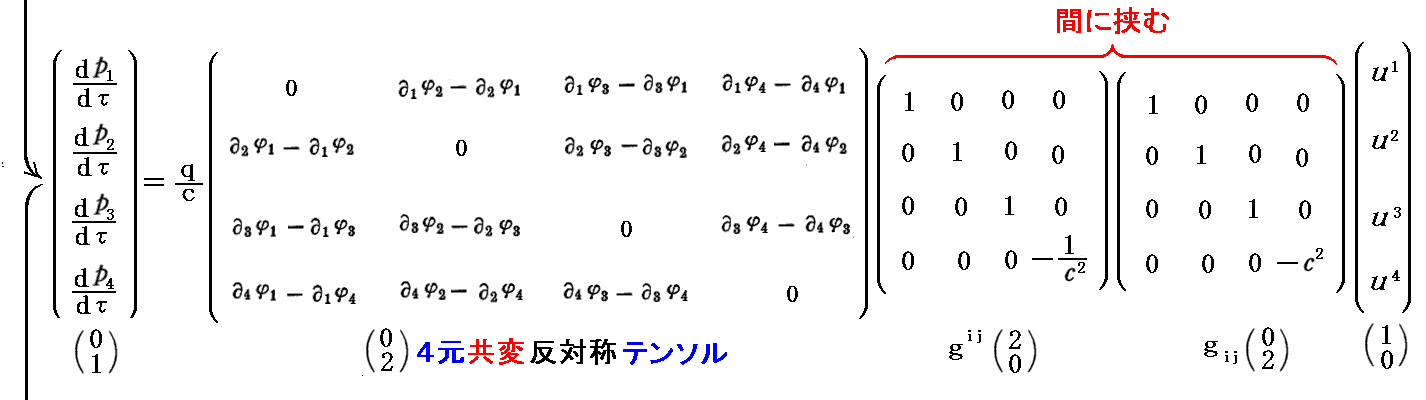
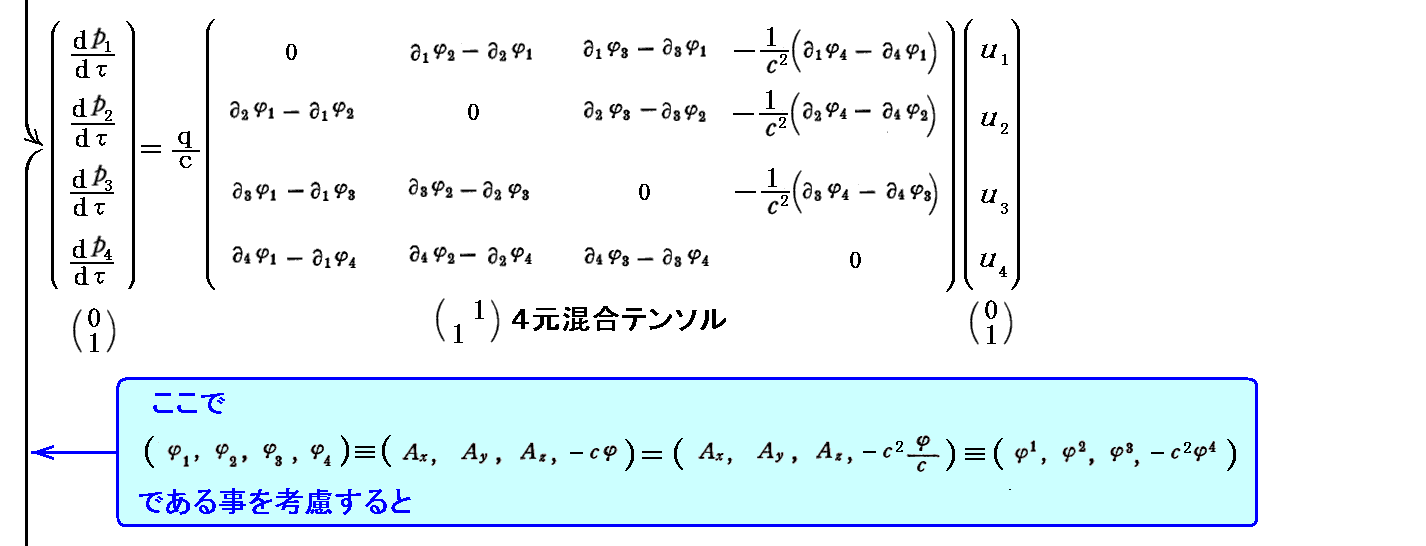
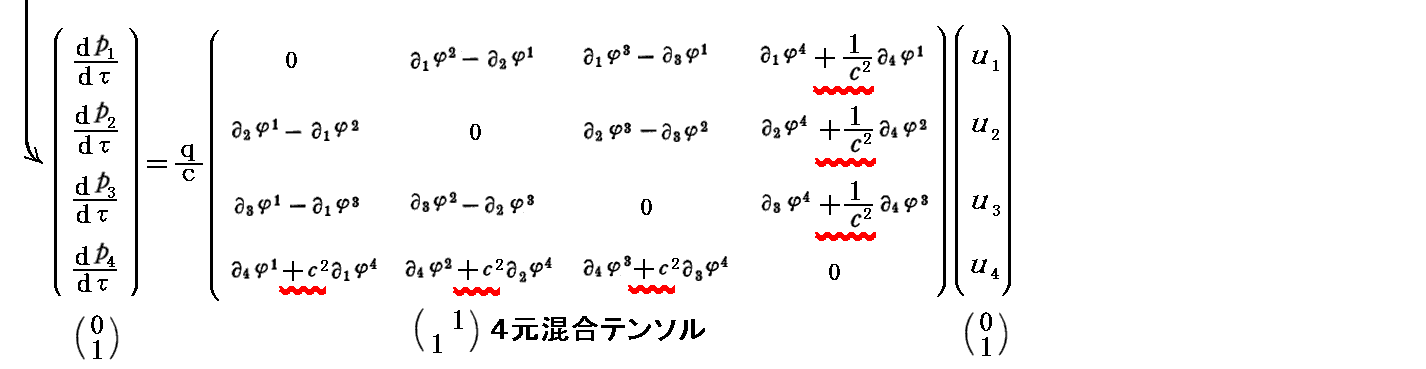
この(11)型4元混合テンソルの場合にも、先に述べた(11)型4元混合テンソルの場合と同様な事情が、第4列と第4行の表示に現れていることに注意して下さい。
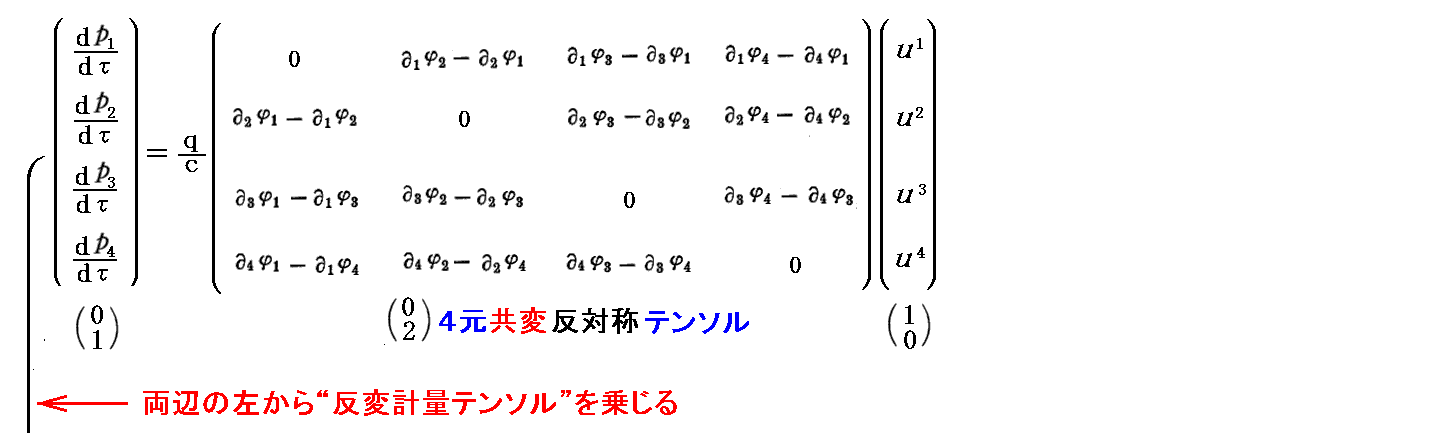
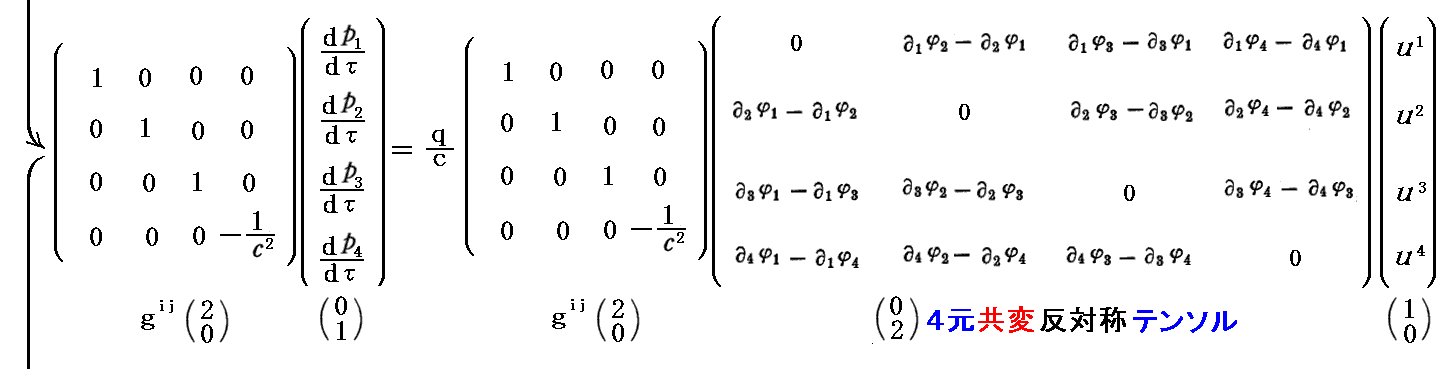

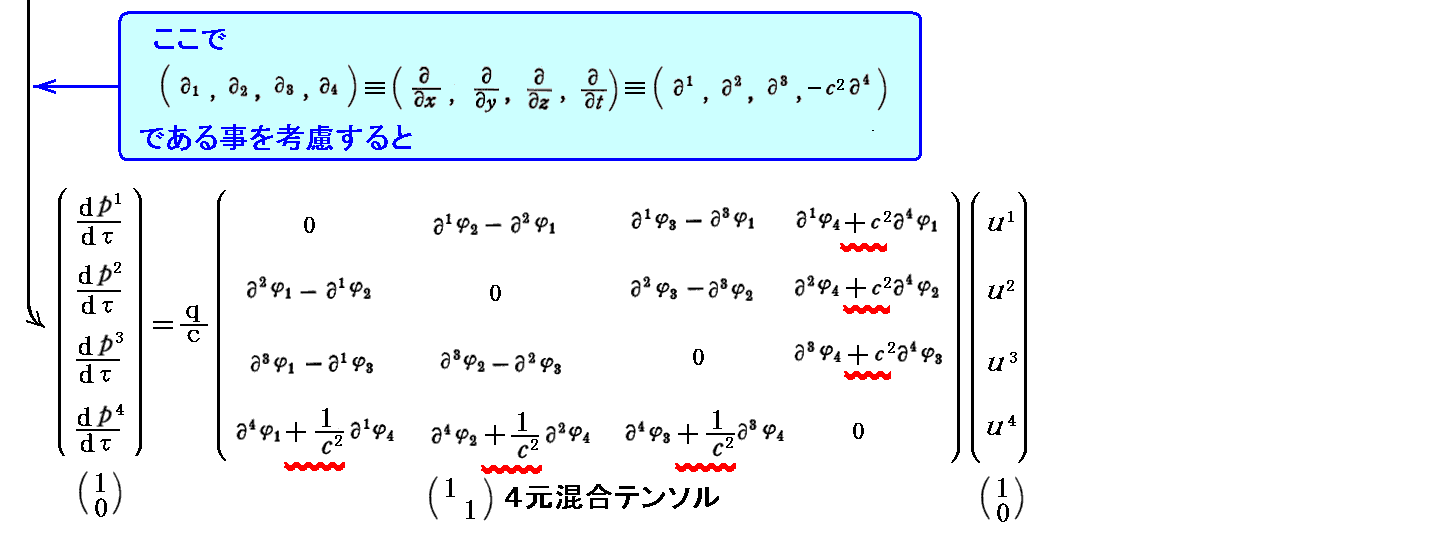
最初の4元共変反対称テンソルの左右から反変計量テンソルを作用させるとは、4元反変反対称テンソルを導く事ができます。これは以前説明した操作の逆過程です。
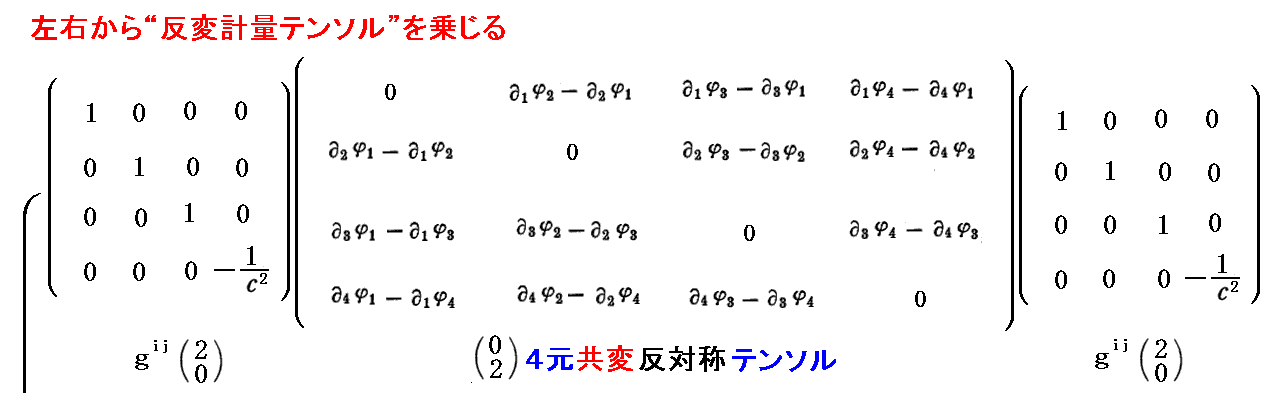
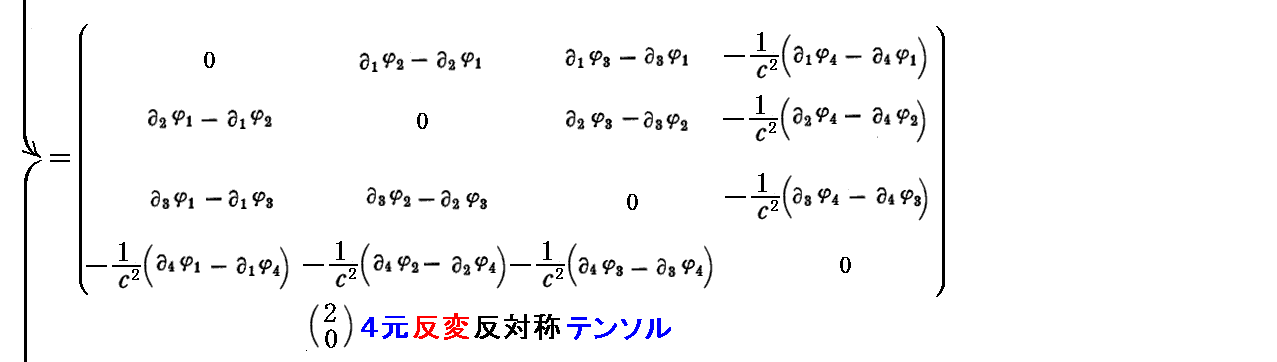
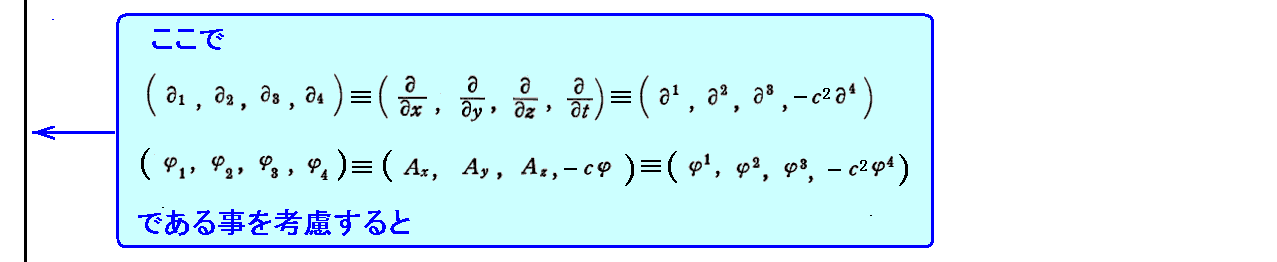
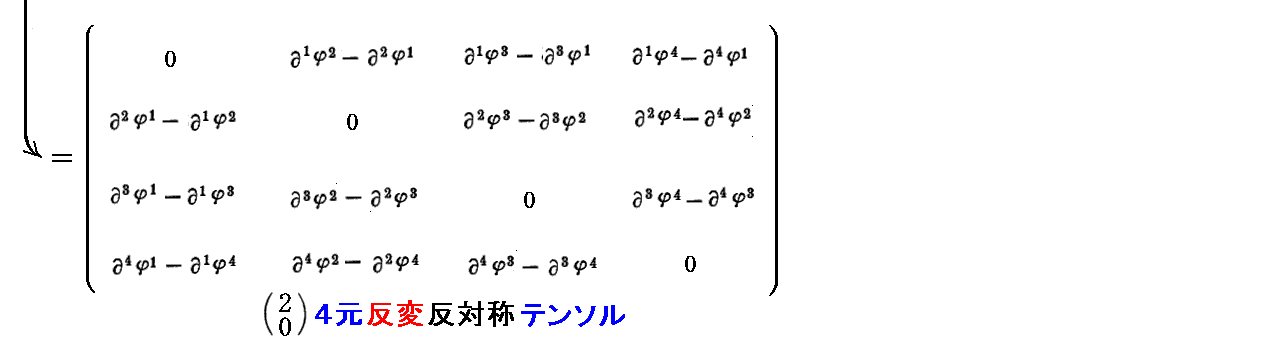
この項の最初に述べた様に、“ローレンツの力の法則”はMaxwell方程式系を構成する法則の中で唯一の“力学的法則”です。そのためこの法則は、“変分原理”に従って正統的に導かれる“Euler-Lagrange方程式”であるはずです。その事は別稿「電磁場中の荷電粒子の運動」で説明しましたが、丁度良い機会ですので復習しておきます。
ただし、上記別稿ではMKSA有理化単位系を用いていましたが、ここでは本稿で採用しているGauss単位系(非有理化-磁場H)で展開します。また、相対論的な4元ベクトルや、計量テンソルの表現としては別稿3.で説明した右側の定義を用います。
[補足説明3]
要するに、荷電粒子の運動方程式を変分原理から導く事を考えるのですが、その導くべき運動方程式として[補足説明3]で様々に議論した中の1つを取り上げて、それを導く事を考える。その中の1つを選ぶのですが、導くべき方程式として
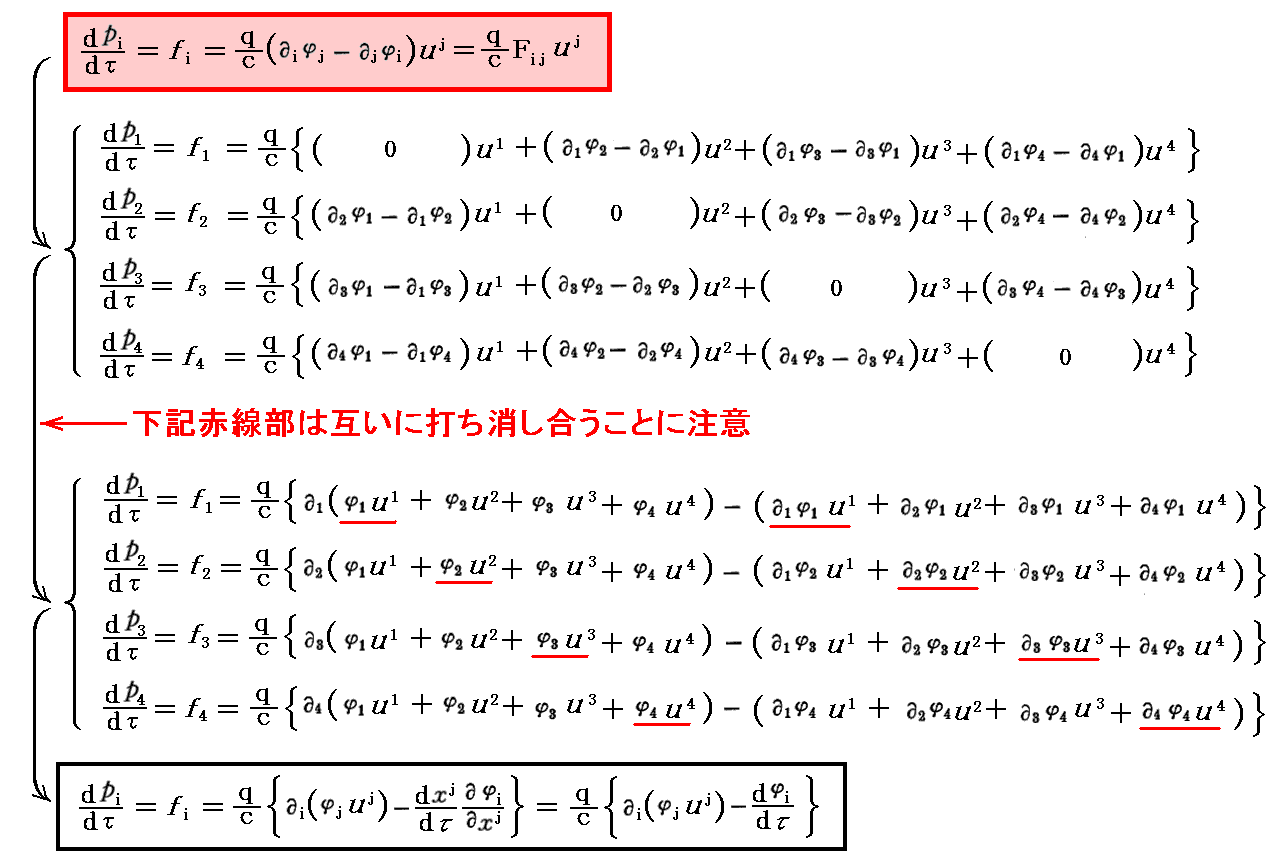
を選びます。
これをもう少し具体的な4元電磁ポテンシャルで表すと
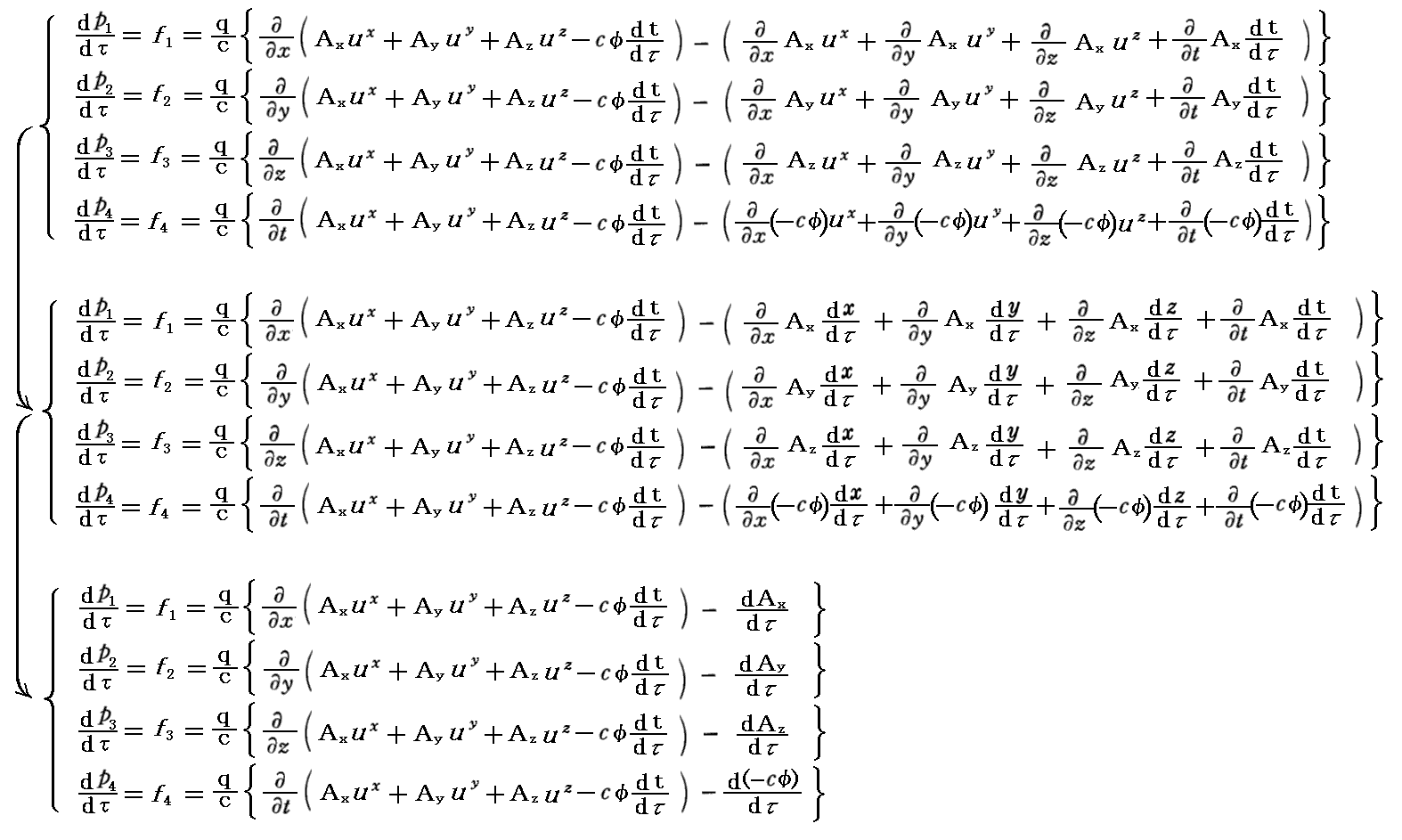
となります。
上記の“運動方程式”が“Euler-Lagrange方程式”によって導けるためには、“Lagrangean”として
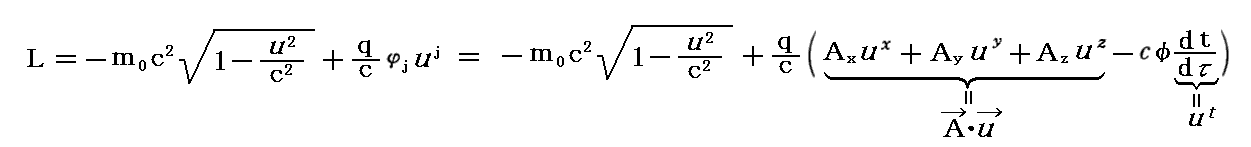
とすれば良いことが解ります。
実際、これを“Euler-Lagrange方程式”に代入すると、以下の様に上記の“運動方程式”が導けます。
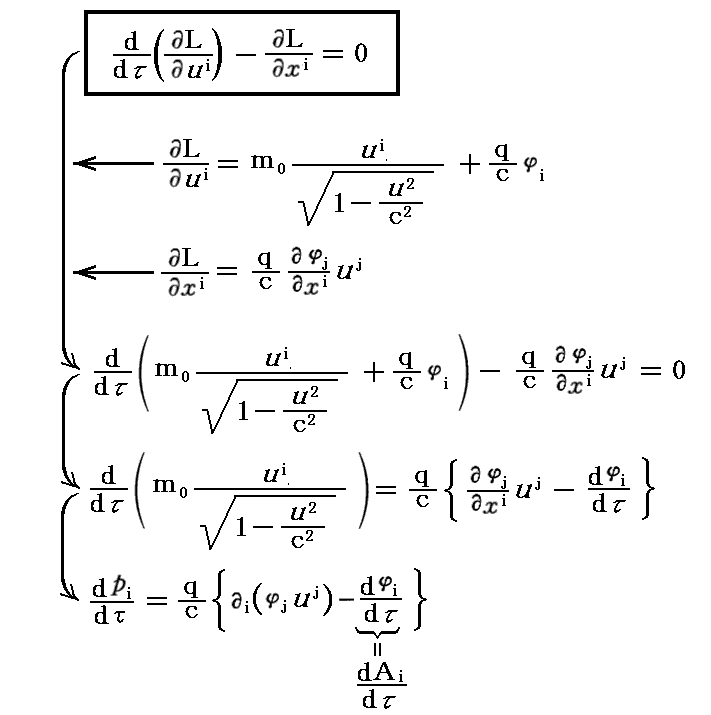
この当たりについてはランダウ・リフシュツ「場の古典論」§16などを復習して下さい。
また別稿「電磁場中の荷電粒子の運動」2.もご覧下さい。ただし、そこではMKSA有理化単位系を用いているため、cが関係するところで表現が少し異なる所があります。
(2)電磁場の非同次波動方程式
2.(1)1.で示した式の中で①式と③式は、両辺に電場と磁場が同時に現れているが、この二式を組み合わせることで電場Eだけ、あるいは磁場Hだけの方程式を得ることができる。
以下でその事を説明するが、空間微分と時間微分の演算順序を交換できることに注意してお読み下さい。
1.電場の非同次波動方程式
まず、①、③式から電場Eの波動方程式を導く。

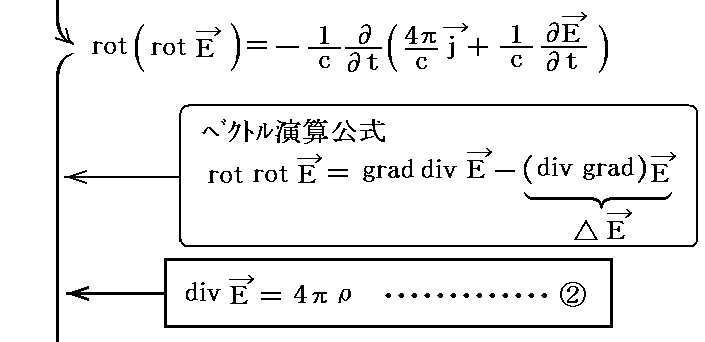
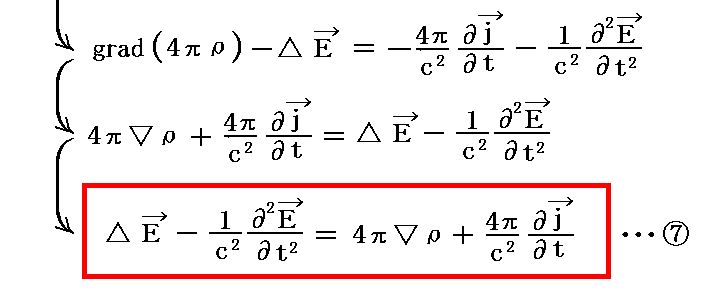
となる。これを⑦式と置くことにする。上で用いたベクトル演算公式 rot(rotE)=grad(divE)-△E の証明はこちらを参照。
もちろん、①式の両辺の時間微分を取って、③、②式を用いても良い。このやり方でも同様な式が得られる。
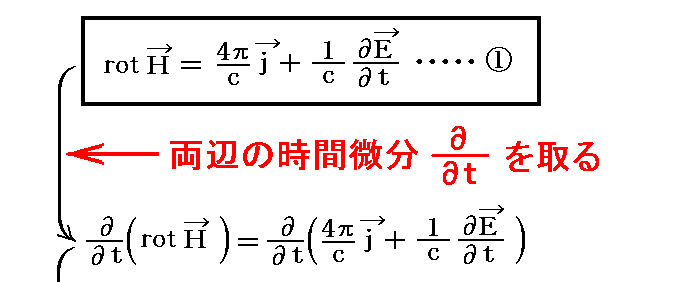
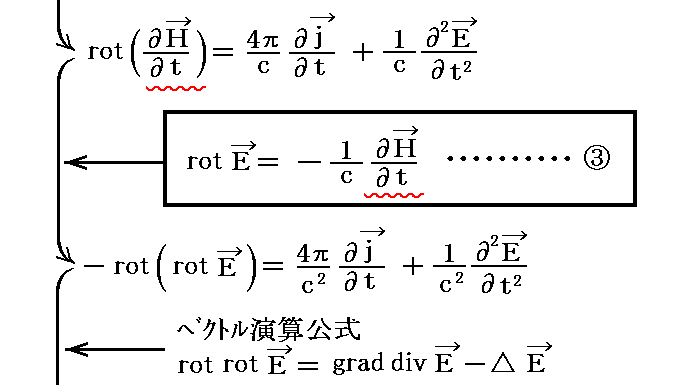
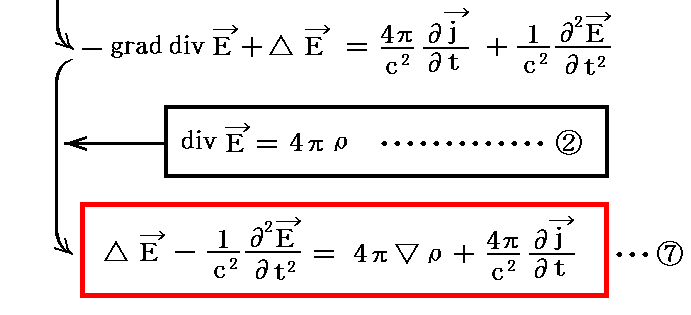
2.磁場の非同次波動方程式
①、③式から磁場Hだけの方程式を求める。①式の両辺のrot演算を取って③、④式を用いて、先ほどと同様な変形をすると
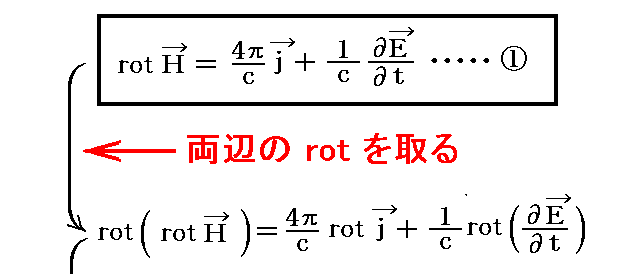
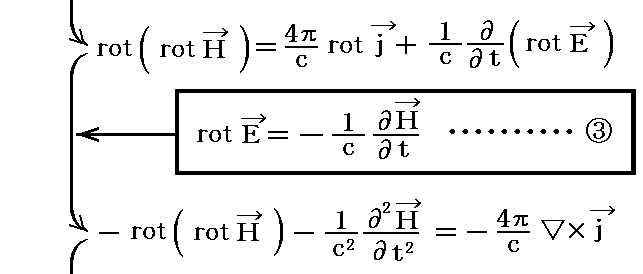
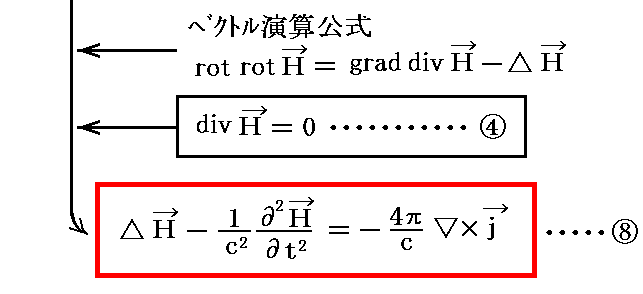
が得られる。これを⑧式と置くことにする。
もちろん、③式の両辺の時間微分を取って開始してから、①、④式を用いても良い。このやり方でも同様な式が得られる。
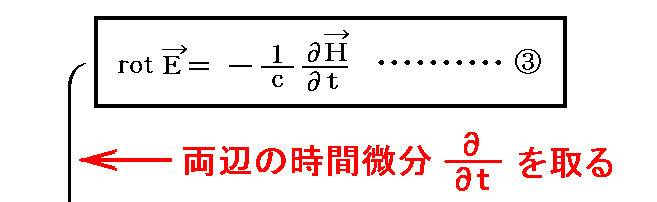
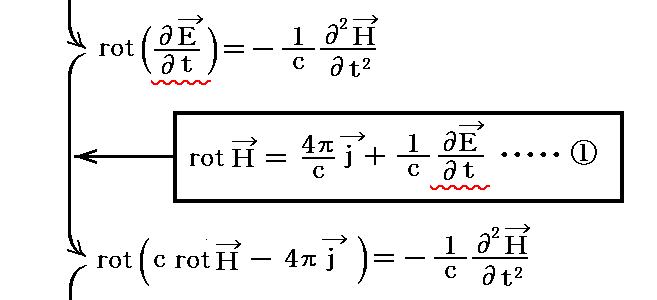
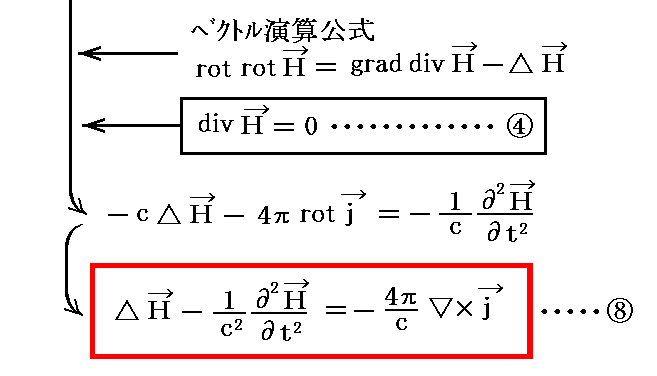
3.Maxwell方程式系と電磁場波動方程式の等価性
ここで説明した方法で、ヘヴィサイドとヘルツが整理したMaxwell方程式系①~④式から、電磁場の非同次波動方程式を最初に導いたのはオランダ人のH.A.Lorentz(1892年)のようです。このことに付いては太田文献2.のp109-02、p112-02やp210をご覧下さい。
ここで重要なことは、電場だけ、磁場だけの方程式にするには、必ず①式と③式を組み合わせなければなりません。①と③の両方を使用する上記の導き方からも解る様に、[Maxwell方程式系①③]は[電場E、磁場Hの非同次波動方程式⑦、⑧]と等価です。
ただし、①③から⑦⑧を導くとき②と④を援用していますし、逆に⑦⑧から①③を導くとき、②と④の援用は必要です。そのため、より正確に言えば下図の様に対応した等価性であると言える。
《2.(2) まとめ》
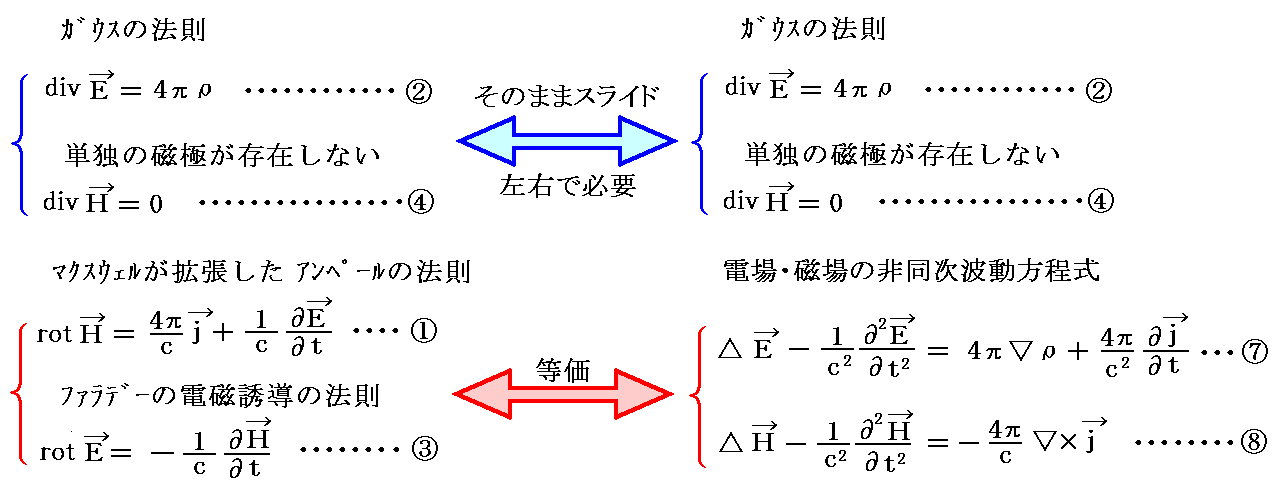
すなわち、①③の方程式系を⑦⑧で置き換えたとき②④の方程式も必要です。
つまり、左側の①~④方程式系の代わりに、右側の②④⑦⑧方程式系を考察する事によっても[電磁場の様子] と [電荷密度・電流密度分布] との関係を導く事ができるということです。
(3)Maxwell方程式系、波動方程式系と特殊相対性理論
ここで導いた[電場E、磁場Hの非同次波動方程式⑦、⑧]の形から、これらの非同次波動方程式系が特殊相対性理論を満たす事を見通すのは難しい。
本来、電場Eと磁場Hは相対論的には両方合わせて2階テンソル場を構成します。古典的電磁場理論で考えられていたようなベクトル場ではありません。だからベクトル量と見なしたときの電場Eや磁場Hの成分値の変換式はローレンツ変換共変の変換式であって、決してローレンツ変換そのものではありません。そのため、電場Eや磁場Hを前面に出した波動方程式形式から相対性理論を見通すのは難しい。
そのとき、(7)、(8)式の右辺を 0 とした同次波動方程式系は、別稿「アインシュタインの特殊相対性理論(1905年)」3.(2)1.[補足説明1]の様に特殊相対性理論の中で利用されていますが、 方程式系の相対論的な構造を明らかにするためでは無くて、次節(4)で説明する様な意味で使われています。
特殊相対性理論に対しては、むしろ元の[Maxwell方程式系①~④、⑤と⑥]の方が見通しが良い。
実際1.(1)で説明した方程式系の中の(3)、(6)式や(8)、(9)式(すなわち①~④の方程式系)は別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」5.(2)や5.(3)で説明した様に相対論的方程式の形をしています。
さらに、1.(1)で説明した方程式系の中で、“電荷の保存則”(7)式や、“ローレンツの力の法則”(2)、(5)式は、2.(1)2.[補足説明1]や2.(1)3.[補足説明1]で説明した様に、元々相対論的方程式です。
そういった意味で、1.(1)で説明した方程式系の方がより根源的なのかもしれません。
補足しますと、第3章で説明します [電磁ポテンシャルA、φで表した波動方程式系] は、特殊相対性理論に適した形をしています。
(4)同次波動方程式と特殊相対性理論
先ほど求めた非同次波動方程式の右辺を構成する電荷密度分布と電流密度分布が全空間にわたってゼロの場合、同次波動方程式に帰着します。それは電荷密度及び電流密度分布がゼロの場合のMaxwell方程式系①~④を用いることでも導かれます。このことは別稿「アインシュタインの特殊相対性理論(1905年)」3.(2)1.[補足説明1]で説明しました。
なぜそこで説明したのかと言いますと、この波動方程式こそ何も無い真空中で存在できる電磁場の振る舞いを説明する方程式だからです。この解によって電磁場の波動である光の示す巨視的な性質が旨く説明できるからです。そのことに付いては先に挙げた別稿3.(2)1.[補足説明2]~[補足説明7]をご覧下さい。
もちろん相対性理論が発見される以前からMaxwell方程式から波動方程式が導かれる事は知られていましたし、波動方程式の中に現れる定数cが波動の伝播速度である事は知られていました。
ところが、やがてこの定数cが光の速度と一致することが解ってきます。つまり定数cが、波動方程式の解である電磁場の波動の伝播速度であり、この定数が光の速度と一致するのであれば、光の波は電磁波そのものであると考えられる様になります。
そういった時代に、Maxwell方程式や波動方程式がどの慣性系に於いても成り立つのか(つまり“相対性原理”が成り立つのか)が、問題になります。自然現象を表す方程式が相対性原理を満たすべきだという考え方は、アインシュタインの特殊相対性理論(1905年)の発見以前から広く考察されていたことです。もちろんそのとき、自然現象を表す方程式はある特定の空間(絶対静止空間)に於いて成り立つものであり、それとは異なった慣性系では方程式の形は変化するという考え方もありました。
そのとき、相対性原理が正しくて、あらゆる慣性系に於いて同一方程式となるのなら、cは慣性系によらない定数となりますから、光速度はどんな慣性系で測定しても一定である事になります。
あるいは、絶対静止の空間でのみで方程式が正しいのであって、それ以外の慣性系では方程式の形は変更を受け、光の速度は異なった値になるのなら、このことを確かめることにより絶対静止空間(エーテル空間)を確かめる事ができるかも知れません。
いずれにしても、このことを確かめる観測や実験が多数行われます。中でも特に有名なのがマイケルソン・モーリーの実験です。
そのとき、上記とは違って次の様に考える事もできます。
すなわち、光速cがそれを観測する慣性系によらず、つねに一定不変な定数である事は慣性座標間のガリレイ変換や、その変換に伴う速度の変換則に矛盾します。このことがひとつの着想をうみます。
すなわち別稿3.(2)[補足説明2]で説明した
『波動方程式が真に正しい物理法則を表しており“相対性原理”を満たしているのなら、波動方程式は二つの慣性系で同じ形になるべき(つまり光速cは定数であるべき)であるが、そのことから逆にガリレイ変換に変わる新しい座標変換法則(“ローレンツ変換”)を導くことが出来るかもしれない。』
という考え方です。
実際、その考え方に従って導かれた変換こそが相対性理論の本質をつかさどる“ローレンツ変換”だったのです。それを導く具体的な方法についてはこちらを、あるいはこちらを参照されたし。
もちろんこれは、光速度があらゆる慣性系で測って一定であるということから、それらの慣性系間の座標変換法則を導く事と同じです。そういった考え方にもとずく座標変換則の導出についてはこちらの[補足説明3]の中に記した引用先を参照して下さい。
そういった試みのすべてを旨く説明し、すべての疑問を解決するものとして、集大成されたものがアインシュタインの展開した特殊相対性理論です。それが「アインシュタインの特殊相対性理論(1905年)」で展開されているものです。
3.電磁ポテンシャルA、φの波動方程式
電磁ポテンシャルの導入は別稿「線型振動子による電磁波の放出」1.(1)や、別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」3.(2)ですでに説明していますが、特殊相対性理論の高い見知から今一度振り返ってみます。
ここも非有理化Gauss単位系で展開します。さらに、“本稿特有な計量テンソル定義”と“本稿特有な4元表示”を用いています。
今日の教科書で展開されている標準的な方法で電磁ポテンシャルA、φの非同次波動方程式を導きます。
すなわち、まず3.(1)で、Maxwell方程式(divH=0とファラデーの電磁誘導の法則)からベクトルポテンシャルAとスカラーポテンシャルφを定義・導入します。
そして、3.(2)1~2.で、上記の定義式を用いてMaxwell方程式(アンペールの法則)からベクトルポテンシャルAの非同次波動方程式を、Maxwell方程式(ガウスの法則)からスカラーポテンシャルφの非同次波動方程式を導きます。
最後の3.(2)3.で、Lorenzの条件式と、ベクトルポテンシャルA・スカラーポテンシャルφの定義式を、先に求めた非同次波動方程式に適用して、逆にMaxwell方程式系を導き、両者の等価性を説明します。
ただし以下の事柄に注意して下さい。すなわち、歴史的な展開は上記とは逆でして、最初ノイマンは電場Eを定義するベクトルポテンシャルAとスカラーポテンシャルφを
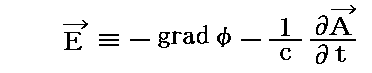
によって導入します。そして、(x’,y’,z’)における電荷密度をρ’としたとき、φは

定義され、(x’,y’,z’)における伝導電流をj’としたとき、Aは
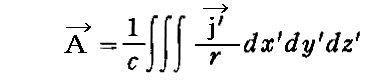
で定義されるとしました。
その後、デンマーク人のL.V.Lorenz は、そのベクトルポテンシャルAとスカラーポテンシャルφを
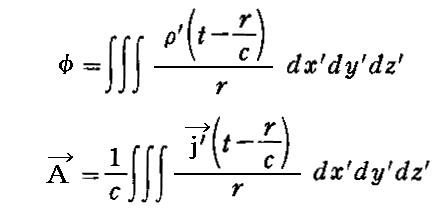
で置き換える事を提案します。つまり電荷や電流による影響は光速度cで伝わるとしたのです。そしてφとAがこのように置き換えて定義されると、この定義は
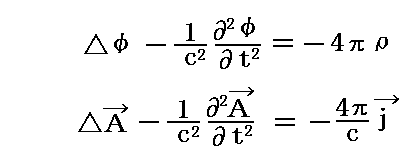
という非同次波動方程式と同等であるとした。
さらに、L.V.Lorenzは、電荷保存の式
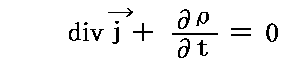
から、今日“Lorenzゲージ”と呼ばれている条件式
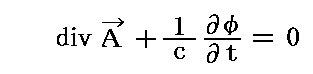
を導きます。そしてこのLorenzの条件式と、ベクトルポテンシャルA・スカラーポテンシャルφの定義式を、先ほどの非同次波動方程式に適用すれば、今日Maxwell方程式と呼ばれているものに相当する方程式系が導かれることを示します。
このL.V.Lorenzが行った最後の手順が、3.(2)3.で説明しているものに相当します。
(1)電磁ポテンシャルA、φ
1.ベクトルポテンシャルAの定義
2.(1)で説明した4つのMaxwell方程式の最初の2つ①式と②式は、左辺は電磁場だが右辺に電荷密度と電流密度を含んでおり、これは荷電物体と電磁場の相互作用を表すものでした。
これに対して③式と④式は電磁場ベクトルのみを含む線形の1次方程式ですから、比較的簡単に積分して解を得ることができます。
まず、④式から
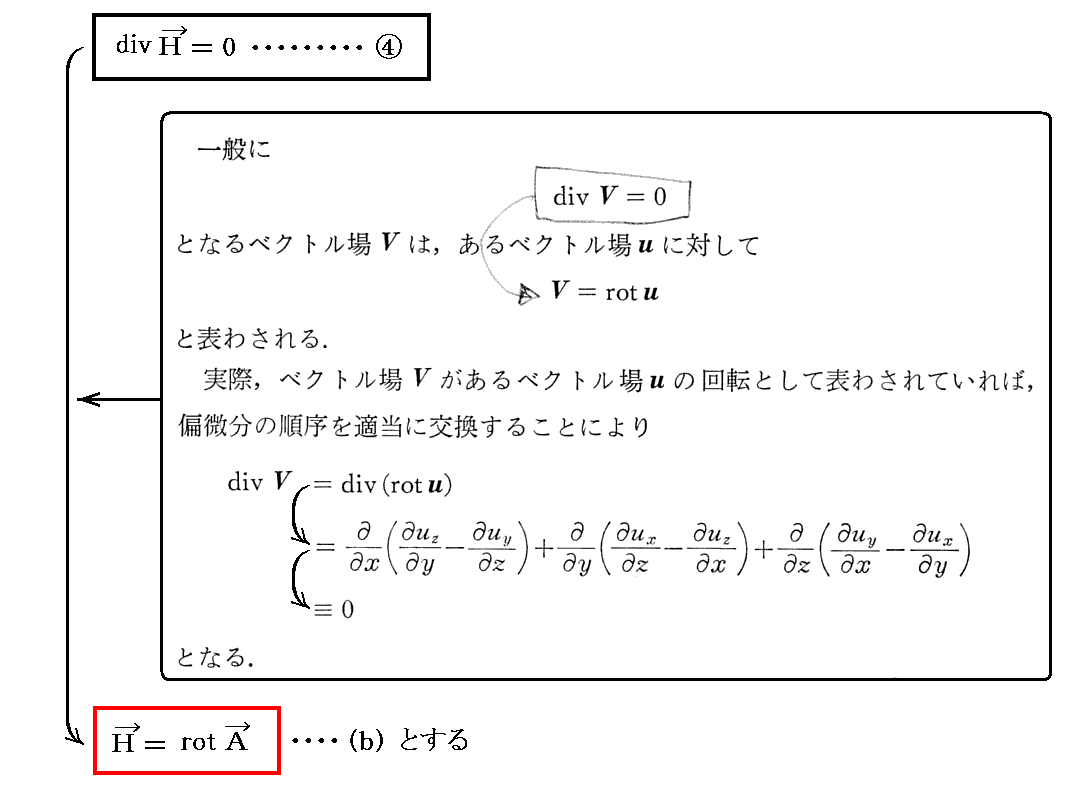
が言える。上記で用いたベクトル演算公式に付いてはこちらも参照して下さい。
このベクトル場Aを電磁場の“ベクトルポテンシャル”と言う。これはベクトル場Aの定義式と見なすこともできる。つまり磁場Hはベクトル場Aのrot演算から得られる。
今後この関係式を(b)とおくことにする。
2.スカラーポテンシャルφの定義
更に、③式から
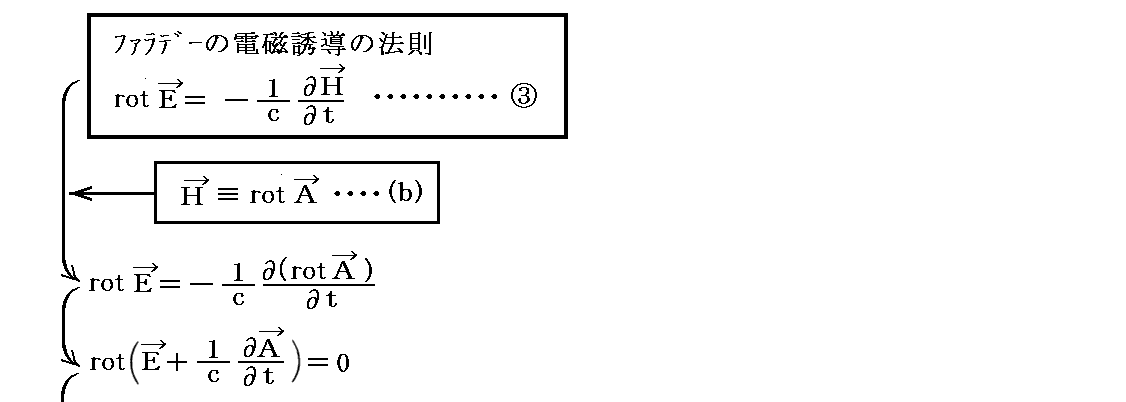
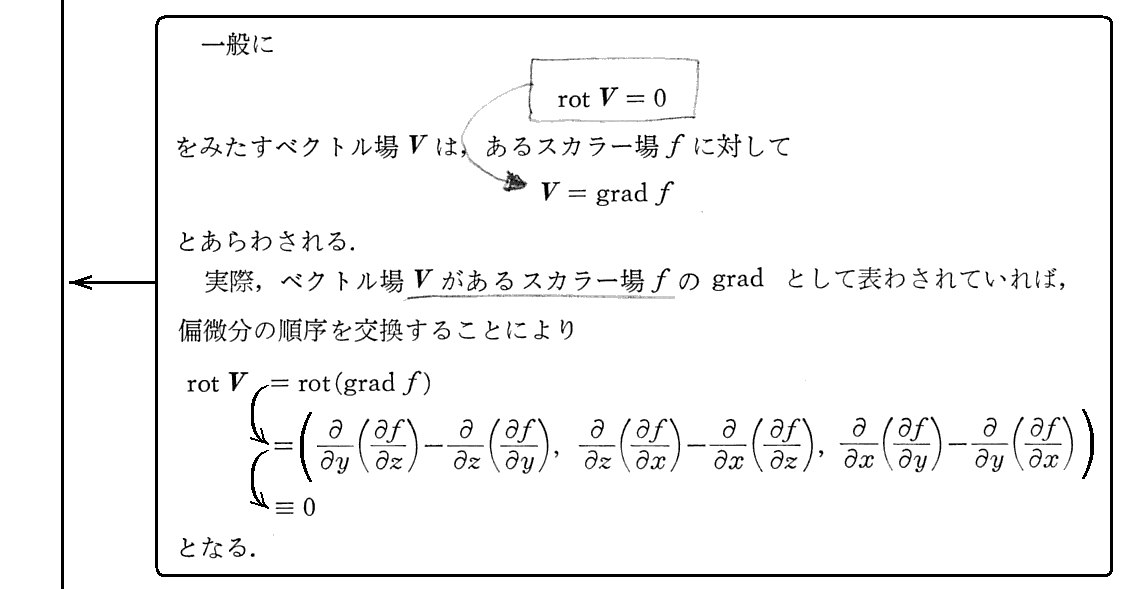
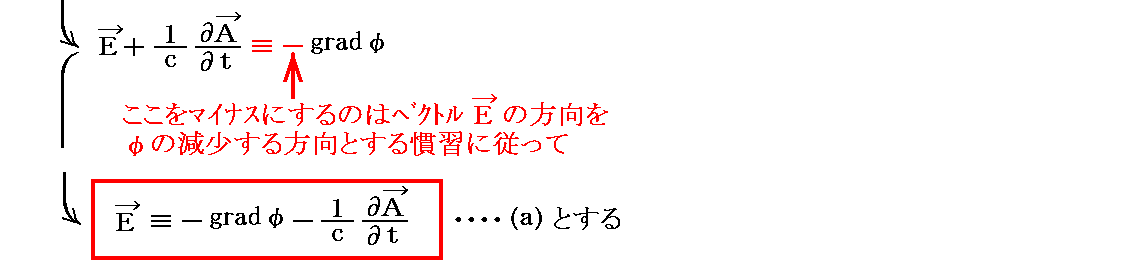
が言える。上記で用いたベクトル演算公式に付いてはこちらも参照して下さい。
このとき導入されるスカラー場φを電磁場の“スカラーポテンシャル”と言う。これはスカラーポテンシャルφとベクトル場Aの定義式と見なすこともできる。つまり電場Eは [スカラー場φにgrad演算を施したもの] と [ベクトル場Aの時間微分したもの] の和となる。
今後この関係式を(a)とおくことにする。
3.[電磁ポテンシャルA、φの定義式] は [Maxwell方程式③、④式] と等価
このとき、逆に(a)、(b)式から③、④式を導く事もできます。
まず、(a)(b)式から③式を導く。
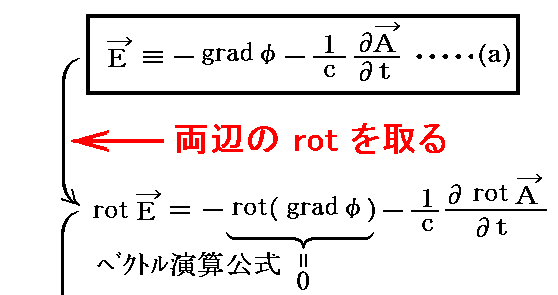
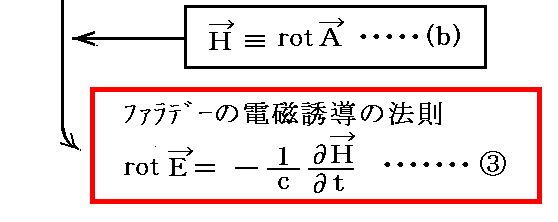
この式変形を最初に導いたのはLorenzです。
次に、(b)式から④式を導く。
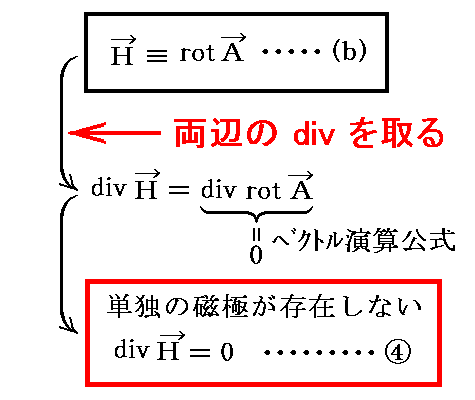
この様に、(a)、(b)式から③、④式が導けます。これは上記3.(1)1.2.項で説明した変換の逆変換に相当します。
ここで述べた逆変換に相当する計算は、ある意味において L.V.Lorenz がすでに行っている事です。このことについては太田文献2.p112-01をご覧下さい。
さらに補足しますと、今日電磁ポテンシャルは上記の様な手順で導入されますが、歴史的には話は逆でして最初(a)式が発見されます。(a)式はノイマンが見つけたもので、Maxwellはこれから③式を導きました。そして、デンマーク人の L.V.Lorenz は電磁ポテンシャルの波動方程式(d)(e)式から出発して、その波動方程式にノイマンの関係式(a)とLorenzのゲージ条件を適用してMaxwell方程式に相当するものを導きました。また、(b)式は1846年にW.Tomsonが見つけたものです。
この当たりはとても錯綜していますが、Whittakerの文献の8章の解説が理解の一助になると思います。
逆変換できることから、[Maxwellの方程式③、④式] と [電磁ポテンシャルの定義式(a)、(b)式] はお互いに 等価 です。
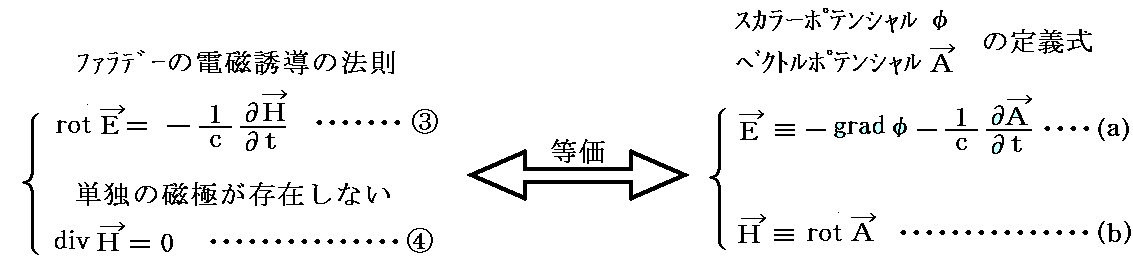
[補足説明1]
上記の等価性について補足します。
別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」5.(3)で説明した様に、[Maxwell方程式③、④式] は [相対論的3階テンソル方程式] に まとめることができました。そのところを復習すると
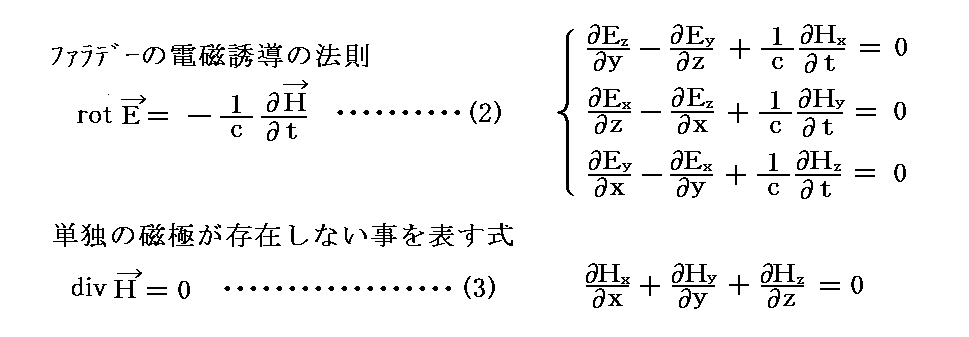
を変形していくと
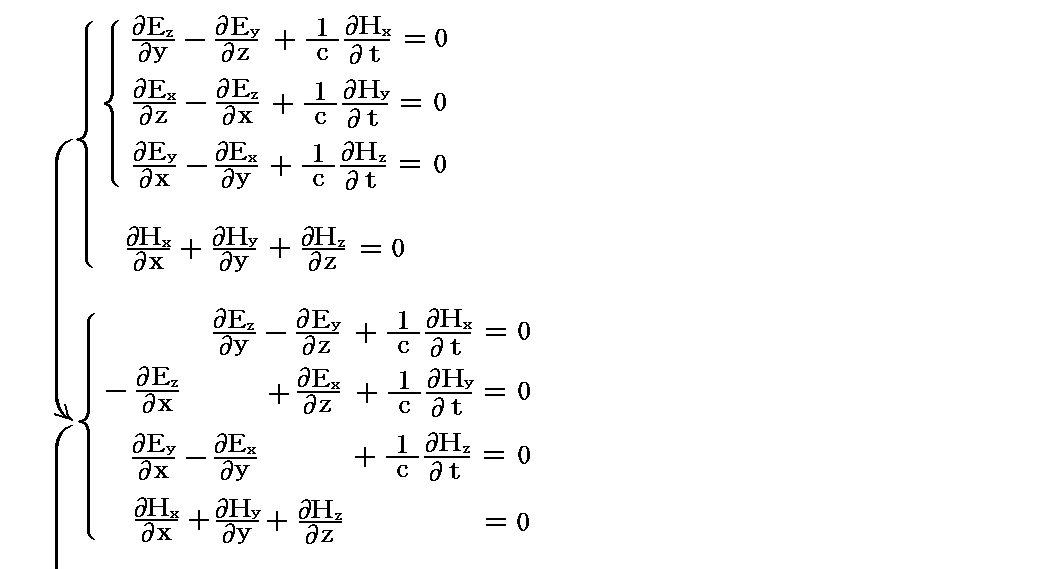
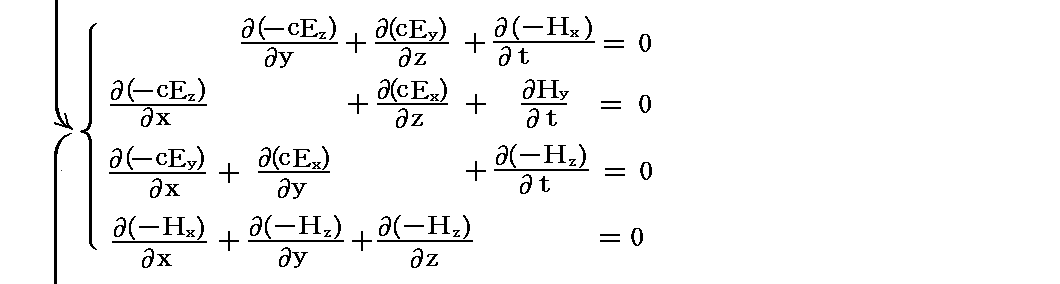
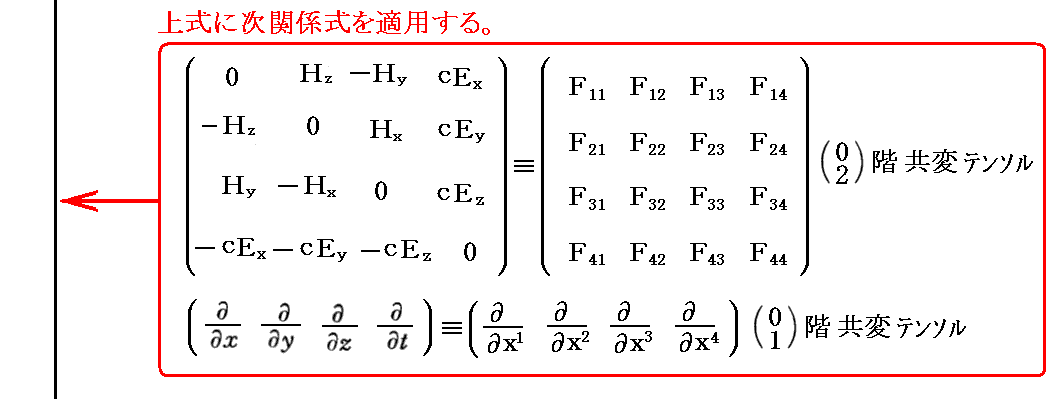

となります。この表現はとても解りにくいが、(0,1)階共変テンソル(つまり1階共変ベクトル)と(0,2)階共変テンソルの“直積”から作られる(0,3)階共変テンソルの“テンソル方程式”を表している。
このテンソルは4×4×4=64個の成分を持ちます。その(i,j,k)成分が ∂jFki+∂jFik+∂kFji であるということです。そして、上記のテンソル方程式は、その全ての成分が 0 であることを示している。
このとき、テンソル方程式の形から解るように64個成分それぞれが一つのテンソル方程式の1成分ですから方程式が64個あることになります。ただし、64個の方程式の内で独立なのは4個だけです。それは(i,j,k)として(1,2,3)(1,2,4)(1,3,4)(2,3,4)を持つものです。そうなることは別稿「ミンコフスキーの4次元世界」4.(2)2.[補足説明2]を、あるいは別稿「対称テンソルと反対称テンソルの独立成分の数」2.(2)を参照して下さい。この独立な4個が前記のMaxwell方程式の4式に相当します。
そのとき、別稿「ミンコフスキーの4次元世界」4.(2)2.[補足説明3]で説明したように、[電磁ポテンシャルの定義式(a)、(b)式] から上記の[相対論的3階テンソル方程式]を演繹的・恒等的に導く事ができます。そこの議論を以下で復習します。ただし、上記別稿は“有理化gauss単位系”を用い、しかも“特殊な形の計量テンソル定義”でしたので、本稿の“非有理化gauss単位系”と“本稿特有な計量テンソル定義”と“本稿特有な4元表示”に書き直しています。
まず、別稿の3.(1)[補足説明5]で述べたように4元共変ベクトルとしての電磁ポテンシャルは(Ax,Ay,Az,-cφ)です。これを(φ1,φ2,φ3,φ4)=φi と置くことにします。
そのとき別稿の3.(9)3.で説明したように、共変ベクトル場を微分したものを下記の様に組み合わせたものは4元の“回転”と呼んで交代(反対称)2階共変テンソル場となるのでした。ここで注意してほしいのですが4元微分演算は共変性のベクトルです。それを共変ベクトルに作用させるのですから、いわゆる“縮約”はできません。“直積”ならできます。ただし、ここで言う“回転”は直積ではありませんが直積操作に似ていまして、結局2階共変テンソルとなります。このことに付いては[補足説明2]をご覧下さい。
【3次元ベクトルの3次元回転演算操作では3次元ベクトルが生じましたが、4元共変ベクトルの4元回転演算操作では2階共変テンソルになると言うことです。おそらくこちらの4元表示が“回転”演算本来の形なのでしょう】
ここで取り上げている[電磁ポテンシャル定義式](a)(b)式は一緒になって2階共変テンソル(しかも反対称性)を構成する(別稿の4.(2)1.[補足説明3]参照)もので、まさにその例です。
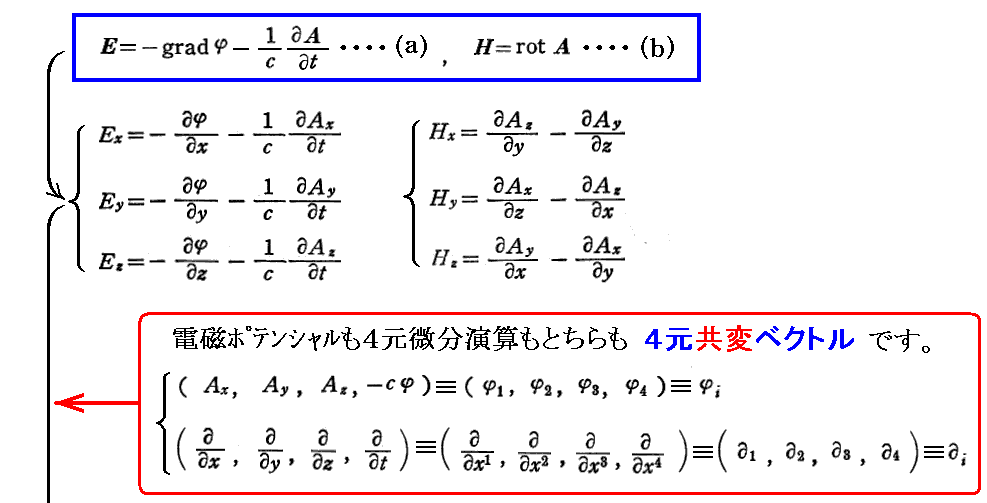
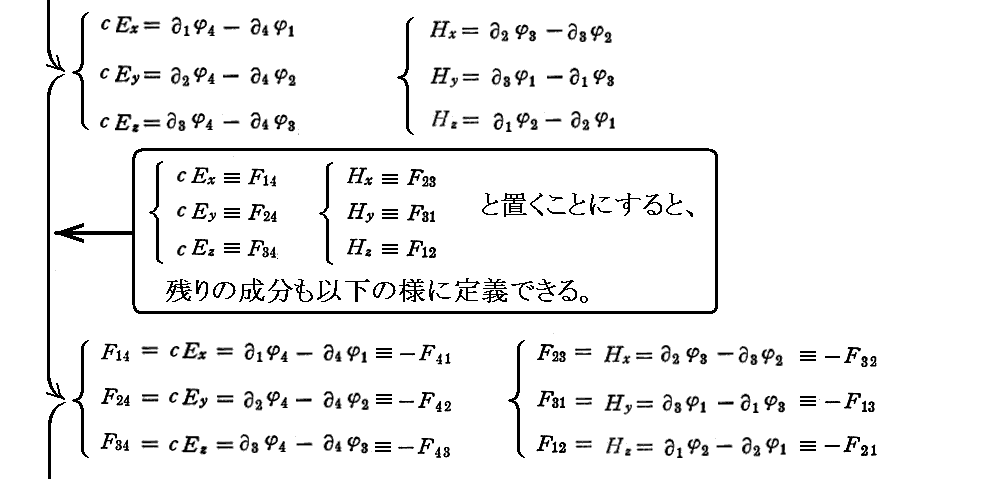
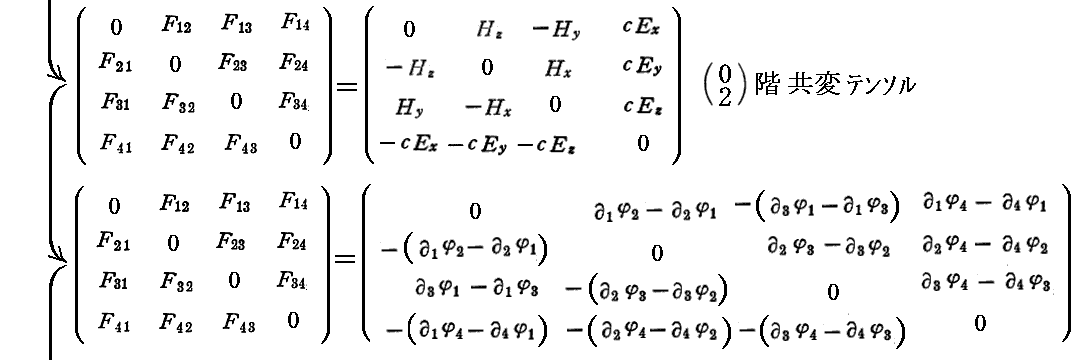
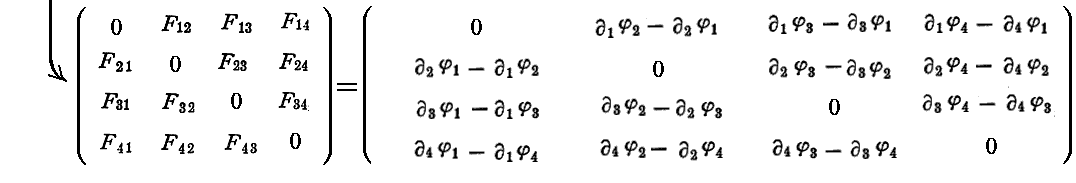
すなわち、[電磁ポテンシャルの定義式]は2階共変反対称テンソルを構成しています。
この[電磁ポテンシャルの定義式]を前記の3階共変テンソル
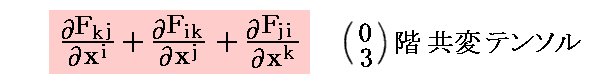
に適用してみれば、それが恒等的に0となることが解ります。実際、
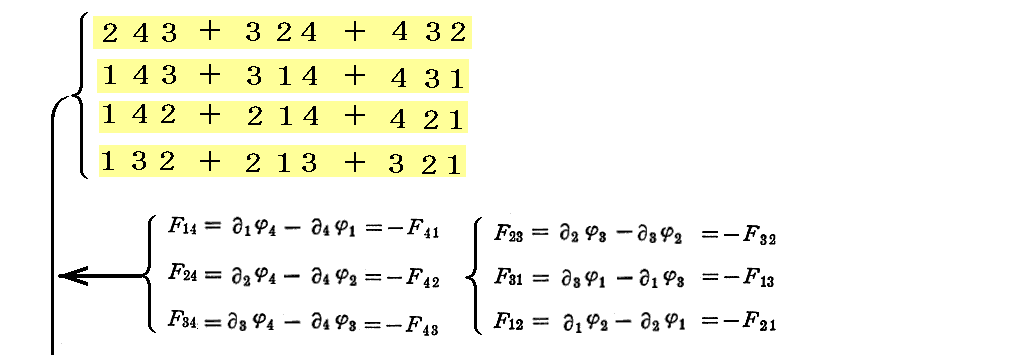
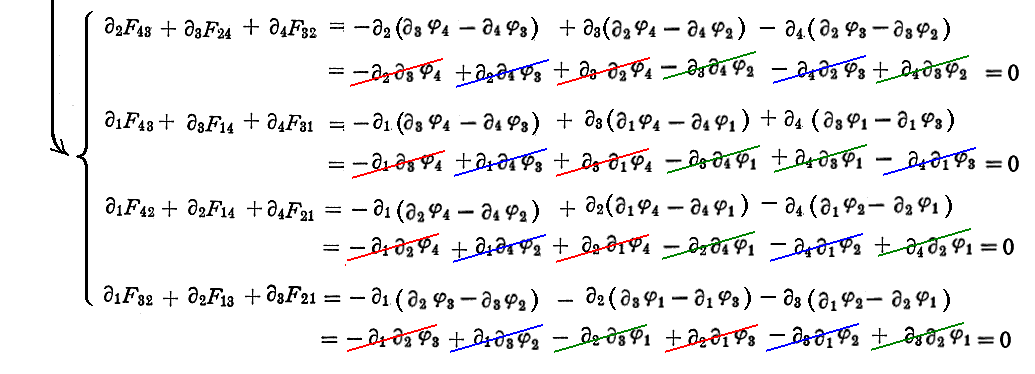
が直ちにいえる。
さらに、この[電磁ポテンシャルの定義式]を用いると、前記の3階共変テンソルが交代(反対称)テンソルであることが証明できます。実際一つの要素について計算して見ると
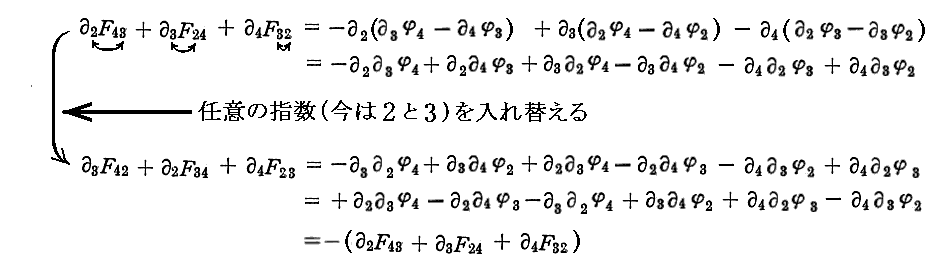
となります。他の3要素についても同様に証明できます。
いずれにしても、このように構成された3階共変交代(反対称)テンソル方程式は、マクスウェルの方程式
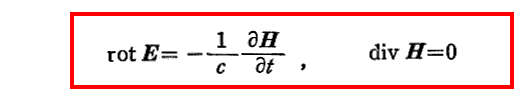
そのものを表している。
この相対論的な説明からも上述の等価性が完璧である事が解ります。
[補足説明2]
上記[補足説明1]に出てきた“4元回転演算”について補足します。これは2つの4元ベクトルの“直積”の一部を取り出したものです。2つの4元ベクトルAとBの“直積”からは16個の成分AiBjが生じますがこれは次の様に書き表すことができます。
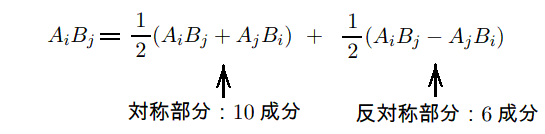
このときAiBiの様に同じ成分の組み合わせは、対象部分の成分としてはカウントできますが、反対称部分の成分は消えてしまいます。またAiBjとAjBiの様に添字を入れ替えたものは対象部分の成分としては同じになり、反対称部分の成分としても符号が入れ替わるだけなので独立なものとは見なせません。だから結局、対称部分は10成分、反対称部分は6成分のみが独立となります。つまり、前記の“4元回転演算”はこの反対称部分の成分を取り出したものです。そのため4元共変テンソルとなります。実際、このようにして構成したものは4元テンソルとしての変換式に従って変換されますので、その様に見なせるということです。
3次元ベクトルに関して同じ“直積”を作ると
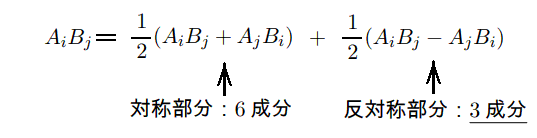
となりますが、その反対称部分は3成分となりますので、反対称部分の成分数が丁度ベクトルの次元数(3次元)と同じなので、それをベクトルと見なして慣習として
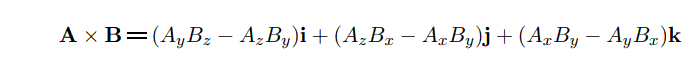
と表すことにしているだけです。本来は3元共変テンソルと見なすべきものだったのです。
(2)電磁ポテンシャルA、φの非同次波動方程式
別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」2.(2)で説明したように、電磁ポテンシャルA、φが満たす非同次波動方程式を最初に導いたのは、デンマーク人のL.Lorenzです。それは1867年のことです。
ただし、LorenzがMaxwell方程式を認識していたわけではありませんから、下記の様にMaxwell方程式から出発して導いたわけではありません。その導き方は別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」2.(2)1.で説明した手順によります。このことに付いては別稿§4.2“ローレンスの光と電流”110-02~をご覧下さい。
さらにそのとき、Lorenzは、本節3.(2)3.で説明する逆変換に相当する式を導いていますので、LorenzはMaxwell方程式に相当する式に到達していたとも言えます。このことに付いては別稿§4.2“ローレンスの光と電流”111-02~をご覧下さい。
1.ベクトルポテンシャルAの波動方程式
“電磁ポテンシャルの定義式”(a)(b)式を、“Maxwellが改良したアンペールの法則”①式に代入すると
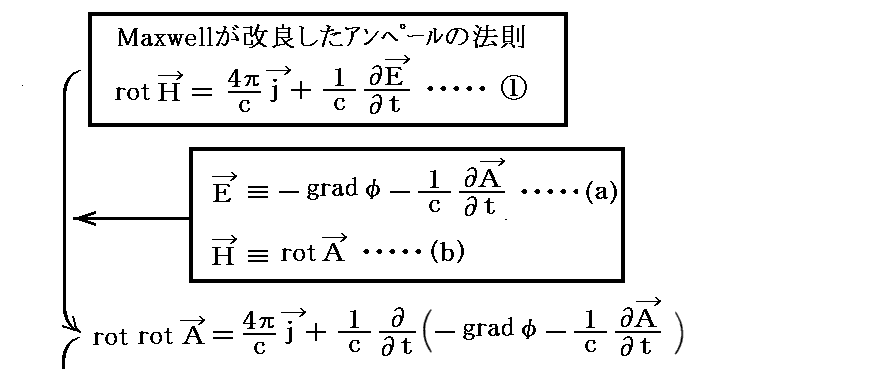
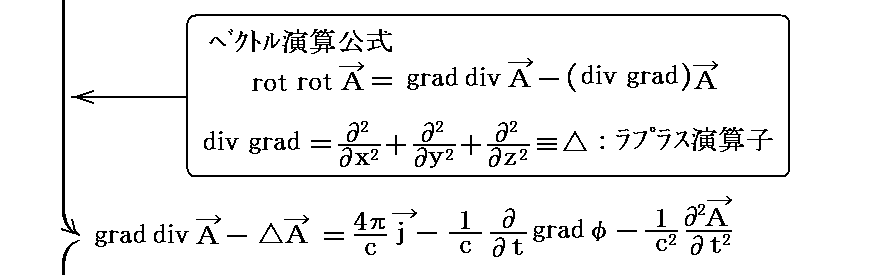
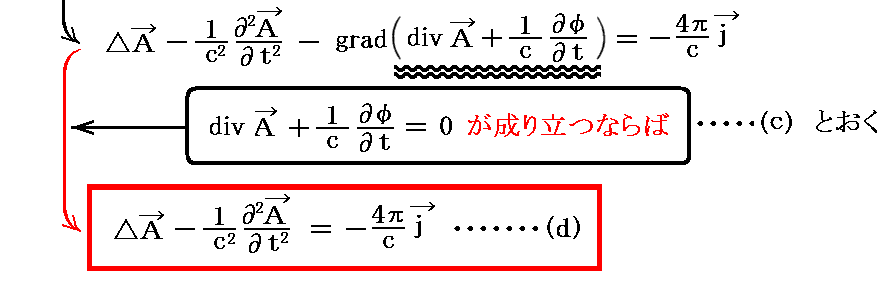
となり、ベクトルポテンシャルAの非同次波動方程式が得られる。これを今後(d)とおく。
ここで

の関係式を用いたことに注意して下さい。以下でも繰り返し用いますが、この関係式を今後“ローレンツ(Loreinz)の条件”と呼び、(c)とおくことにします。
2.スカラーポテンシャルφの波動方程式
“電磁ポテンシャルの定義式”(a)式を、“ガウスの法則”②式に代入すると
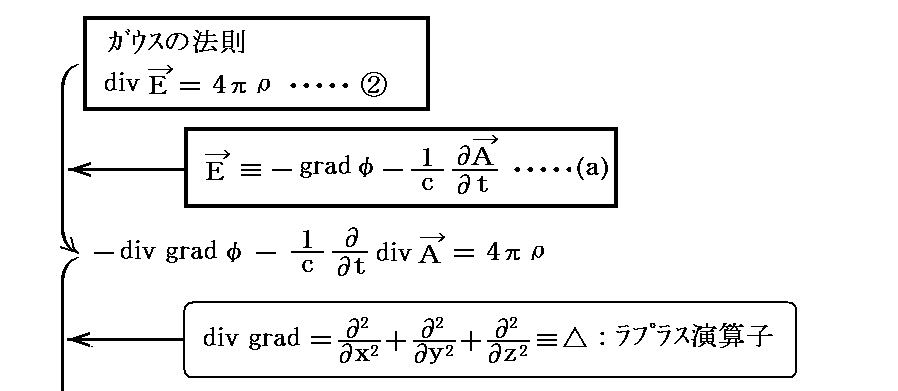
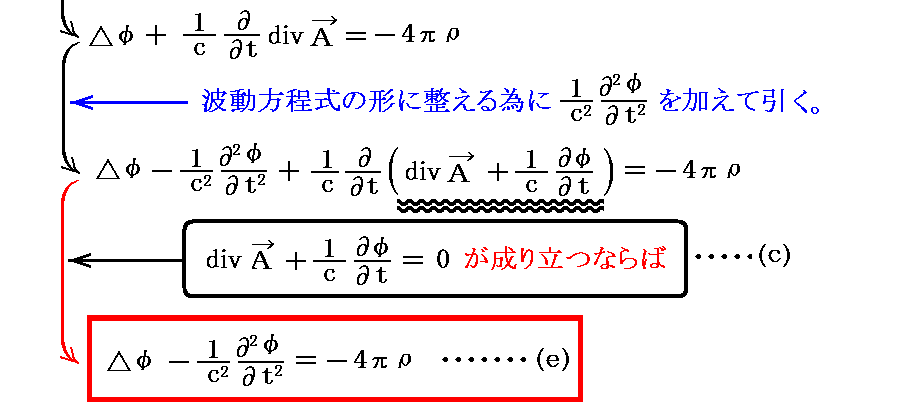
となり、スカラーポテンシャルφの非同次波動方程式が得られる。これを今後(e)とおく。
[補足説明1]
上記の電磁ポテンシャルについての非同次波動方程式(d)、(e)式を初めて導いたのはデンマーク人のLorenzです。
今日の教科書では、上記の様にMaxwell方程式に電磁ポテンシャルの定義式を適用して導きますが、Lorenzがこれらの波動方程式を導いたときにはMaxwell方程式を知らなかったので、別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」2.(2)1.でWhittakerが説明している方法で導いたのです。
要するに、最初に“遅延電位”と“遅延ベクトルポテンシャル”の表現式を仮定して、これが解であるためには上記の波動方程式が成り立たねばならないというやり方で証明したのです。実際の証明計算は別稿「非同次波動方程式の一般解」3.(3)や、別稿「ポアソン方程式と波動方程式」2.などをご覧下さい。
3.[Maxwell方程式系①~④式] と [電磁ポテンシャルA、φの波動方程式系(d)(e)] の等価性
1.2.項の手順とは逆に(d)、(e)式から①、②式を導くことができます。これは(2)1.~2.の逆変換に相当します。
そのとき、A、φをE、Hの方程式に変換するのですから、A、φとE、Hを結ぶ [電磁ポテンシャルA、φの定義式(a)、(b)式] の援用が必要なのは当然ですが、さらに [ローレンツの条件(c)式] の援用も必要になります。
まず、(d)式から①式を導く。そのとき(b)(a)式と(c)式を援用します。
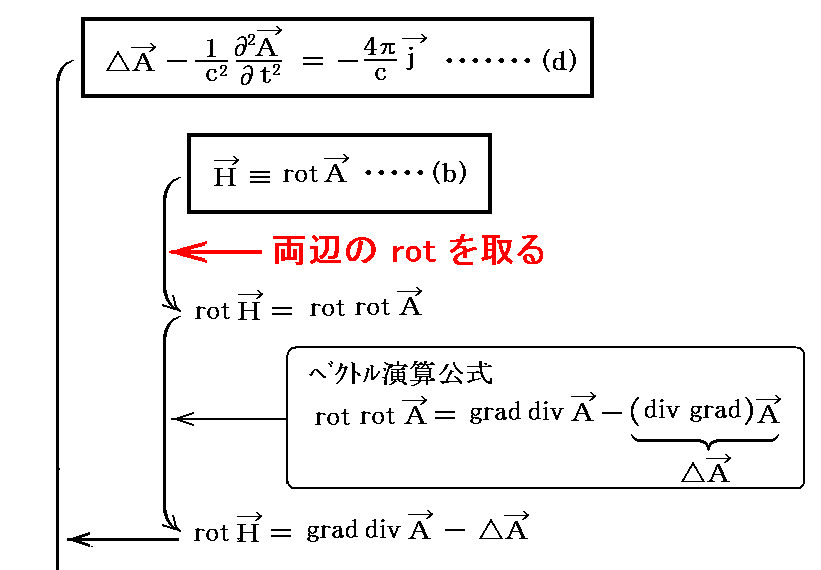
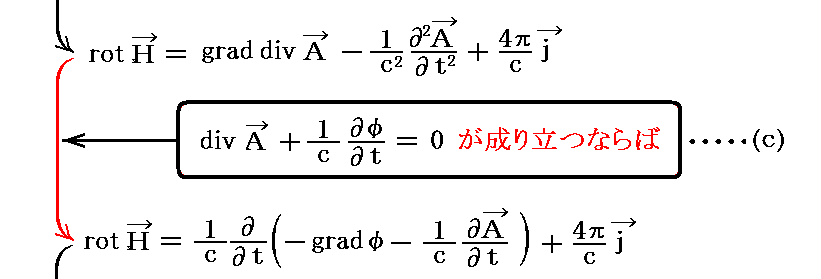
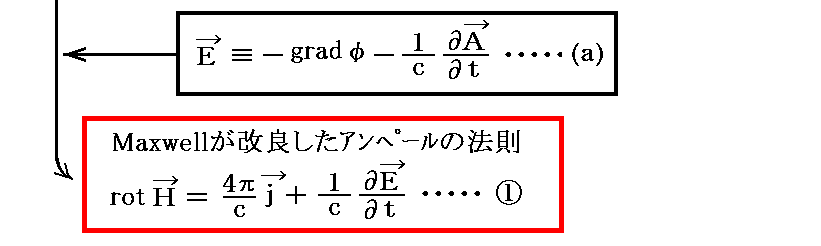
上記と同じなのですが、こちらの式変形も参照して下さい。
上は(b)式の両辺の rot を取ったものを援用しましたが、もちろん(a)式の両辺の 時間微分 を取ったものを援用しても良い。
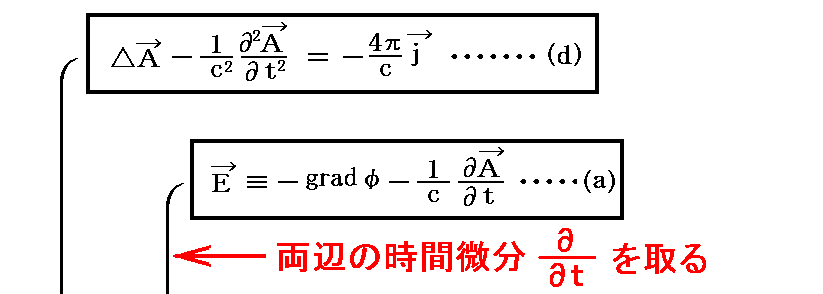
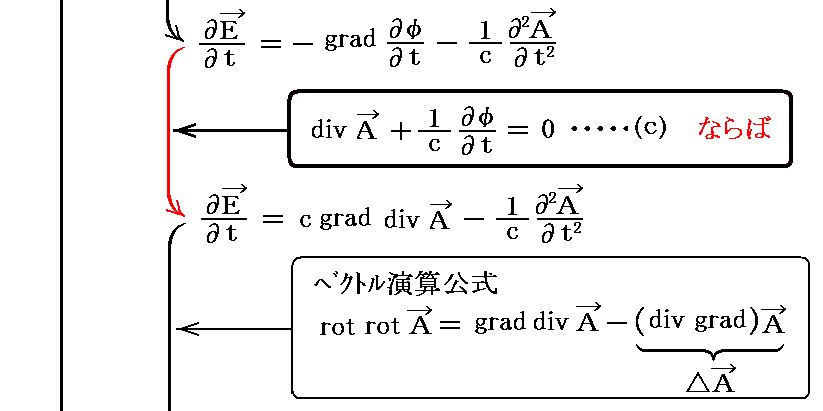
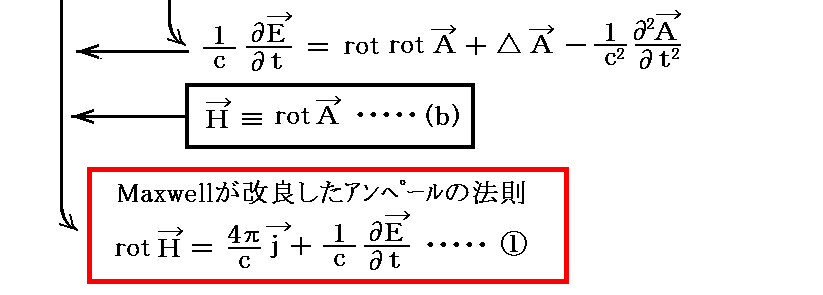
上記と同じなのですが、こちらの式変形も参照して下さい。こちらが、Lorenzが実際に行った式変形です。
次に、(e)式から②式を導く。そのとき(a)式の両辺のdivを取ったものを援用する。
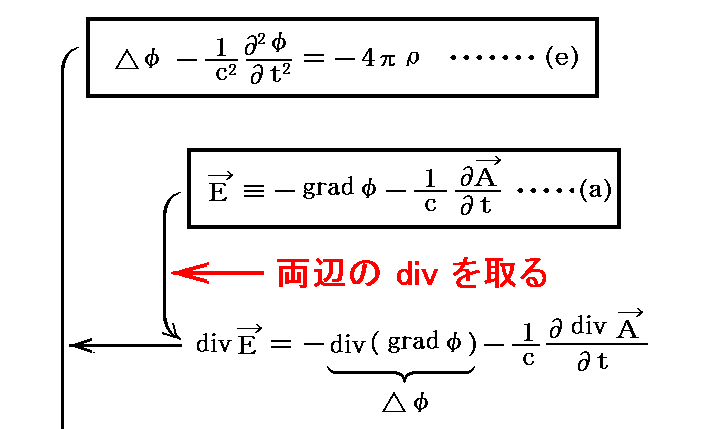
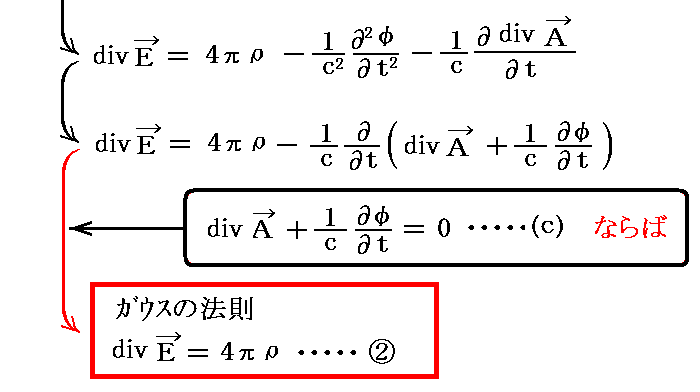
上記と同じなのですが、こちらの式変形も参照して下さい。
ここで述べた逆変換に相当する[電磁ポテンシャルA、φの波動方程式]から[Maxwell方程式]を求めることは、ある意味においてL.Lorenzがすでに行っている事です。このことについては太田文献2.p111-02をご覧下さい。
《3.(2) まとめ》
以上の様に逆変換も可能ですから、 [Maxwell方程式系①~④] と [電磁ポテンシャル方程式系(a)(b)(d)(e)] は互いに等価でして、下記の様に対応することが解ります。
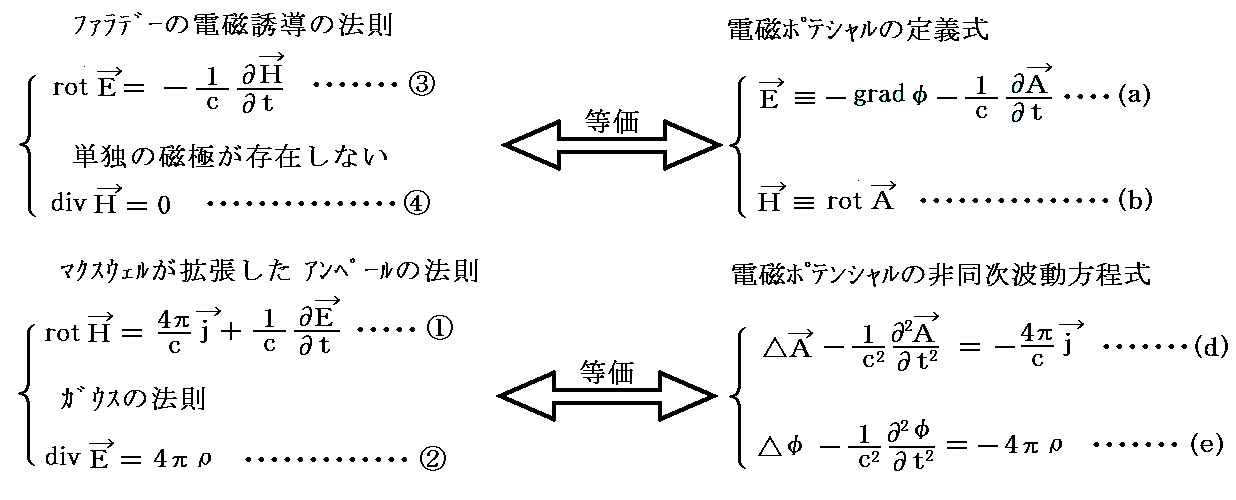
上段の③④と(a)(b)が対応するのは、③④が場そのものの関係を示しており、(a)(b)も場Aとφそのものの関係を(場EとHとの関係を含めて)示しているからです。
これに対して下段の①②と(d)(e)が対応するのは、どちらも場とその場を生じる物質(電荷と電流)の関係を示しているからです。
さらに補足しますと、3.(1)3.[補足説明1]で説明したように、上段の③+④ と (a)+(b) は、どちらも元々相対論的な方程式です。このことは、③+④については別稿 「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」5.(3)で、(a)+(b)については別稿の3.(1)で確認できます。そのとき別稿「ミンコフスキーの4次元世界」4.(2)2.[補足説明3]もご覧下さい。
さらに、相対論的に見通しの良い①+②方程式系が、そのまま(d)+(e)方程式系に変換されますので、右側の電磁ポテンシャル非同次波動方程式系も相対論的に見通しの良い方程式です。つまり、下段の左右どちらの方程式系も相対論的な見通しが良い方程式です。そのことは、(d)+(e)については別稿 「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」3.(2)で、①+②については別稿の5.(2)で確認できます。そのとき①+②に関しては2.(1)2.[補足説明1]も復習されて下さい。また、3.(3)3.[補足説明2]もご覧下さい。
結局の所、次節で説明する“Lorenzの条件式”(c)式に従った電荷と電流密度の分布の下で、非同次波動方程式(d)、(e)式を解いて電磁ポテンシャルAとφを求める。
次に、その様にして求められた電磁ポテンシャルA、φから(a)、(b)式によって電場Eと磁場Hを求めることになります。
(3)ゲージ条件
1.Lorenzの条件式
前節でMaxwell方程式①②から電磁ポテンシャルの波動方程式(d)(e)を導くとき
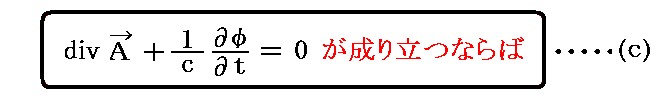
という条件式を用いました。この条件を明示的に指摘したのは、デンマーク人のL.Lorenz(1867年)ですので、今日この条件式は“Lorenzのゲージ条件”と呼ばれています。
今日の様にMaxwell方程式系に電磁ポテンシャルの定義式を適用して波動方程式を導く立場で見ると、この条件式が必要な理由は単純です。この条件を置かないと、この余分な項のために、綺麗な形の非同次波動方程式にならないからです。この余分な項が消去できれば、電磁場ポテンシャルの解を電荷密度、電流密度の遅延関数の積分として求める事ができる波動方程式が導けます。このことは3.(2)1.~2.を復習されれば明らかです。ただし、歴史をたどれば解るように、Lorenzはこれとは全く違う方法でこの条件式を導いています。
それでは、Lorenzはどの様な過程でこの条件式を導いたのかといいますと、彼は非同次波動方程式を満たす(彼が発見した)遅延電荷密度関数や遅延電流密度関数に“電荷保存則”を適用して導いたのです。
このことに付いては太田文献2.§4.2のp110-02や、ホィティカーの解説「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」2.(2)1をご覧下さい。これは別稿「線形振動子による電磁波の放出」1.(2)2.でも説明しました。
ホィティカーの解説が最も解りやすいと思います。これを4次元相対論的に展開したものが3.(3)3.で説明するものです。
2.ゲージ条件が必要なことの今日的な説明
Lorenzがこの条件式を設定した理由は明白ですが、その様な条件を設定できる根拠はどこにあるのでしょうか。その事に付いて、今日では次の様に説明されています。
電場Eや磁場Hの代わりに電磁ポテンシャルφ、Aを用いた議論では、なぜこの条件式が必要になるのか。それは、3.(1)で導いた電磁場E、Hと電磁ポテンシャルA、φを結び付ける定義式(a)(b)では電磁ポテンシャルの決定に任意性が残るからです。別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」2.(3)1.[補足説明1]で説明した様にこの定義では電磁ポテンシャルには任意性が残ります。最初に電磁ポテンシャルがA0とφ0で与えられた場合、それらに gradχ や -(1/c)∂χ/∂t を加えた
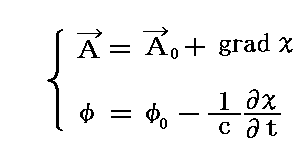
も定義式(a)と(b)を満足します。
そのことは上式を定義式に代入してみれば
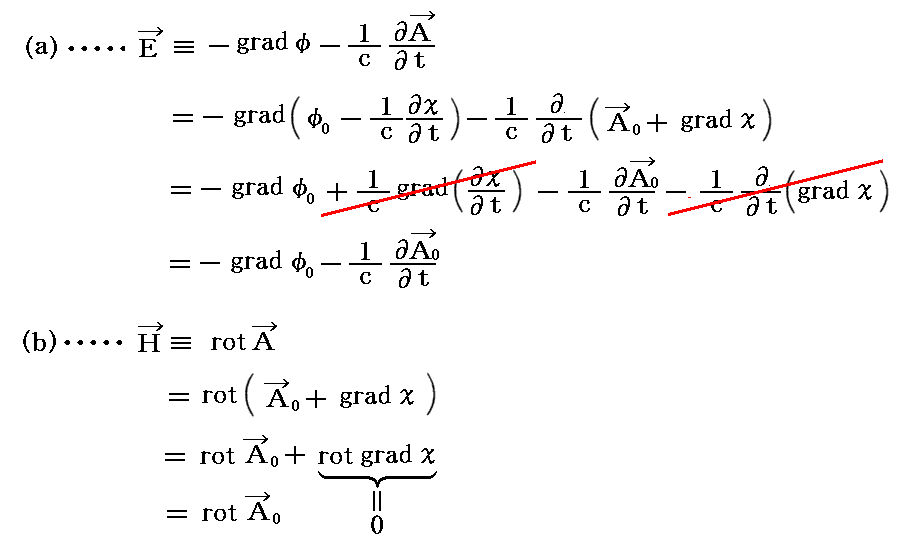
となることから解ります。
ここでχは時間的に変化する任意のスカラー関数であってかまいませんが、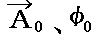 の組みから
の組みから の組みへ移る事を“ゲージ変換”(gage transformation)と言います。上記のことは、観測可能な量である電場Eや磁場Hはゲージ変換しても、その値を変え無い事を意味します。
の組みへ移る事を“ゲージ変換”(gage transformation)と言います。上記のことは、観測可能な量である電場Eや磁場Hはゲージ変換しても、その値を変え無い事を意味します。
このように電磁ポテンシャルが持つ任意性を“ゲージ自由度”といいます。実際の電場Eや磁場Hを定めるAやφを確定するには、その自由度を制限するさらなる条件が必要で、その制約条件を“ゲージ条件”と言います。
上記の“Lorenzの条件式”は、それに相当するものだと言うのが今日的な説明です。しかしこれはいかにも付け焼き刃的なつじつま合わせの説明です。
Lorenz条件式に対する上記の説明は、ランダウ・リフシュツ著『場の古典論』の中で説明されているものです。推測ですが、今日多くの書籍で採用されているこの説明は、おそらく『場の古典論』の記述からの受け売りなのでしょう。
3.Lorenzの条件式の物理的な意味
“Lorenzの条件式”を
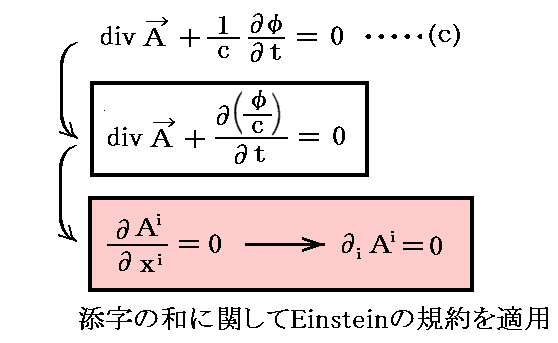
と書き直して、(Ax,Ay,Az,φ/c)≡(A1,A2,A3,A4)と並べて見れば、相対論的な“電荷保存則”
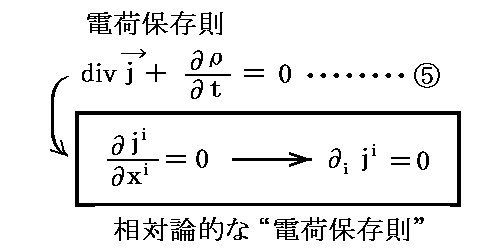
に現れる4元反変ベクトル(jx,jy,jz,ρ)≡(j1,j2,j3,j4)と旨く対応します。どちらも相対論的な4元反変ベクトルに4元div演算(共変ベクトル)を施したら 0 となる事を示している。
このことは別稿「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」3.(1)[補足説明3]と[補足説明5]で説明しました。ならば電荷保存則とLorenzの条件式が密接に関係するのではないかと思われます。
実際、[電磁ポテンシャル波動方程式(d)、(e)式] と “電荷保存則”⑤式 が成り立てば、以下の様にして“Lorenzの条件”(c)式が導けます。すなわち(d)、(e)式を成分表示して相対論的な4元ベクトル方程式とみなして変形する。本当は、(jx,jy,jz,ρ)と(Ax,Ay,Az,φ/c)はどちらも反変ベクトルですから、(jx,jy,jz,ρ)と(Ax,Ay,Az,φ/c)の様に書くべきです。その辺は上記別稿を復習されて下さい。
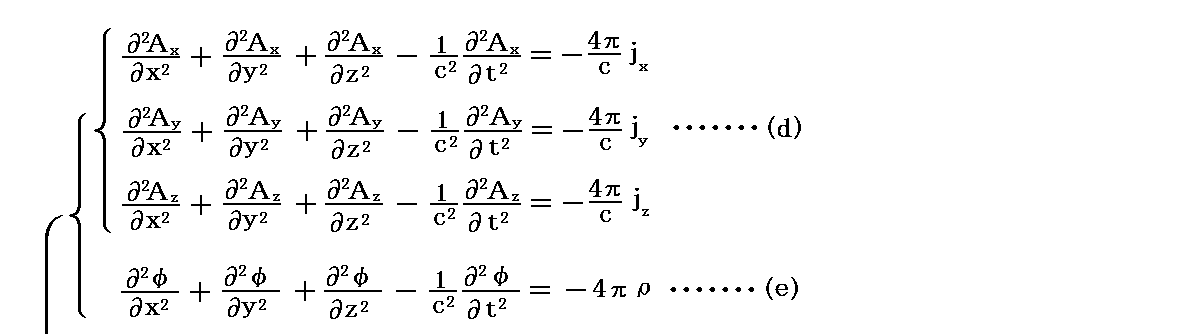
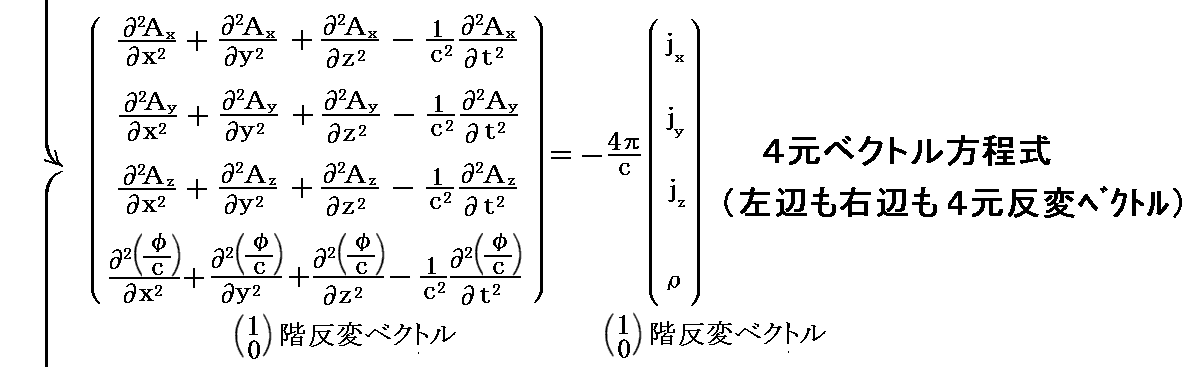
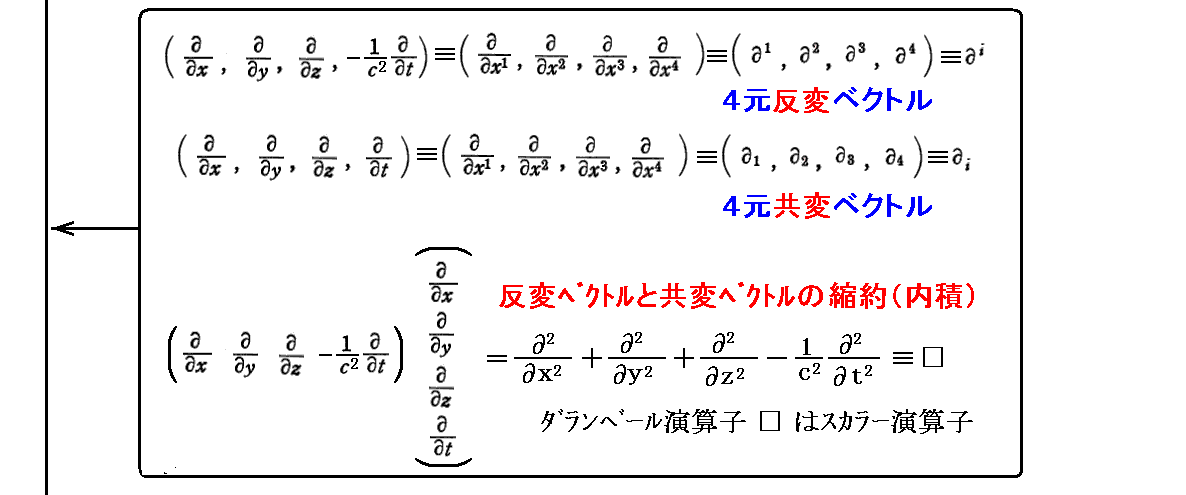
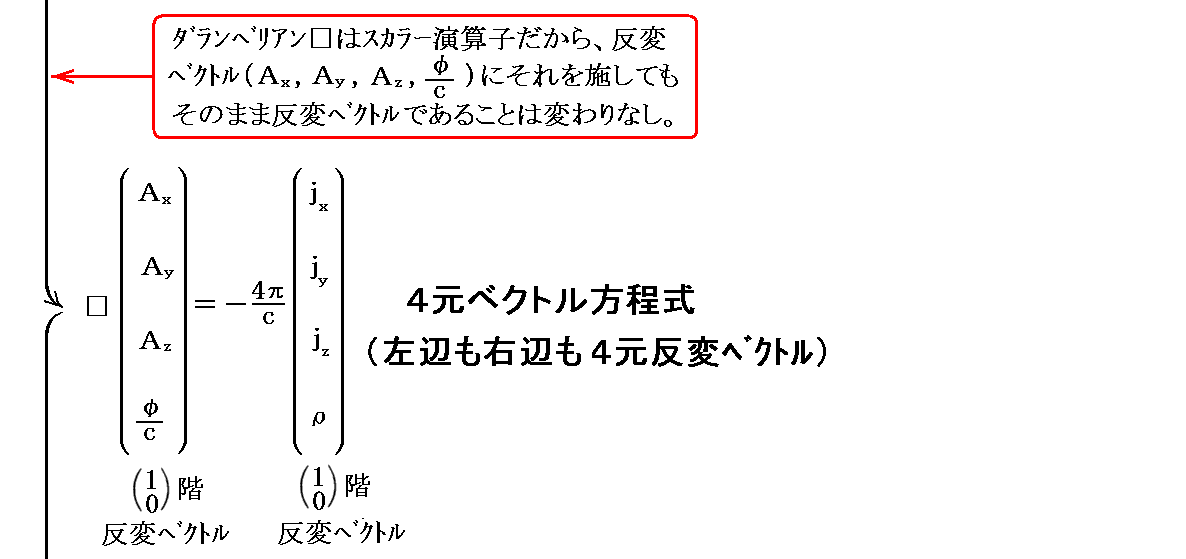

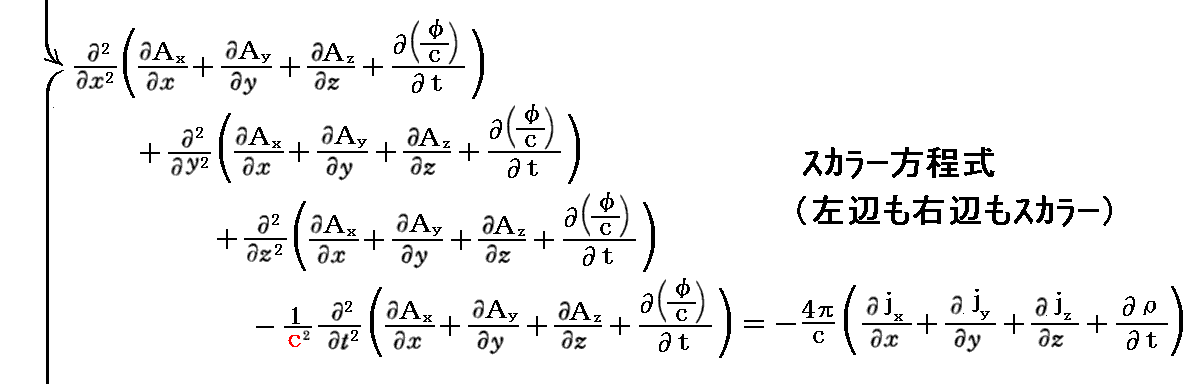
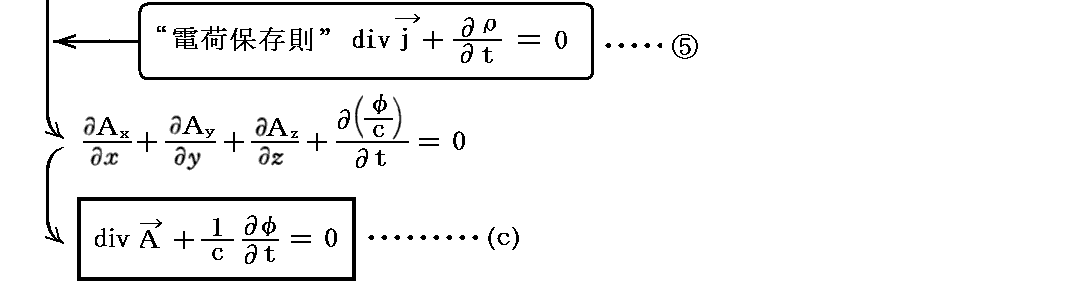
となります。
これを3次元的・古典論的に行うと、「Maxwell方程式系の先見性と電磁ポテンシャル」2.(2)1におけるホィティカーの示した手順の脚注1)の展開になる。
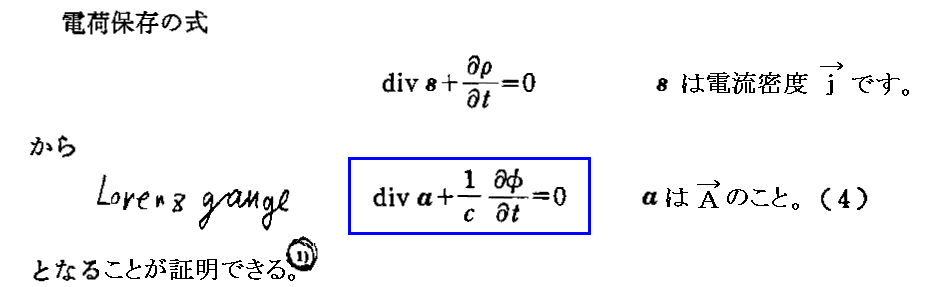
すなわち、上記の“電荷保存式”中の電流密度sや電荷密度ρが遅延時間の項を含む遅延電流密度関数s’(t-r/c)であり、遅延電荷密度関数ρ’(t-r/c)であるとすると、それらは当然ベクトルポテンシャルaとスカラーポテンシャルφの“非同次波動方程式”
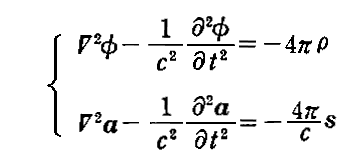
の解となりますので、
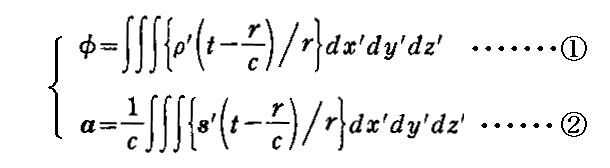
の様におけます。以下の展開ではこの2つの関係式①②から出発します。
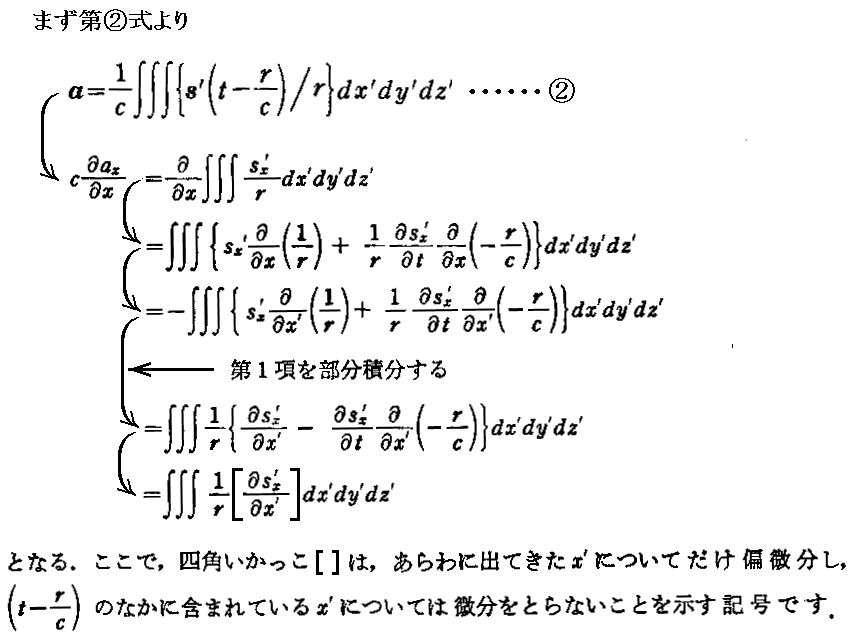
この式変形の意味は解りにくいので、別稿「線形振動子による電磁波の放出」1.(2)2.を参照されたし。
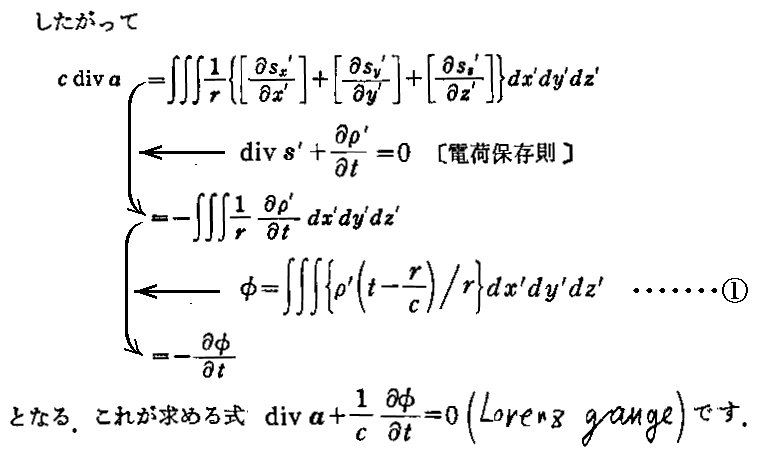
いずれにしても、“Lorenzの条件”(c)式 は [電磁ポテンシャル波動方程式(d)、(e)式] と “電荷保存則”⑤式 から必然的に導けます。だから“Lorenzの条件式”の物理的意味は電荷保存則であると言って良いでしょう。
このとき、2.(1)2.[補足説明1]で注意したように“電荷保存則”⑤式 は [Maxwell方程式①、②式] と等価でしたから、[Maxwell方程式①、②式]と[電磁ポテンシャル波動方程式(d)、(e)式]が等価なら、Lorenzの条件式(c)式が(d)、(e)式の中に含まれているのは当然かも知れません。実際、(d)、(e)式を得るためには(c)式が成り立つことが必然の条件なのですから。このことは3.(2)1.や3.(2)2.の式変形を見なおせば確認できます。。
その様に見なすことができるのは、スカラーポテンシャルφやベクトルポテンシャルAが下記[補足説明1]で説明する様なものであるとすれば φ と A の関係は丁度“電荷保存則”に於ける ρ と j の様な関係と見なすことができるからでしょう。]
[補足説明1]
ここで、スカラーポテンシャルφやベクトルポテンシャルAとは何なのかを補足します。これらの量の説明は
前野昌弘著「相対論講義録2010年度(平成23年2月4日版)」p97~98
の解説が秀逸なので前野氏のHPからそのまま引用しています(別稿「カルマン渦列」2.(3)2.[補足説明3]も参照)。
スカラーポテンシャルφをつくるものは電荷と、ベクトルポテンシャルAを作るものは電流になります。下左図の○に+の記号の位置に電荷が存在する。また下右図の黒矢印の位置に電流密度素片が存在するとします。本来電流は連続した回路となるのですが、その一部が取り出されていると考えて下さい。
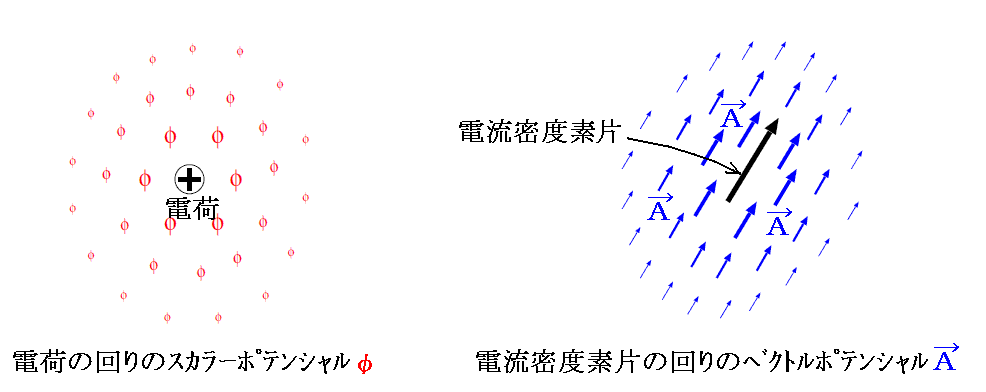
上左図の電荷の回りのφの値を決めるのが、次式
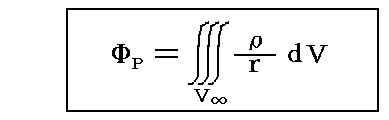
です(非有理化gauss単位系)。上左図ではφ記号の大きさでφの値の大きさが、その分布の様子とともに示されています。φの大きさは電荷からの距離に反比例して小さくなる。もちろん上式のρは電荷密度です。そして、電荷がたくさん分布している場合は、それぞれの電荷が作るスカラーポテンシャル場を重ね合わせたものになります。
また上右図のAベクトルの分布を決めるのが、次式

です(非有理化gauss単位系)。図の青矢印の分布でベクトルポテンシャルAの分布の様子が示されています。ベクトルAの方向がすべて電流密度素片の方向を向き、その大きさは電流密度素片からの距離に反比例して小さくなります。もちろん上式の(jx、jy、jz)は電流密度ベクトルです。もちろん電流密度素片が連続的に分布して回路を作る場合は、それぞれの電流密度素片が作るベクトルポテンシャル場を重ね合わせたものになります。
スカラーポテンシャルの意味は別稿「保存力」で説明した二次元の場合のポテンシャルの山を三次元に拡大したもので尽くされています。もし電荷qがスカラーポテンシャル場φの中に存在するとqφという位置エネルギーを持つことになり、場φの大きさの勾配に従った力を受けることになる。
ベクトルポテンシャルの意味を、上図の電流密度素片が縦方向に無限に連なった無限直線電流の場合で説明します。無限直線電流が作るベクトルポテンシャルAの分布は、上記の電流密度素片が作るベクトルポテンシャルを重ね合わせたものになりますから、下図の様に直線電流の回りに、直線電流の方向を向いて分布し、その大きさは距離に逆比例して小さくなります。
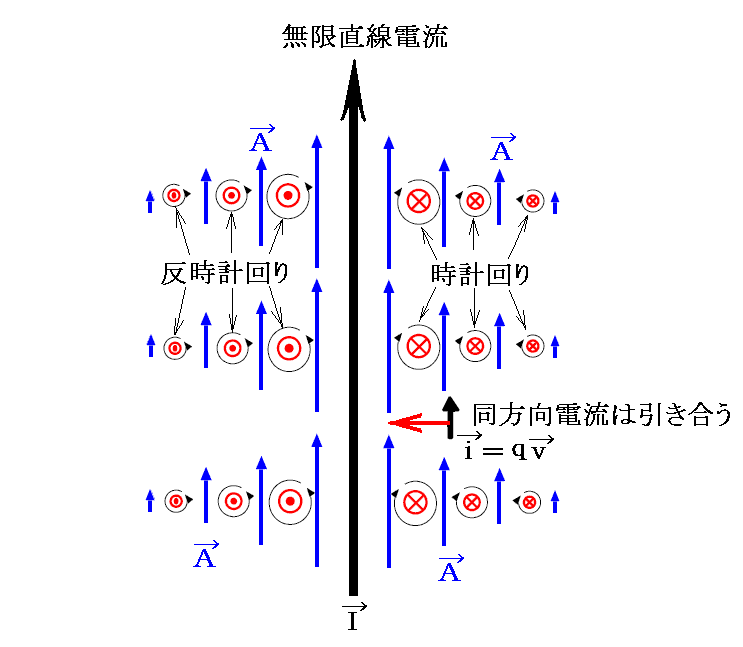
このベクトル場Aを流れの流速を表す様なものだと見なして、別稿「カルマン渦列」2.(2)で説明したベクトル演算 rot
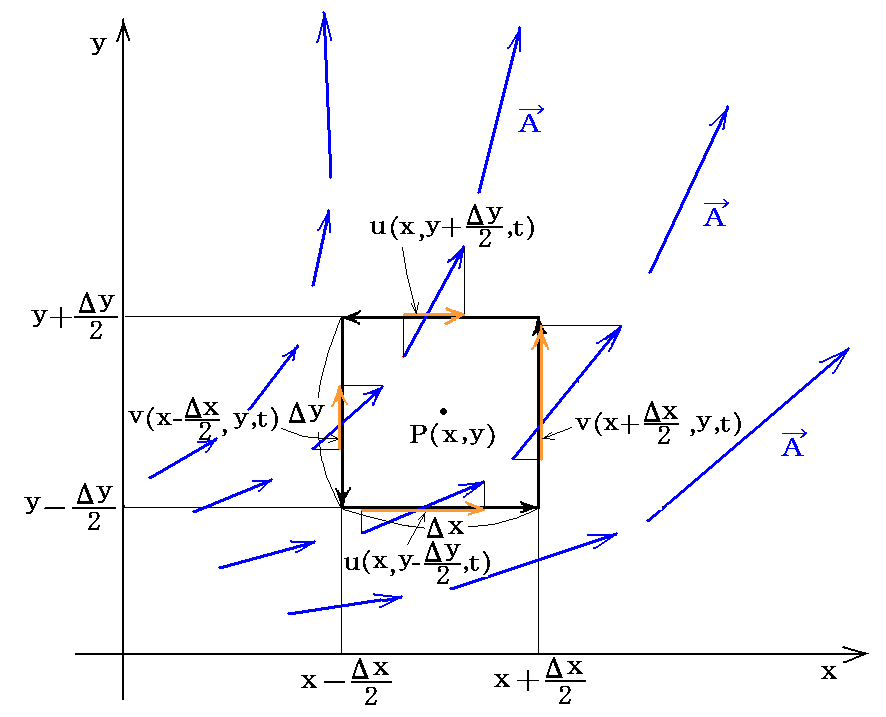
の意味を適用する。
一つ前の図の青矢印で示した流れの場Aは導線の左側では反時計回りの渦を、導線の右側では時計回りの渦を生み出す。実際ベクトル演算rotAはその渦の回転を右ネジと見なしたときネジの進む方向のベクトルを意味する。この rotA こそ電磁気学における磁場ベクトルHです。
つまり磁場H=rotAは導線の回りに渦を巻くように存在することになる。一つ前の図の赤丸に赤点は手前向きの磁場ベクトルHを赤丸に赤×は向こう向きの磁場ベクトルHを表す。その○の大きさが磁場ベクトルHの大きさを表している。
このようなベクトルポテンシャル場の中に電流素片 i=qv を入れるとローレンツの力の法則に従った力を受けるので、電流素片 i=qv は一つ前の図中赤矢印方向の力を受けることになる。
つまり、ベクトルポテンシャルAと同方向の電流要素 i はベクトルポテンシャルAが増大する方向に力を受け、ベクトルポテンシャルAと反対向きの電流要素 i はベクトルポテンシャルAが減少する方向の力を受ける。これはちょうど-電荷がスカラーポテンシャルφが増大する方向に力を受け、+電荷がスカラーポテンシャルφが減少する方向に力を受ける事情によく似ている。
まさに、それら分布状況がポテンシャル(位置エネルギー)を表している。
[補足説明2]
3.(3)3.本文中の式変形に付いて補足します。
《3.(2) まとめ》で示した様にMaxwell方程式①②は電磁ポテンシャル非同次波動方程式(d)(e)と等価です。
そのとき、①②を4元ベクトル方程式に統合して両辺の4元divを取ったものについて2.(1)2.[補足説明1]で説明しました。そのとき左辺の4元テンソルの反対称性から左辺が 0 となる事が必然的に言えて、それから電荷保存則が導けるのでした。
ここで示した操作は(d)(e)に付いて、それと同じ操作4元divを取るものです。その式変形の類似性について、是非そこと比較検討して見てください。ここでは、まず右辺の電荷保存則から左辺が 0 になる事が必然的に言えて、それから左辺の構成要素であるローレンツの条件式が成り立つ事が言える事になったのです。
4.参考文献
この稿を作るに当たって、下記文献を参考にしました。感謝!
- 太田浩一著「マクスウェル理論の基礎(相対論と電磁気学)」東京大学出版会(2002年刊)
- 太田浩一著「マクスウェルの渦アインシュタインの時計(現代物理学の源流)」東京大学出版会(2005年刊)
第4章、第7章および引用文献のリスト
- 内山龍雄著「相対性理論」岩波書店(1977年刊)第Ⅲ章“相対論的電磁気学”
これは電磁気学単位系としてMKSA有理化単位系を採用し、4元ベクトルや計量テンソルの表現として別稿3.で説明した左側の定義を用いています。ただし、4元電磁ポテンシャルの表現は単位系に依存しますので注意。
- 中野董夫著「相対性理論」岩波書店(1984年刊)第8章“電磁気学”
これは電磁気学単位系としてMKSA有理化単位系を採用し、4元ベクトルや計量テンソル表見として別稿3.で説明した左側の定義を用いています。ただし、4元電磁ポテンシャルの表現は単位系に依存しますので注意。
- P.G.ベルグマン著「相対性理論序説(新訂増補版)」秀潤社(1978年刊 原本は1942年刊)非有理化Gauss単位系(磁場H)
第Ⅴ章“n-次元連続体におけるベクトルとテンソル”、第Ⅶ章“相対論的電気力学”
- C.メラー著「相対性理論」みすず書房(1959年 原本は1951年刊)
第Ⅳ章“相対性理論の4次元定式化:テンソル算法”、第Ⅴ章“真空中の電磁気学”
これは有理化したGauss単位系を用いていますので注意して下さい。