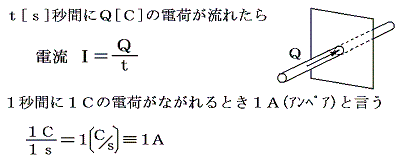
このページを印刷される方はこちらのバージョンをご利用下さい。ブラウザーでは見にくいのですが印刷は鮮明です。
電気分野の大法則ですが、何故偉大な法則なのかを説明します。
電流とは導線のある断面を単位時間に流れる電気量のことです。
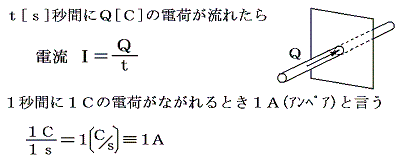
電流は I や i の記号で表されるが、それは“intensity of electricity”の頭文字で、もともと“電気の強さ”を意味する量であった。電気の強さに関する量で最初に正確に測定できたのは電圧ではなくて電流である。以下に述べるねじり秤の先につけた磁針を回転させる力は、まさに電流に比例するからである。オームはねじり秤を用いて電流の大きさを正確に測定することができたので法則を発見することができた。
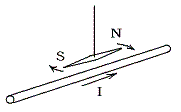
ところで導線の中を電子はどれくらいの速さで移動しているのだろうか。銅の密度は8.93g/cm3を用い、銅原子1個当たり1個の自由電子を供出すると仮定して計算してみる。以下の比例計算から普通の電流現象での電子移動速度は数mm/s程度であることが解る。
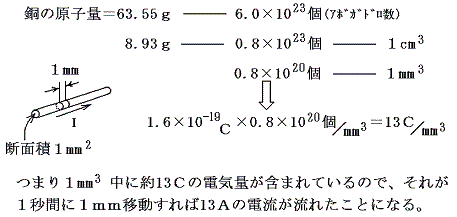
普通の電気製品を流れる電流は断面積1mm2程度の導線に数アンペア程度であるから、まさに電子の移動速度は数mm/s程度である。しかし電流に関係して3つのレベルの速度がありこれらの違いがどの様に関わってくるかを理解することが大切です。
後で説明するように上記の1と2の速度の違いがオームの法則の成立に重要な意味を持つ。
また、1と3の違いが別稿「発電機とモーターの理論」、「交流電気回路」、「交流電源とRLC回路」、「自己誘導とRL回路」等で本質的な意味を持つ。
ゲオルグ ジーモン オーム(Georg Simon Ohm 独)は1827年に「数学的に取り扱ったガルバーニ回路」で今日オームの法則と言われるものを報告した。これは I=V/R という法則だが、何故これが大法則で、何故この発見が偉大なのか良く解らないのが高校生の偽らざる心境だと思う。
しかし、ボルタの電池が発明されて僅か27年後の電流現象について混沌として不可解な当時の状況を考えて欲しい。この法則の発見でもって初めて、今日の電流、電圧、抵抗という概念が確立され動電気を定量的に取り扱えるようになった。そして不可解な電流現象を見事に統一的に理解できるようになった。
さらに、この法則は実験則・経験則であるにもかかわらず下記の様に驚くべき広範な適応性を持っていた。
ボルタの電池の発明が大いなる動電気学を生み出したのだが、オームの法則の発見なくしては動電気の世界の理解・発展は無かったであろう。静電気学のレベルに止まっていたのでは、その後の偉大な電磁気学・電気工学・電子工学の発展は無かった。
これは[導線を流れる電流は、導線の両端の電位差に比例する。比例定数の逆数を導線の抵抗というが、抵抗は流れる電流の量によらない]ことを言っている。
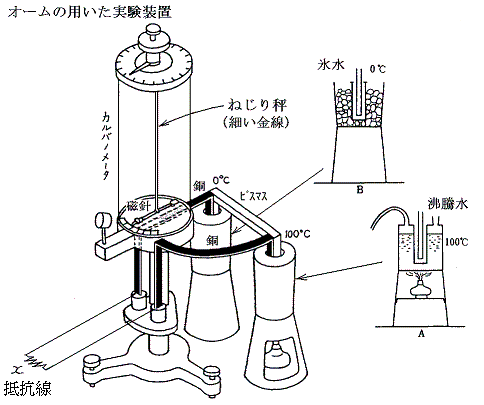
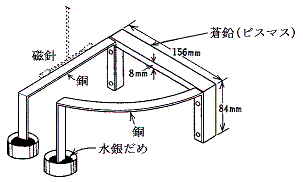
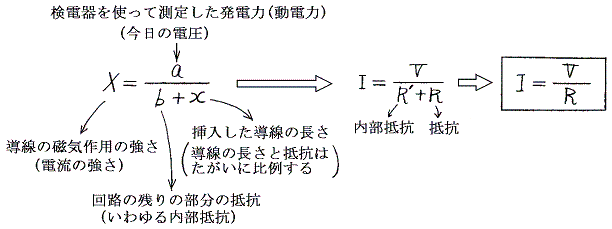
オームは抵抗線xとして同じ太さの様々な長さの銅線をもちいた。抵抗線の長さxとガルバノメーターの捻りばかりの捻り角度から求まる電流強度Xの測定値に対して上記の実験式が成り立つことを見つけて、今日オームの法則と言われるものを導いた。彼が成功した理由は以下の3つである
オームは長さ、太さ(切り口の面積)、材料のそれぞれ異なる導線からなる回路についても実験した。そして、この回路の電流の強さIは、すべての動電力Eの和(異種材料の導線の接触点ごとに動電力が働く)に比例し、回路の「修正された長さ」に反比例することを示した。
「修正された長さ」というのは、オームが抵抗という概念の変わりに用いたもので、導線の均一部分の実際の長さをL、その部分の切り口の面積をS、材料の伝導度をk(今日の抵抗率ρの逆数)とするとL/(kS)で表される。これは[導線の抵抗は、その長さに比例し、断面積に反比例する]ことを示すものである。
上記のオームの法則は電場の基本的な法則からは導くことはできない。電流が流れる物質中に起こる過程を統計的に理解することで初めて導くことができる近似的な法則で、それが成り立つ範囲の制約がある。しかし法則が成り立つ条件範囲が非常に広範であるが故に、この法則が偉大なのである。
電位差によって生じる電界強度はE=V/dである。だから力F=qEより動かされる電荷の運動は加速度に関係するはずである。しかしオームの法則は電位差V(つまり電界強度E)が定常的な電流を生じるというのだから、力が電荷の平均的な速度(加速度ではない)に結びつけられると言っている。これは驚くべきことだ。このようになることの理由を以下で考える。
電場の中の電子の動きが定常的な流れになる説明として下図のパチンコ台モデルがよく使われる。斜面に摩擦は無いが、釘との衝突により加速にブレーキがかかり一定の速度で電子は流れていくとする。釘が密になるほど小刻みな衝突を繰り返して流れが悪くなり、抵抗の大小と電流、発熱の関係を旨く説明できる。
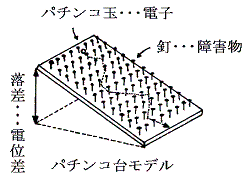
しかし参考文献(1)で指摘されているように、このモデルでは旨くいかない。以下でそのあたりを説明する。
今簡単化して1次元で考える。釘と釘との間隔を L として釘が一列に並んでおり、釘に衝突するたびに速度が零にリセットされると考える。そうすると次の釘との衝突までは初速度零の等加速度運動をすると考えることができる。力学で習う等加速度運動のとき成り立つ式を用いる。釘に衝突してから次の釘に衝突するまでの時間をtc、釘に衝突する直前の速度をvc、電界による加速度をaとすると
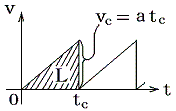
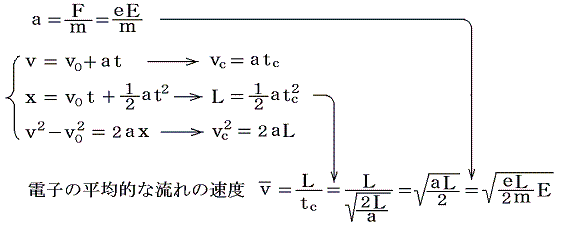
となり[電子の平均的な流れの速度]は[電界の平方根]に比例する。これはオームの法則と矛盾する。
このようになってしまったのは釘に衝突したときの速度が零になると仮定したためである。実際には1章 電流 で述べたように金属中の電子は105m/s程度の速度で動き回っている。だから釘と衝突した次の瞬間にも105m/s程度の速度を持っているとしなければならない。
前記のモデルを次のように改良する。今一次元的に間隔 L で釘が並んでいるとする。そして電子は右向きと左向きにv0=105m/s程度の速度で同数の電子が走っているとする。それらが右向きの電界による力を受けて、右向きに進んでいる電子は加速され、左向きに進んでいる電子は減速されるとする。しかし、それらはやがて次に位置する釘と衝突し、それらのもつ速度がリセットされて最初の熱運動による速度v0にもどるとする。そしてその時点で右向きと左向きの電子の数は再び等しくなるとする。(おそらくここの仮定が一番問題になるところだろう。もう少し立ち入った議論は参考文献(4)に譲ることにして、ここではこの仮定が成り立つらしいというところを感じ取って下さい。)
前記のモデルと同様に、釘に衝突してから次の釘に衝突するまでの時間をtc、釘に衝突する直前の速度をvc、電界による加速度をa、衝突から次の衝突までに進む距離(釘の間隔)をLとすると
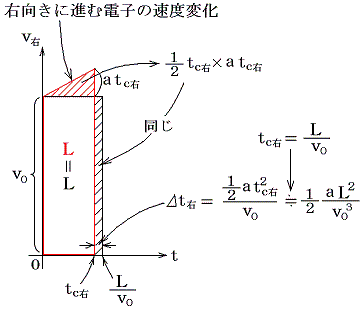
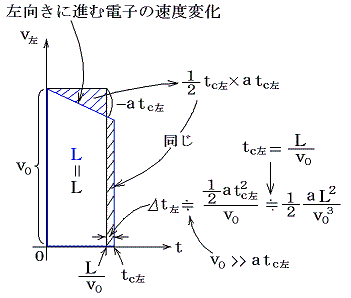
のような関係になる。だから
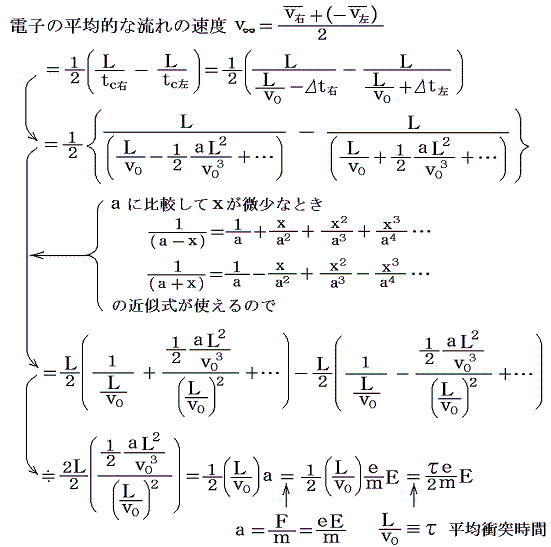
となり、[電子の平均的な流れの速度v∞]は[電界の強さE]に比例することになる。
このような結論が得られる理由は、電界によって得られる速度は釘に衝突するごとにリセットされて零にもどるが、電子の熱運動に伴う速度は釘に衝突してもほぼそのままの値を持ち続ける所にある。つまり、リセット時間は熱運動による速度に関係しており、電界によって得られる速度(これが電流のもとになる)成分に無関係になる。これがオームの法則を保証する条件です。パチンコ玉モデルが旨くいかなかったのはリセット時間が電界によって得られる速度に依存していたからです。
[補足説明]
多くの参考書では以下のように説明している。リセット時間tcは熱運動による速度に関係し、Eには無関係だから
となり、電子の平均的な速度はEに比例する。
しかし、そういわれても、tcがなぜEに比例しないのかはなかなか納得できない。また、熱運動による速度ベクトルは様々な方向を向いているのだから、リセット時間とどのように関係するのか疑問に思うところです。その為上記の様なモデルを考えました。
前節の結論を用いてオームの法則を導く。ただし簡単のために電流を担う電子は正電荷として論じる。
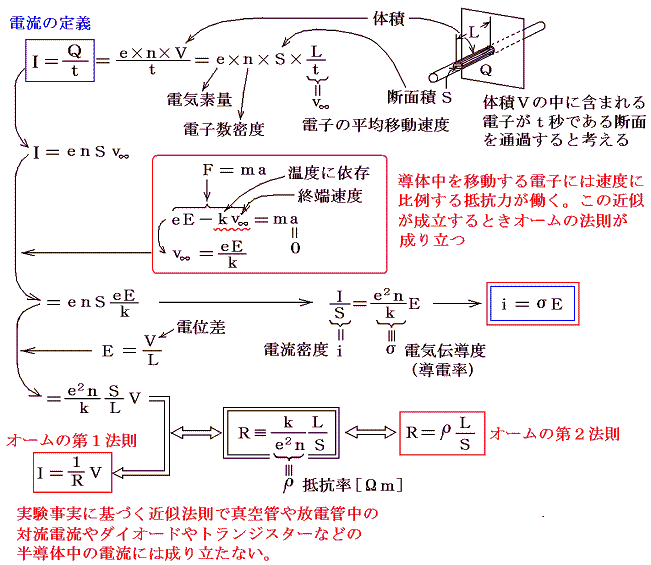
(1)節の結論を用いると(2)節の比例定数kは
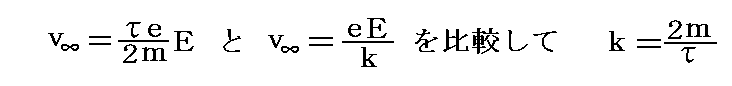
となる。ゆえに抵抗率ρ=1/σ(導電率の逆数)は
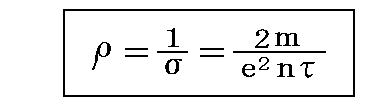
となる。
ここで、導体として銅を取り上げ数値的な見積もりをしてみる。以下の計算では
銅の導電率 σ=5.8×107/Ωm
銅原子1個に自由電子1個とすると 電子数密度 n=8×1028個/m3
電子の質量 m=9.1×10-31kg
電子の電荷 e=1.6×10-19C
の値を用いる。
上式より、電場による加速によって得る速度がリセットされる衝突と衝突の間の時間間隔(平均衝突時間 τ)は
![]()
となる。前記の数値を代入すると平均衝突時間 τ は
τ=(2×9.1×10-31kg×5.8×107/Ωm)÷{(1.6×10-19C)2×8×1028個/m3}=5.0×10-14s
程度となる。
また1.で述べたように電子の熱運動による速度は運動学的な理論によりv0=105m/s程度だから電子が衝突までに走る平均的な距離(平均衝突距離 L)は
L=v0×τ=105m/s×5.0×10-14s=5.0×10-9m
程度になる。
これは原子の大きさ(Cuで2.56×10-10m)の20倍程度になる。なぜこんな大きな値になるのかというと、電子の波としての性質による。電子のド・ブローイー波長(高校物理の最後で習う)は、電子の質量が原子の数千分の一の為に常温付近でλ=h/p=h/(2mkT)1/2〜10-9m程度になり、金属結晶を構成する原子間の距離〜10-10mより大きくなる。これは金属中の自由電子は非常に高密度で、濃密な相互作用をする状態にあることを意味する。そのため電子が従うパウリの排他原理を考慮した量子力学的な扱いをしなければならない。
電界Eの強さを10V/m程度とすると電子の平均流速 v∞ は
v∞=τeE/m=5.0×10-14×1.6×10-19×10/9.1×10-31=8.8×10-3m/s〜数mm/s
程度となり1.章の説明を裏付ける。
電子が衝突から次の衝突までに動く距離(平均衝突距離 L)は銅Cu原子の場合5.0×10-9m程度だったが、その間に電子をkT程度の運動エネルギーを持つように加速しようとしたら
kT=(1/2)mv2=eV=eEL=e×E×5.0×10-9
が成り立つ。
ここで、ボルツマン定数k=1.38×10-23J/K、絶対温度T〜300K程度、電子の電荷 e=1.6×10-19Cを代入すると電場の強さは
E=(1.38×10-23×300)/(1.6×10-19×5.0×10-9)=5×106V/m〜5万V/cm
となる。
つまり電場の強さがこのレベルまで強くなるとv∞がEに比例するということが成り立たなくなり、オームの法則は成立しなくなるであろう。しかしこれは導体中に生ずる電場としてはかなり強い電場です。静電気学では絶縁体に対する摩擦電気などでこの程度の電場は簡単に発生できる。しかし、自由電子が動き回って本来電界が存在しない金属導体の中にこれほどの電位差を生じさせるためにはかなり強大な電流を流さなければならない。ゆえに普通の状況ではオームの法則は問題なく成り立つと考えて良い。
抵抗線を電流が流れる場合、電流がする仕事はすべて熱エネルギーになる。その時間的割合Pは抵抗線の両端の電位差V、電流Iと P=VI=RI2=V2/R となることは授業でならう。このようになるメカニズムを以下で説明する。
3.(1)の改良モデルで考える。抵抗線の中の自由電子は、正イオンと衝突するたびに、それまでに電場から得た運動エネルギーを失うものとする。また、抵抗線中の電場E、電子の電荷−e、電子質量m、自由電子と正イオンが衝突する平均の衝突時間の間隔をt(これは3.(1)で述べたリセット時間τ)とする。
まず自由電子1個が正イオンとの1回の衝突によって失うエネルギーを求める。以下簡単化のために電子の電荷は正として考える。3.(1)で述べたように電子は最初からある速度v0で動いている。
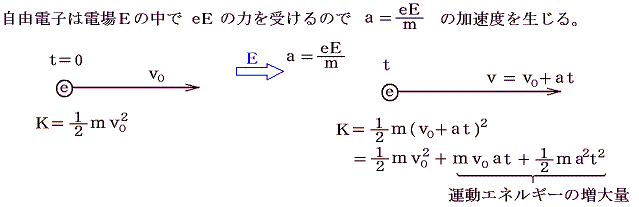
このとき増大した運動エネルギーを衝突で正イオンに与え電子は元のエネルギーにもどる。そのとき衝突によって失われる自由電子の運動エネルギーが金属結晶中のイオンの熱エネルギーになる。そのときの値は
これは注目すべき事柄である。ここでも統計的な取扱が必要である。3.(1)のモデルでは、電子の半数は電場とは反対方向に動いており、それらは電場により減速される。つまり
となる。そのため電場に対して正・負の方向に動いている電子を同時にしかも統計的に取り扱わねばならない。つまり
となる。電場の方向に対して正・負の方向に動く二つの電子をペアで考える。それらの電子が正イオンに衝突して元の速度に戻る過程で失うエネルギーの総和は、上記の値を2で割って、電子1個当たり
となる。抵抗線の中にある自由電子の数は N=nSL (抵抗線の長さをL、断面積をS、自由電子密度をn)である。自由電子はt秒間に1回衝突するので、1秒間に1/t回衝突する。従って、1秒間に抵抗線中の全電子(N個)が衝突することによって失われるエネルギーはP=KN/t となり、
と変形できる。これは、お馴染みの式で、抵抗線中の全自由電子が毎秒正イオンに与えるエネルギーであり、抵抗線が毎秒生み出すジュール熱である。
3.(2)のやり方で考える。ここでも簡単のために電子の電荷が正であるとして電子の移動方向と電流の方向が一致するとして考える。
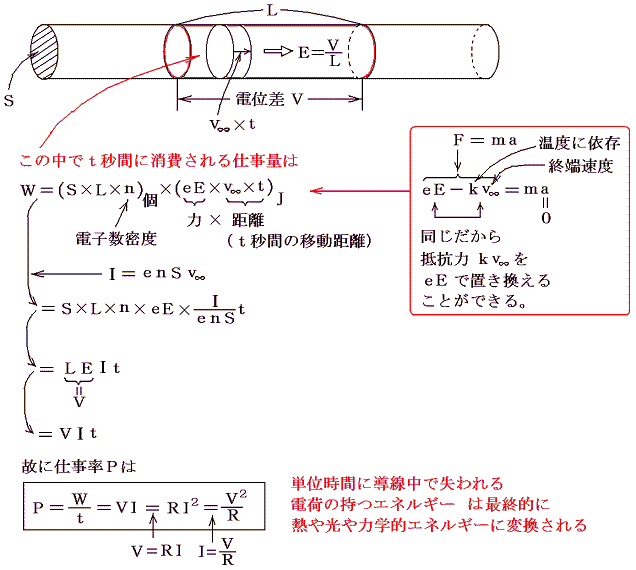
電位差の定義(二点間の電位差Vは、電荷eをその2点間で移動させるに要する仕事Wをeで割ったもの)をもちいるともっと簡単に求まる。
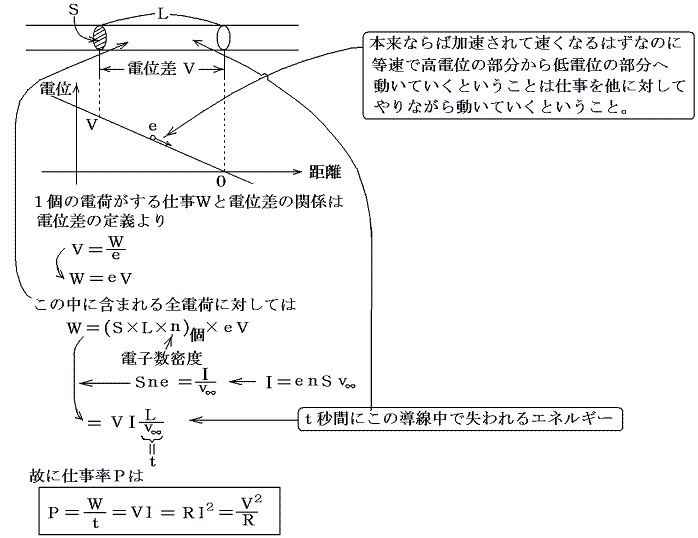
詳細は「発電機とモーターの理論」で論じたのでここでは簡単に説明する。モーターは高校物理でよく出てくる磁場中におかれた平行導線の上を滑る金属棒で構築する。この金属棒に電流を流すと力が発生して導線上を滑って動き外界に対して仕事をすることができる。
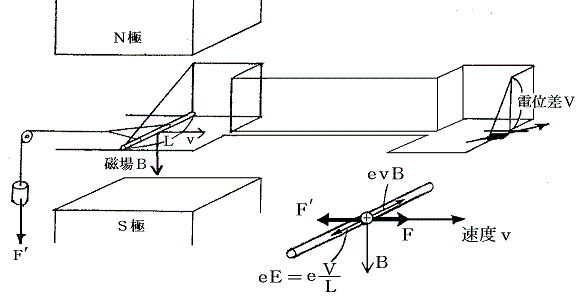
v=一定(a=0)の定常状態では力の釣り合いが実現されているので
evB=eE ・・・・・・・・(1)
F’=F ・・・・・・・・・・・(2)
が成り立つ。これに電磁気学の公式
EL=V ・・・・・・・・・・(3)
F=IBL ・・・・・・・・・(4)
を適用する。(1)式と(3)式から金属棒が動く速度 v は電源電圧 V で決まるv=V/(BL)となる。また(2)式と(4)式よりモーターにかかる負荷の大きさ F’が金属棒を流れる電流の大きさ I を決める。このとき電流が外界に対して単位時間にする仕事(仕事率 P)はその定義より
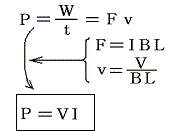
となりお馴染みの結論が得られる。
ただしモーターはオームの法則を満足する回路素子ではないのでこれ以上の変形はできない。